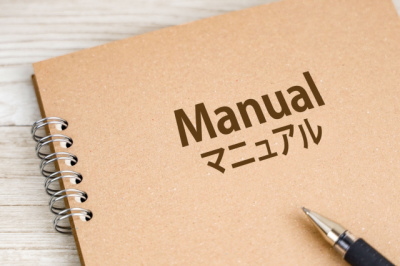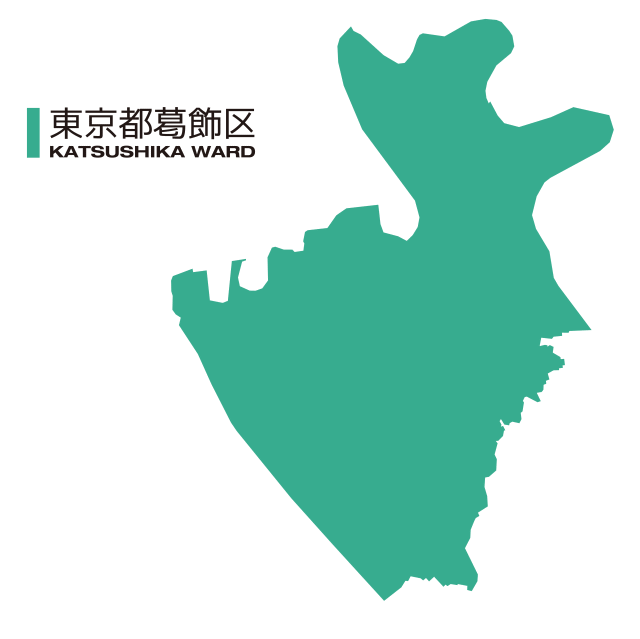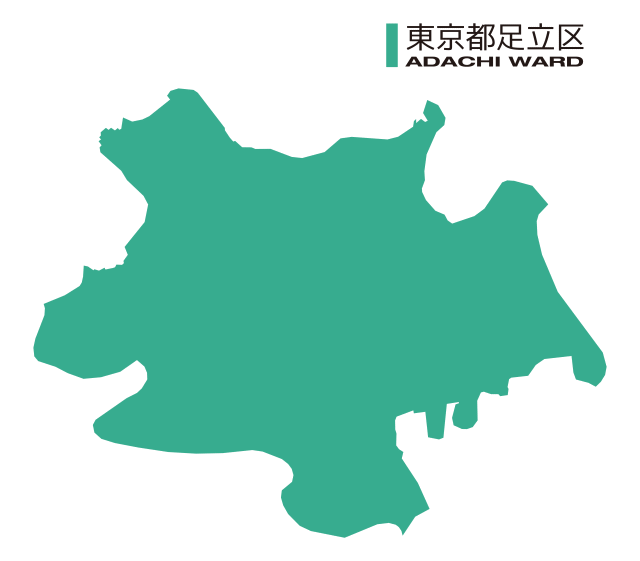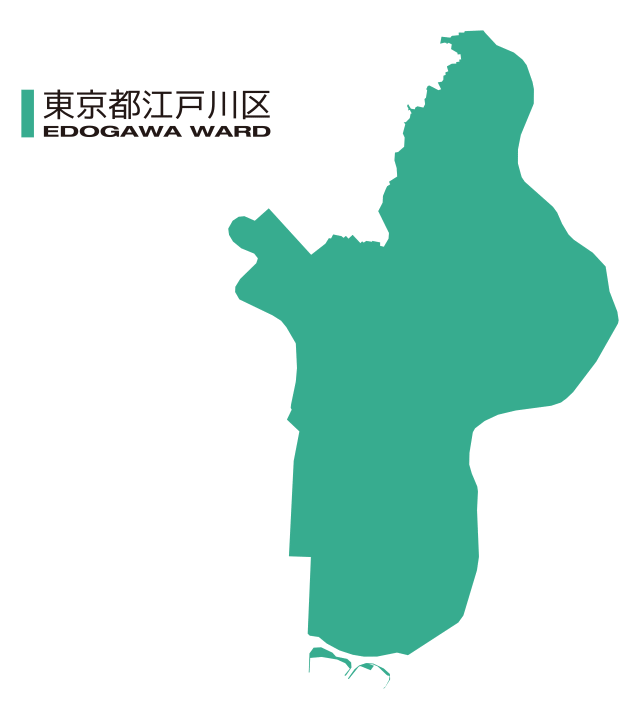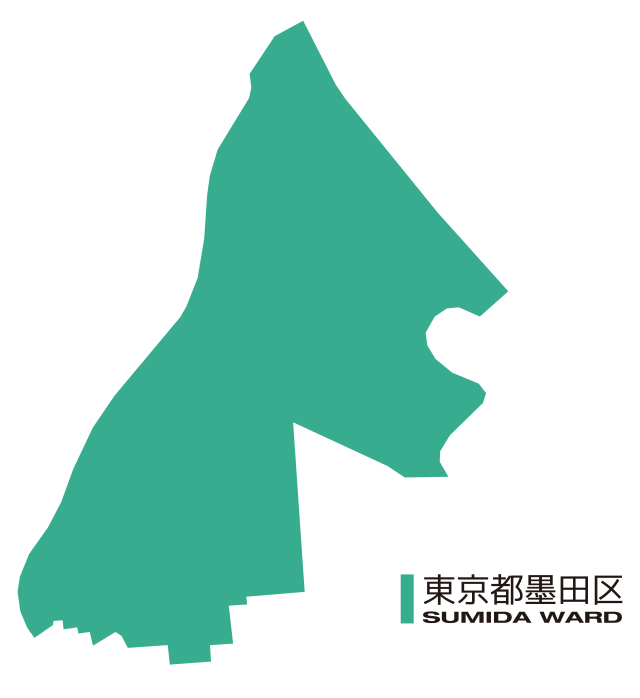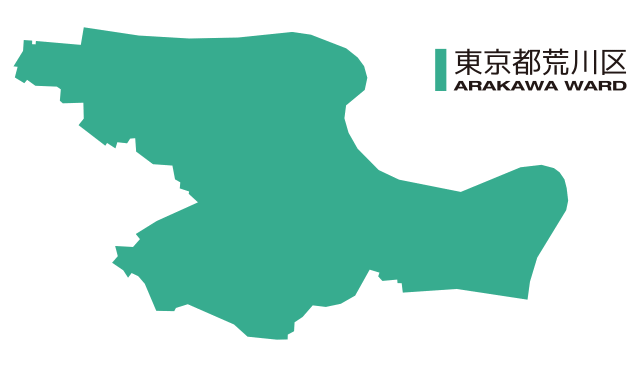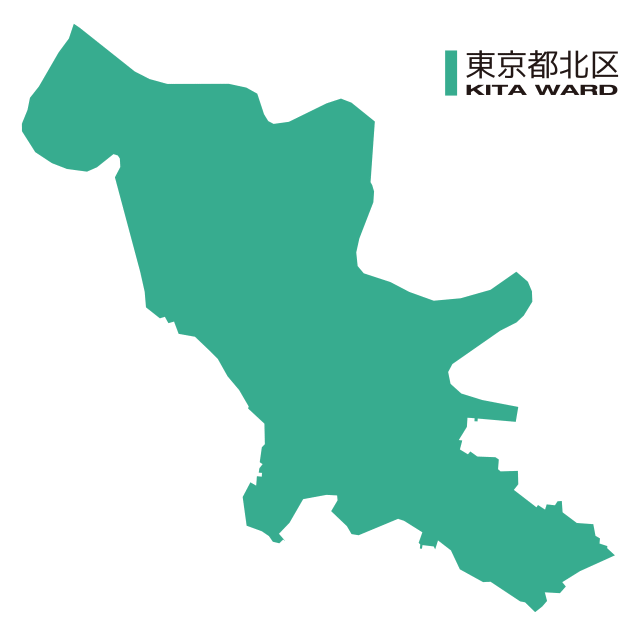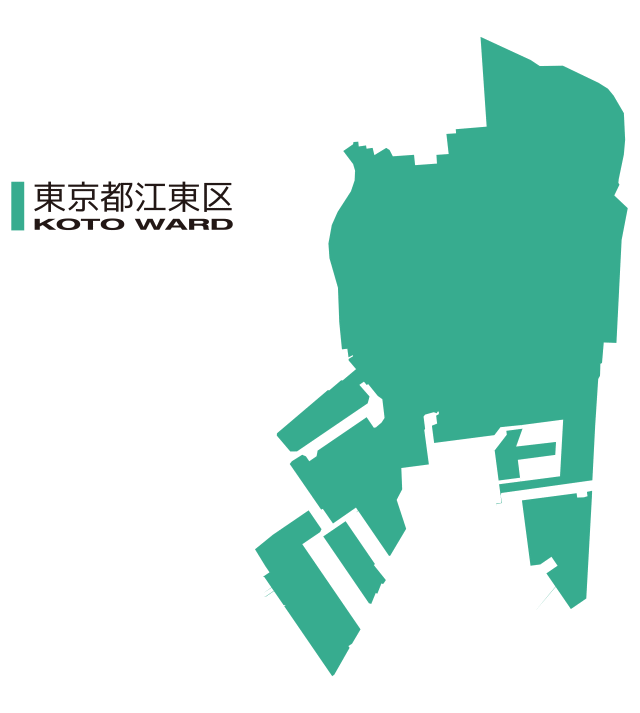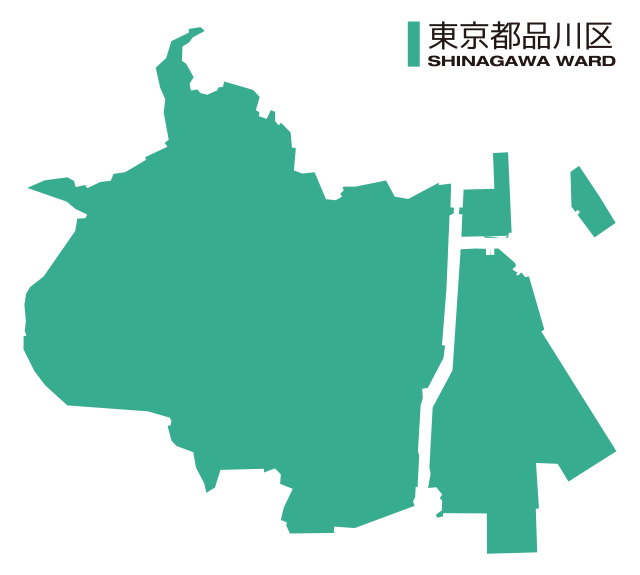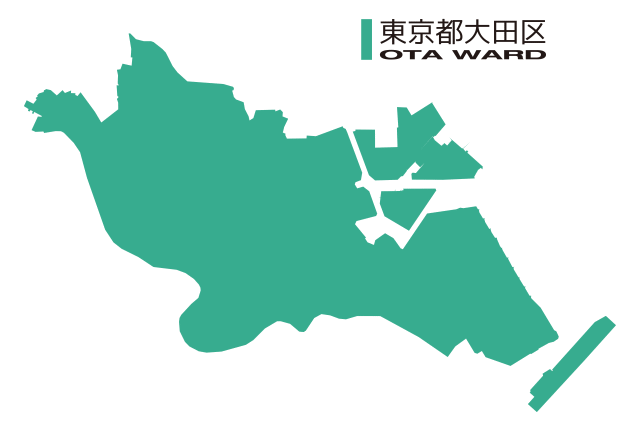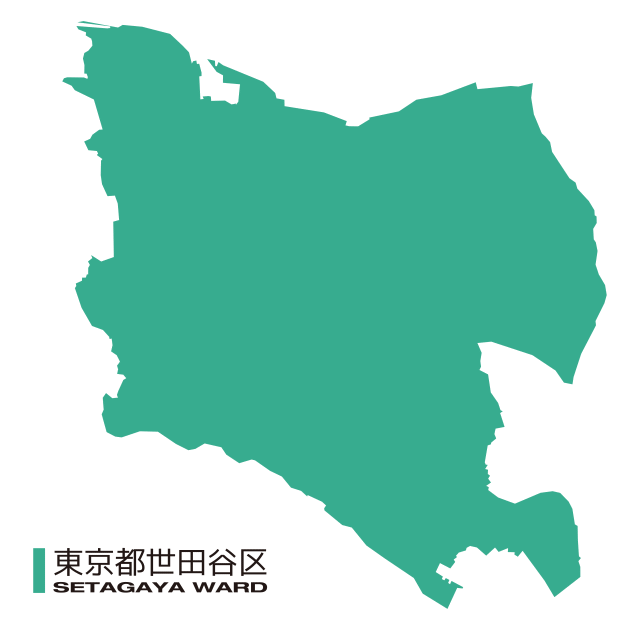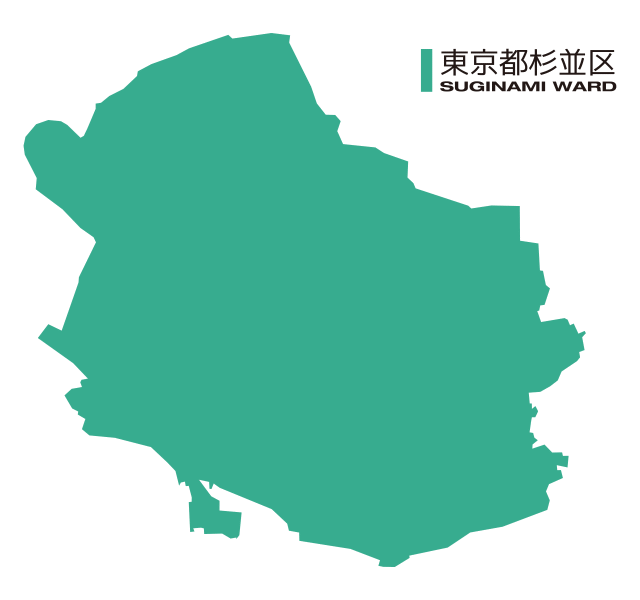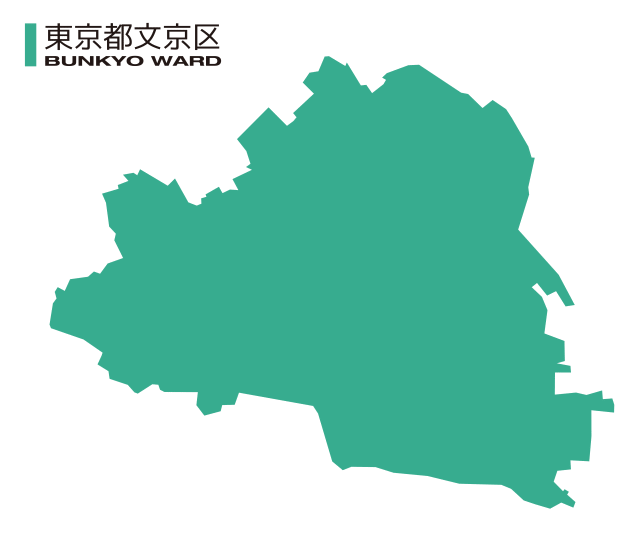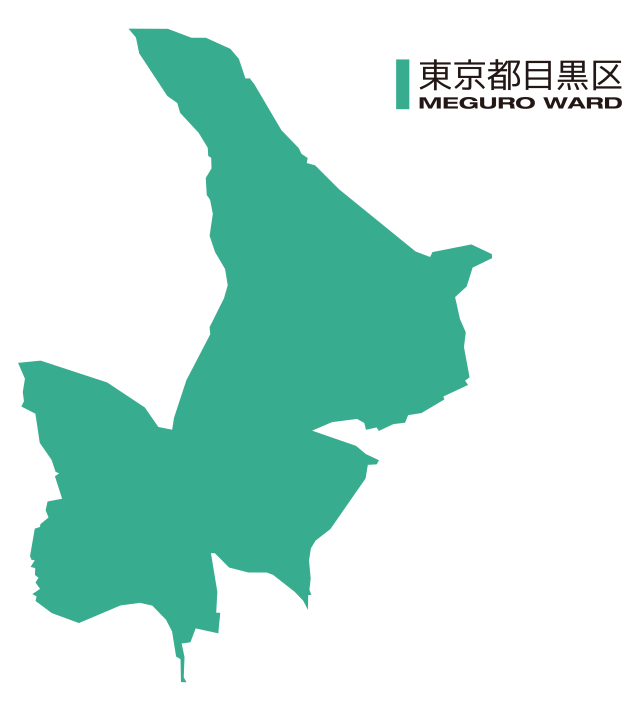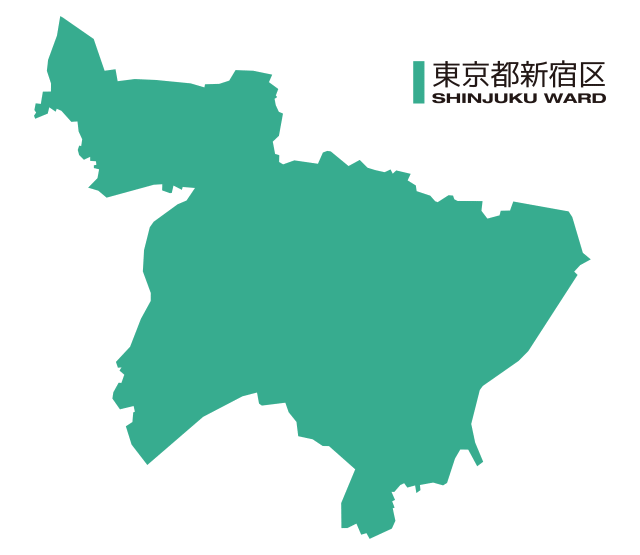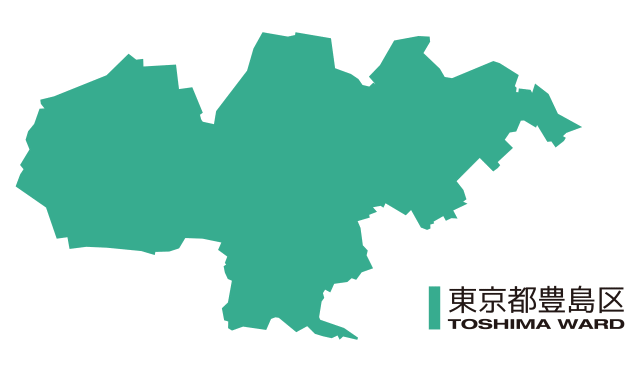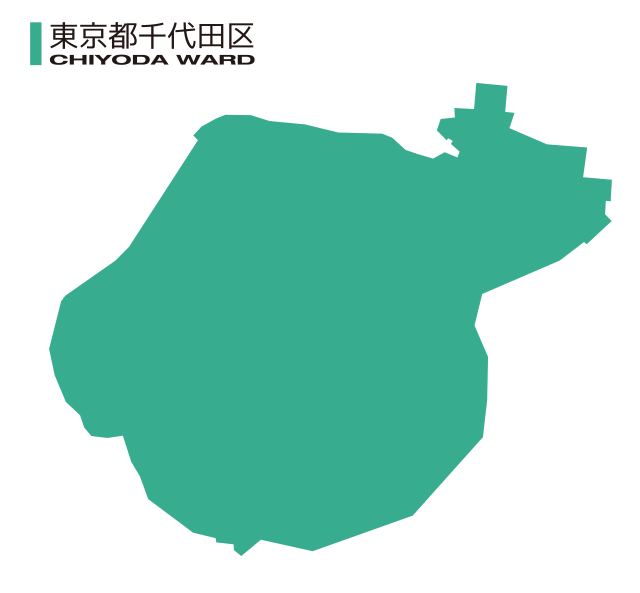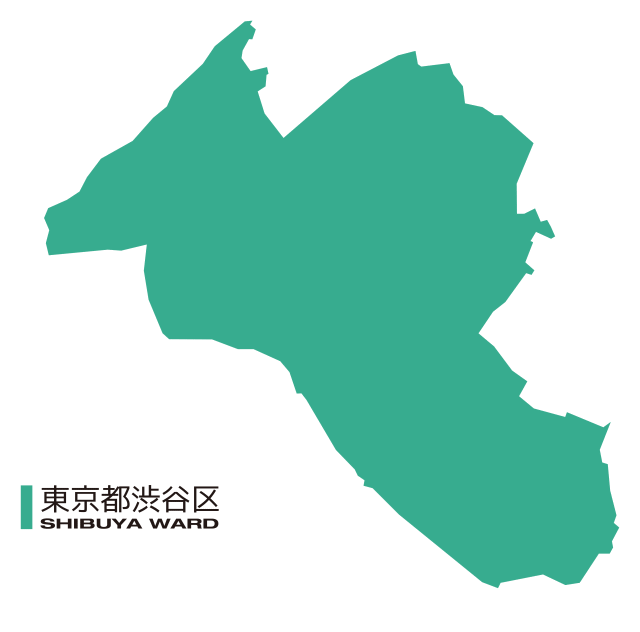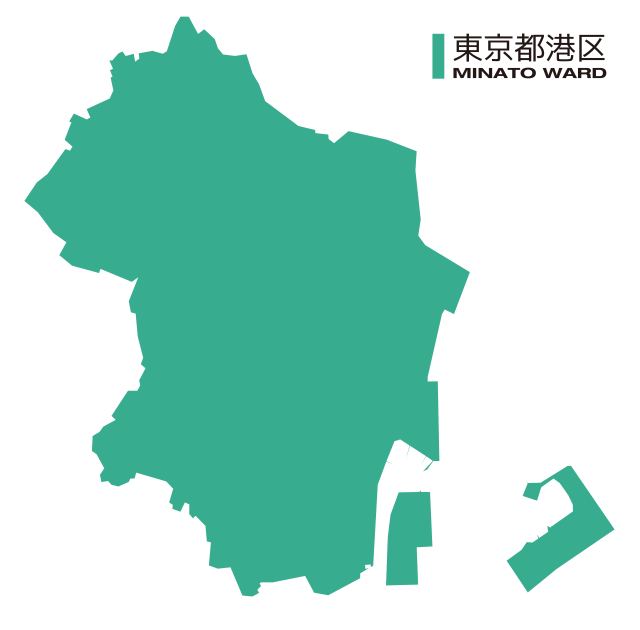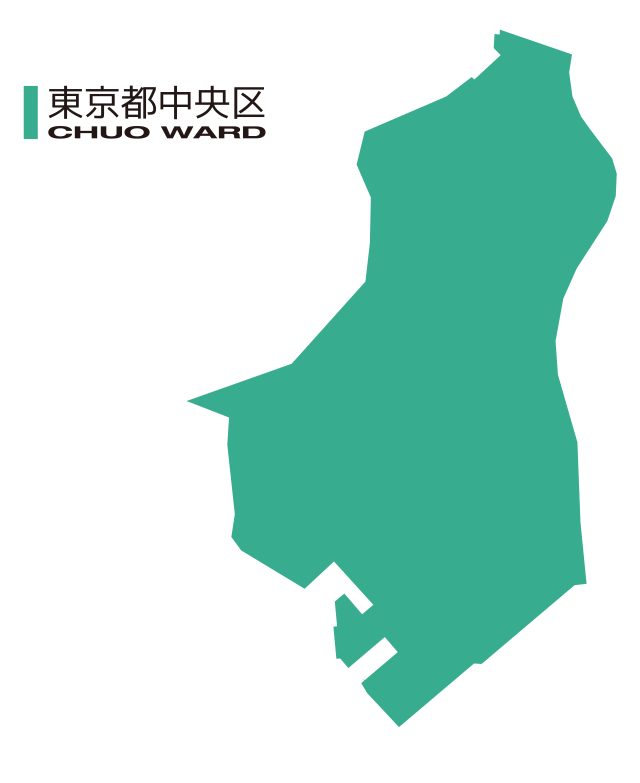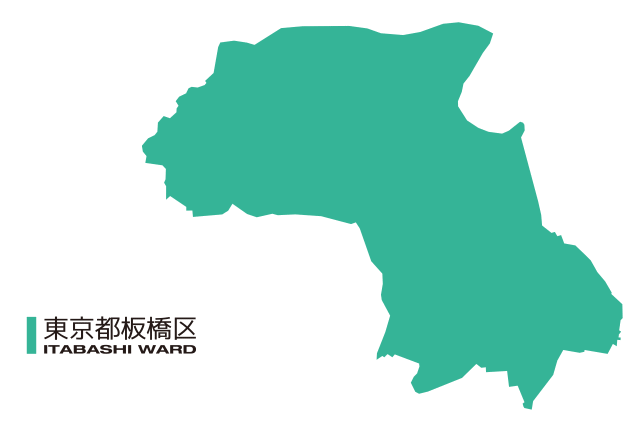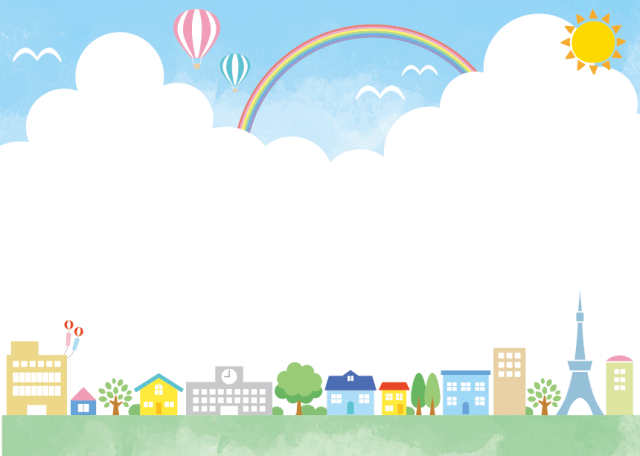千葉県松戸市に位置する八柱霊園は、昭和10年に開設された都立霊園で、都立霊園の中では唯一千葉県にあります。広大な公園型墓地として、豊かな自然環境と落ち着いた雰囲気が特徴です。当事務所では、この八柱霊園での墓じまいや改葬に関する複雑な手続きを、迅速かつ丁寧なサポートで代行いたします。八柱霊園での手続きでお困りの方は、お墓の専門家である行政書士にぜひご相談ください。1.八柱霊園の「墓じまい・改葬手続」のご相談・当事務所は平成21年度に開業したお墓専門の行政書士事務所です。これまでに100件以上の墓じまい・改葬をサポートしてまいりました。都立霊園の手続きにおいても豊富な経験と実績がございますので、安心してご相談いただけます。八柱霊園での手続きは、民間の霊園に比べて提出書類が多く、時間と労力がかかる場合があります。当事務所では、墓地使用者の承継、墓じまい、改葬、現地立会など、お客様の状況に応じた必要な範囲のみをサポートいたします。また、都立霊園の各種手続き全般について経験豊富ですので、複雑な手続きも安心してお任せください。墓じまいや改葬の手続きに不安がある方八柱霊園での手続き方法について知りたい方改葬にかかる費用や必要な書類について確認したい方この様な方々のために、わかりやすく丁寧にご説明させていただきます。当事務所が提供する具体的な業務内容については、都立霊園の墓じまい・改葬手続代行のページをご覧ください。また、都立霊園の各種手続きや申請に必要な書類については、都立霊園の申込方法・要件・墓地の種類のページに詳しく掲載しております。・この様な方にお勧めします。当事務所は、以下のようなご希望をお持ちの方に最適なサポートを提供します。遠方に住んでいて、八柱霊園での改葬を希望している方お墓の承継者がいないので、永代供養墓に移したいと考えている方墓地の引越しや施設変更を考えているが、手続きに不安を感じる方八柱霊園をはじめとするお墓の手続きにおいて、当事務所の深い知識と豊富な経験を活かし、お客様の大切な手続きを迅速かつ丁寧にお手伝いいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。都立霊園の手続きは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!都立霊園の墓じまい・お墓の引越し(改葬)なら ご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから2.八柱霊園の概要・八柱霊園は千葉県松戸市に位置し、昭和10年に開設された公園型墓地です。都立霊園の中では唯一千葉県にあり、総面積は多磨霊園に次ぐ約104.6ヘクタールの広大な霊園です。・八柱霊園正門までの道路(県道51号)には、700mに渡りケヤキが植えられており、自然豊かな落ち着いた風情の参道です。又、参道の両側には、老舗の石材店が数多く並んでおりますので、お墓を建立する場合など、霊園から徒歩数分で石材店に行く事が出来ます。3.八柱霊園の墓じまいの流れ・八柱霊園から他の都立霊園の合葬埋葬施設(小平・八王子・多摩霊園)に施設変更する場合、②民営霊園の永代供養墓等に改葬する場合、それぞれの流れについて解説いたします。(1)墓じまい+施設変更(小平-多摩-八柱)施設変更とは、現在八柱霊園にお持ちのお墓を墓じまいし、都立霊園が提供する合葬埋蔵施設へ改葬する制度です。この制度を利用できるのは、小平霊園、多磨霊園、八柱霊園に設置されている合葬埋蔵施設となります。ここでは、八柱霊園におけるこの施設変更の流れについて詳しく解説いたします。①施設変更の仮予約・書類の取得最初に八柱霊園管理事務所(TEL:047-387-2181 千葉県松戸市田中新田48-2)に連絡を行い、施設変更の仮予約をします。尚、施設変更に関する書類は、仮予約後に管理事務所から郵送で届きます。②石材店の決定八柱霊園で施設変更する場合、現在所有している墓地を更地に戻して返還する必要があります。このため、撤去を依頼する石材店を決める必要があります。尚、都立霊園の場合、指定石材店はありませんので、ご自身で石材店を選び契約を行う事になります。又、施設変更の申込書類は、石材店の押印をして提出する書類があります。このため、申込日までに石材店から押印をもらう必要があります。③施設の変更の申込施設変更申込期間(7月.10月.12月初旬から中旬の年3回)内に八柱霊園管理事務所で手続きを行います。書類に不足があると、再度、管理事務所で手続きを行う事にもなりかねません。手続が一度で済むよう申請書類(施設変更申請書等)、添付書類(住民票、印鑑証明書等)等の必要な書類一式を確認した上で霊園管理事務所に行きましょう。(念のため実印・認印も持参しましょう。)④改葬手続施設変更の手続き完了後2~3か月程度の期間を経て「合葬埋葬施設の使用許可証」が、ご自宅に郵送されます。この使用許可書等を持参し、再度、八柱霊園管理事務所で改葬の手続きを行います。手続が終わりましたら改葬許可申請書が発行されますので、この申請書を松戸市 市民部 市民課(TEL:047-366-7340)に提出して改葬許可証を取得します。※松戸市役所 支所で改葬手続を行うことも出来ます。八柱霊園付近の支所は常盤平支所(TEL:047-387-2131 松戸市常盤平3丁目30番地)東松戸支所(TEL:047-703-0610 松戸市東松戸2丁目14番地の1 ひがまつテラス2F)いずれの支所も八柱霊園から車で10分程度の距離になります。⑤遺骨の取出し+改葬改葬許可証が無事取得出来ましたら、お墓じまい及び改葬の日程を関係先と調整して決めます。当日、お墓を撤去する石材店にカロートから遺骨を取出してもらい、改葬先の霊園に遺骨を引き渡し完了となります。(お墓の撤去は、後日石材店により行われます。)以上が、八柱霊園のお墓から合葬埋葬施設に改葬する流れになります。⑥墓じまい+施設変更のフロー図STEP施設変更の仮予約・書類取得八柱霊園管理事務所に連絡し、施設変更の仮予約を行います。申請に必要な書類は、この仮予約後に管理事務所から郵送で届きます。STEP申請書類の準備書類が到着しましたら、内容を確認し記入可能な箇所は記入を行います。又、申請時に添付する住民票、印鑑証明書なども申請前に取得しておきます。(但し、有効期間が3か月になりますので、申請日受付け日を確認した上で取得して下さい。)STEP申込手続(八柱霊園管理事務所)施設変更申請書等の書類及び添付書類一式を持参して、八柱霊園で施設変更手続を行います。(年3回の申込受付期間内に行う必要があります。)STEP改葬手続(管理事務所+松戸市役所)八柱霊園から合葬施設の使用許可証が届きましたら、再度、管理事務所で改葬の手続を行う必要があります。改葬手続完了後に、改葬許可申請書が発行されます。次に、この書類を松戸市役所(又は、支所)に提出に提出し改葬許可証を取得します。STEP施設変更石材店の日程調整を行い、八柱霊園の墓じまい日を決定します。当日、墓所から遺骨を取出し、改葬先の霊園に移動します。管理事務所で納骨の手続を行い、遺骨を引渡し完了となります。(尚、墓石の撤去は、後日石材店により行われます。)(2)墓じまい+民営の永代供養墓等に改葬八柱霊園の墓所を墓じまいし、民営霊園の永代供養墓等に改葬する流れについて解説いたします。①ご遺骨の埋葬先を決める。八柱霊園の墓じまいを行う場合、埋葬されている遺骨の改葬先を考えておく必要があります。沢山の霊園等がありますので、ご自宅近くの霊園等のある程度の範囲、おおよその費用を考えた上で、霊園選びを始めた方が良いかと思います。②墓地返還書類の取得改葬先の霊園が決まりましたら、次に八柱霊園管理事務所(TEL:047-387-2181)から墓地返還に関する書類を取得します(管理事務所又は、郵送依頼)。③添付書類の取得墓地返還に関する書類、添付する書類も確認しておきます。①八柱霊園の墓地使用者の印鑑証明書(3か月以内)、改葬先の霊園から発行される②使用許可証(受入れ証明書)を取得しておきます。これらの書類は、墓地返還及び改葬手続の際に提出する書類になります。④墓地返還手続き・改葬手続八柱霊園管理事務所で墓地返還手続きを行います(郵送不可)。書類一式を持参して墓地管理者に提出します。尚、提出する書類に、墓石を撤去する石材店の押印箇所がありますので返還手続き前に、墓石を撤去する石材店を決めておく必要があります。⑤改葬許可申請上記、墓地返還手続きと併せて改葬手続も管理事務所で行います。こちらは、改葬先の霊園の使用許可書(受入れ証明書)の提示が必要になります。書類不足により、再び管理事務所に行かなくても済むよう、忘れものがないか?事前に確認した上で八柱霊園に行きましょう。この手続完了後、改葬許可申請書が渡されますので、松戸市役所で申請を行い改葬許可証を取得し手続完了となります。⑥遺骨の取出し+改葬上記、改葬許可証の取得後、墓じまい及び改葬の日程を石材店等に相談の上で決定することになります。当日、お墓を開けて遺骨を取出し、改葬先の霊園まで移動し納骨を行います。ご住職にご供養をお願する場合は、ご住職の予定も確認しておきましょう。尚、お墓の撤去は、後日、石材店により行われます。⑦墓じまい+改葬のフロー図STEP改葬先の霊園の選択・決定ご遺骨を改葬する霊園を決めて、契約を行います。契約後に手続の際に必要になる墓地使用許可書(受入証明書)を発行して貰います。STEP墓地返還書類の取得・準備郵送又は管理事務所で墓地返還に関する書類を取得します。返還の手続には、印鑑証明書等も必要になりますので、こちらも準備しておきましょう。STEP撤去石材店の決定お墓を撤去する石材店を決めて契約を行います。墓地返還書類に関する「誓約書」は、お墓の撤去を行う石材店の押印が必要になりますので、契約後に押印を頂いておきましょう。STEP墓地返還・改葬手続(管理事務所+松戸市役所)書類の準備が整いましたら、八柱霊園管理事務所で墓地返還・改葬手続を行います。この手続完了後に階層許可申請書が渡されますので、松戸市役所(支所)で改葬許可申請を行います。改葬許可証は当日発行されますので、この許可証を受取り手続完了となります。STEP墓じまい+改葬最後に、墓じまい(ご遺骨の取出し)及び改葬(納骨)する日を石材店、霊園との日程調整を行った上で、決定します。当日、石材店にお墓から遺骨を取り出して貰い、改葬先の霊園に移動し納骨して完了となります。尚、八柱霊園のお墓の撤去は、後日石材により行われます。(3)八柱霊園で墓じまい・改葬する場合の注意点八柱霊園は、東京都が運営する都立霊園になりますので、墓地返還、改葬に関する手続等について、霊園で定められている規則に従い行う事になります。民営の霊園のと比べ、提出する書類も多く管理事務所で手続きを行う必要もあるため、最初にどの様な手続、書類が必要か良く確認した上で手続きに行かないと、何度も管理事務所に行くことになりかねませんのでご注意下さい。又、印鑑証明書、住民票等の公的な書類は、申請日から3か月以内に発行さたものと定められていますので、施設変更等を行う場合は、時間が掛かる場合がありますので、タイミングをみて書類を取得する必要があります。①施設変更を行う場合八柱霊園の一般墓所から合葬埋葬施設に施設変更を行う場合は、施設変更申込で1回、改葬手続で1回と最低でも2回、八柱霊園管理事務所に行き手続きを行うことになります。又、改葬許可証は、松戸市区役所(支所)で発行されますので、こちらの手続きも行う必要があります。②お墓を継ぐ人が墓じまいする場合八柱霊園の墓地所有者が亡くなり、その方が所有していた墓を墓じまいする場合は「使用者変更」の手続きが必要になります。尚、手続きを行うには、祭祀承継者の証明書類(例:遺言書による指定、喪主としての葬儀通知等)が必要になります。この手続きを行い、新たに使用者となった方が墓地返還・改葬等の手続きを進めることになります。(同時に手続きを行うことも可能です。)(4)墓じまい+改葬費用の目安・八柱霊園(千葉県松戸市田中新田48-2)の墓じまい+改葬に掛かる費用を参考に掲載させて頂きます。墓石撤去費(1㎡辺り10万円程度)八柱霊園で墓じまいを行う場合のお墓の撤去代は、一般的な和型の場合、20万円~50万円程度、洋型の場合、10万円~30万円程度が相場と言えます。但し、お墓の面積が広い場合、石材量が多い場合などは、これより高額になる場合があります。石材店に依頼すると見積書を作成して貰えます。数社の石材店に見積書を依頼し、ご自身のお墓の撤去代相場を把握した上で、材店との契約を行って下さい。(石材店により金額に差が出る場合があります。)改葬費(5万円程度~)八柱霊園の一般墓から合葬埋葬施設に施設変更する場合、改葬先の費用は掛からず事務手数料のみ発生することになります。一方、民営の霊園を選択する場合は、霊園の場所、埋葬形式により金額が異なります。永代供養墓の場合、他の遺骨と一緒に埋葬する形式(合祀)で5万円程度~20万円程度、骨壺で埋葬する形式(合葬)は、10万円~50万円程度となり、区画で購入する形式(樹木葬等)では、20万円~100万円程度が相場と言えます。その他の費用事務手数料(数百円~)書類取得費(印鑑証明書、住民票、戸籍等)1通 数百円~ご住職のお布施(供養を行う場合)3万円程度~2.八柱霊園 情報八柱霊園では、令和7年度は「一般埋蔵施設」「芝生埋蔵施設」「合葬埋蔵施設」の3形式で公募が行われました。公募結果と費用の詳細(令和7年度)八柱霊園は、都立霊園の中でも松戸市民も申込可能な唯一の霊園であり、全体的に競争率が低く、費用も安価です。一般埋蔵施設募集区画数は330区画に対し、申込数は447件で、平均競争率は1.4倍でした。募集区画(1.70㎡~6.00㎡)の永代使用料は34万8,500円~123万円です。申込資格は遺骨申込のみで、都内または松戸市に継続して5年以上居住している方に限られます。芝生埋蔵施設募集区画数は60区画に対し、申込数は153件で、競争率は2.6倍でした。募集区画(4.00㎡)の永代使用料は94万4,000円で、年間管理料は3,720円です。合葬埋蔵施設募集総体数は1,440体に対し、申込数は2,223件で、平均競争率は1.5倍でした。遺骨1体あたりの使用料は47,000円~117,000円で、年間管理料はかかりません。八柱霊園は、都立霊園の中でも一般埋蔵施設、合葬埋蔵施設の当選確率が非常に高い狙い目の霊園と言えます。(注)令和7年度の募集は既に終了しています(7月4日締切)。最新の情報は、必ず東京都公園協会の公式サイトでご確認ください。(1)八柱霊園の特徴・霊園の所在地が開設当時、東葛飾郡八柱村であった為、その地名にならい八柱霊園と名付けられました。墓地の種類は、一般墓地(芝生・壁型)・納骨堂、合葬式墓地の3種類になり、松戸市在住の方も申込可能です(都立霊園では八柱霊園のみ可能)。園内にはアカマツ、サクラ、モミジなどの木々が植えられた自然環境の豊かな霊園であり、嘉納治五郎(講道館創設者)、西条八十(詩人・作詞家〔東京ブルース(歌:美空ひばり)・王将(歌:村田英雄)等〕)、大村能章(作曲家〔麦と兵隊(歌:東海林太郎)〕)といった著名人も埋葬されています。八柱霊園 園内マップ(2)お墓の種類一般埋蔵施設(芝生埋蔵施設・壁型埋蔵施設含む)納骨堂施設合葬埋蔵施設令和7年度の八柱霊園では、「一般埋蔵施設」「芝生埋蔵施設」「合葬埋蔵施設」の3形式すべてで募集が行われました。競争率は、一般埋蔵施設が1.4倍、合葬埋蔵施設が1.5倍と、都立霊園の中で最も低い水準でした。(3)園内施設八柱霊園の園内施設は主に下記になります。①トイレ、②水汲み場、③下げ花置場、④桶・杓置場、⑤休憩所(4)補 足八柱霊園は、他の都立霊園と比べ募集数も多い為、その影響で競争率が低くなったものと考えられます。ちなみに一般墓地の永代使用料を最小区画で比較すると・・青山霊園(1.55㎡~)約460万3,500円~谷中霊園(1.50㎡~)約264万1,500円~八柱霊園(1.70㎡~)約34万8,500円~以上の事から、都立霊園の中では一番低い使用料になっています。都立霊園は基本的に、周辺の霊園等と同程度、又は、低く使用料が設定されますので、唯一千葉県にある霊園である為、この使用料が設定されたと思われます。(5)よくある質問(FAQ)開園時間は何時から何時ですか?八柱霊園の開門時間は、正門・西門・東門が7:30~17:00。南中央門・松飛台中央門が8:00~17:00。南門・紙敷門・松飛台門が8:30~17:00とそれぞれ時間が異なっておりますので、ご注意下さい。車で通行可能な門は、西門・東門(南門と南中央門は、土日祝日のみ通行可)になります。休日はありますか?管理事務所・納骨堂の休日は、年末年始の12月29日~1月3日となります。合葬埋蔵施設とは、どの様なものですか?いわゆる納骨堂の一種であり、八柱霊園では、骨壺のまま地下カロートに20年間安置され、その後、遺骨を骨袋に写し共同埋蔵施設に合祀されます。尚、生前に申込が可能で承継者も不要です。個人・夫婦・親子・兄弟など併せた申込(2体又は3体まで)も可能ですが、埋蔵予定者に申込者が含まれること、埋蔵予定者が居住要件を満たすことなどの条件があります。車イス・お墓の清掃道具などの貸し出しは、ありますか?八柱霊園に用意されている、貸出用の車イスは1台となります。お墓の清掃道具の貸出しも行われておりますので、使用を希望される方は、管理事務所にその旨お伝え下さい。八柱霊園にお墓を建てるメリットは?競争率・使用料ともに他の都立霊園に比べ非常に低くなっております。令和7年度の競争率は、一般埋蔵施設が1.4倍、合葬埋蔵施設が1.5倍と、都立霊園の中で最も当選確率が高い霊園と言えます。永代使用料も34万8,500円からと安価です。東京都運営の安心感のある霊園に埋葬したいとお考えの方には、最も狙い目の霊園です。一般的な墓を建立される場合も、使用料で節約出来た分で墓石のグレードアップするなども考えられます。八柱霊園にお墓を建てるデメリットは?八柱霊園までに都心から1時間程度の時間が必要になります。電車の場合、最寄り駅からも遠い為、バスかタクシーでお墓参りに行くことになります。このアクセスがあまり良くない状況が気になる方は、民営のお墓も検討された方が良いかと思います。また、募集が1年に1回となっており、抽選に外れた場合、他の霊園等を改めて探すことになります。(競争率が都立霊園で最も低いとはいえ、抽選となるため当選が保証されるわけではありません。)手元にあるご遺骨を早目に埋葬したい場合などは、民間の霊園も考えておく必要があります。5.関連リンク・八柱霊園(東京都公園協会)の公式サイトは、こちらから八柱霊園サイト・八柱霊園の改葬許可申請は、松戸市役所(支所)で行う必要があります。松戸市役所サイト6.アクセス情報● 所在地:〒270-2255 千葉県松戸市田中新田48-2TEL:047-387-2181(霊園管理事務所)・「JR武蔵野線」新八柱駅・「新京成線」八柱駅(南口)バス停1番乗り場 ~(東松戸駅行・紙敷車庫行)~ 八柱霊園駅前 下車 ~ 霊園(徒歩5分) ・「JR武蔵野線」東松戸駅 バス停3番乗り場 ~(八柱駅行)~ 八柱霊園駅前 下車 ~ 霊園(徒歩5分)7.周辺の見どころ(1)東松戸 ゆいの花公園(霊園から徒歩15分程度)・季節の花々やハーブ等が植えられている美しい植物公園です(平成19年に開園)。季節の花が鑑賞できる花の丘、バラのアーチ、ツバキが植えられている丘など見どころ満載です。マグノリアハウスという公園管理施設では、月2,3回、ハーブティ作りなど講座が行われています。又、春・冬の年2回、コンサート等のイベントも行われています。東松戸 ゆいの花公園(2)21世紀の森と広場(霊園から車で7分程度)・広大な公園(50.5ヘクタール)内には、水鳥等の生息を守る為に作られた千駄堀池、草原・湿地・水辺の昆虫や植物が観察できる野草園、竪穴式住居が設置されている縄文の森などの施設があり、自然の中で1日を楽しめる公園です。又、松戸市立博物館、森のホール21も隣接されています。21世紀の森と広場(3)戸定邸・戸定歴史館(霊園から車で20分程度)・戸定が丘歴史公園内に、水戸藩最後の藩主・徳川昭武が住んでいた戸定邸が、公開されています。こちらは、明治時代の徳川家の住居がほぼ完全に残る唯一の建物にあり、国の重要文化財に指定されています。戸定歴史館には、徳川昭武の遺品を中心に松戸徳川家、徳川慶喜家に関連した書物、調度品等も公開されています。戸定邸・戸定歴史館8.八柱霊園 まとめ八柱霊園は、千葉県松戸市に位置する都立霊園で、広大な敷地と豊かな自然環境が特徴です。東京都心から電車でのアクセスも便利で、松戸駅からの交通も良好です。霊園内には四季折々の風景が楽しめる自然豊かな空間が広がり、静かで落ち着いた雰囲気を提供しています。また、八柱霊園は平坦な地形で、歩きやすくお参りもしやすい環境が整っています。敷地内は手入れが行き届いており、整備された通路や施設が多く、霊園を訪れる人々にとって快適で安心な空間となっています。周囲の緑との調和が取れた美しい霊園です。墓じまいや改葬をお考えの場合八柱霊園も他の都立霊園と同様に、墓じまいや改葬を行う場合、所定の手続きを経る必要があります。具体的には、墓地の管理事務所にて、改葬許可申請書などの必要書類を提出することが求められます。手続きにおいては、必要書類の準備や提出方法が複雑であり、ご自身で進めることが難しい場合もあります。そのため、専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることも可能です。当事務所のサポート当事務所では、八柱霊園をはじめとした都立霊園での墓じまいや改葬の手続きについて、専門的なサポートを提供しています。改葬や墓じまいの手続きは複雑で、必要な書類の準備や提出方法に不安を感じる方も多いです。特に初めて手続きを行う場合、どこから始めて良いか、どの様な書類を準備すれば良いかなど、わからない方もおります。また、ご自身では八柱霊園の管理事務所に行くことが難しい方もおります。当事務所は、数多くの霊園での手続きサポート実績を有しており、お客様が必要とする書類の作成や提出の代行、各種手続きの進行管理を行います。これにより、手続きに伴う負担を軽減し、安心して進めることができます。もし、八柱霊園での改葬や墓じまいをお考えの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。迅速かつ確実にサポートいたします。都立霊園の手続きは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!都立霊園の墓じまい・お墓の引越し(改葬)なら ご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから事務所案内大塚法務行政書士の事務所案内は、こちらから事務所実績当事務所で行わせて頂いた墓じまい・改葬の実績は、こちらからお客様の声当事務所にご依頼頂いたお客様のアンケートはこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから都立霊園の記事TOP・都立霊園の改葬・墓じまいは、こちらから