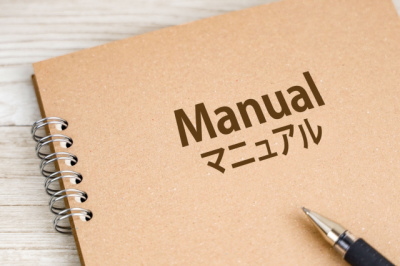・墓じまいを進める中で、寺院への「お布施」について疑問を感じる方は少なくありません。
「いくら包めばいいの?」「いつ渡すのが適切?」「封筒の書き方は?」といった具体的な疑問から、「離檀料との違いは何?」という根本的な疑問まで、お布施に関する悩みは尽きないものです。
このページでは、墓じまいにおけるお布施に特化し、その適切な金額相場、渡すタイミング、封筒の正しい書き方、さらには離檀料との明確な違いや、トラブルを避けるための注意点までを行政書士が徹底解説いたします。
安心して墓じまいを進めるための参考にして下さい。
1.墓じまいにおける「お布施」とは?
墓じまいを進める上で、寺院に渡す「お布施」について正しく理解しておくことが大切です。
(1)お布施の基本的な意味
お布施とは、僧侶への対価ではなく、仏様への感謝の気持ちを表すものです。僧侶が行う読経や供養といった仏事に対する感謝や、寺院の維持・運営への協力といった意味合いが込められています。そのため、決まった金額があるわけではなく、施主の気持ちによって包む金額は異なります。
(2)お布施と離檀料との違い

墓じまいにおいては、「お布施」と「離檀料」が混同されがちですが、これらは異なるものです。
- お布施(閉眼供養など): 墓じまいの際に行われる「閉眼供養(魂抜き)」などの仏事に対してお渡しするものです。
- 離檀料:檀家関係を解消する際に、これまでの寺院へのお礼や、寺院運営への協力金として任意で渡す金銭です。法的な支払い義務はありません。
寺院によっては、離檀料という明確な項目を設けず、閉眼供養のお布施に「これまでの感謝」という意味合いを含めて、やや多めの金額を提示するケースもあります。もし不明な点があれば、具体的な内容を寺院に確認することが重要です。
・離檀料について詳しく知りたい方は、【離檀料の相場】墓じまい・改葬時の注意点 もご覧ください。
2. 墓じまいのお布施の相場と目安
お布施に決まった金額はありませんが、一般的な目安を知っておくことで準備が進めやすくなります。
(1)閉眼供養(魂抜き)のお布施
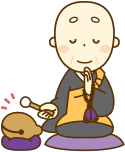
墓じまいの際に行う「閉眼供養(魂抜き)」のお布施は、一般的に3万円~5万円程度が相場と言われています。これは、お墓から仏様の魂を抜いていただく儀式に対する感謝の気持ちです。
ただし、地域や寺院の格式、ご住職との関係性、法要の規模によって幅があります。事前に寺院に直接尋ねるのが最も確実な方法です。
(2)お礼のお布施(離檀の際)
閉眼供養のお布施とは別に、長年お世話になった感謝の気持ちとして、別途「お礼のお布施」を包むケースもあります。これは、離檀料とは異なり、あくまで「お布施」として感謝の気持ちを示すものです。
この場合、閉眼供養のお布施に上乗せして渡すか、別々の封筒で渡すかは寺院の慣習やご自身の気持ちによります。金額は、5万円~20万円程度を目安とすることが多いようです。高額な離檀料トラブルを避けるためにも、寺院との円滑な関係を維持する上で有効な場合もあります。
(3)お車代・御膳料について
ご住職が寺院から墓地まで移動される際、施主側が交通費を負担するのが「お車代」です。また、法要後にお食事の席を設けない場合に渡すのが「御膳料」です。
- お車代:5千円~1万円程度が目安です。タクシー代やガソリン代などを考慮して包みましょう。
- 御膳料:5千円~2万円程度が目安です。ご住職がお食事を辞退された場合に渡します。
これらも「お布施」とは別に、別の封筒で渡すのがマナーです。
3. お布施を渡すタイミング
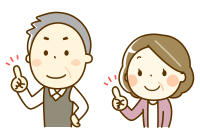
お布施を渡すタイミングは、閉眼供養の前後が一般的です。
- 閉眼供養前: 供養が始まる前に、ご住職への挨拶とともに渡すのが丁寧です。
- 閉眼供養後: 供養が無事に終わったことへの感謝を伝えながら渡すのも良いでしょう。
いずれの場合も、感謝の言葉を添えて渡すことが最も大切です。袱紗(ふくさ)に包んで渡すのがより丁寧な方法とされていますが、白無地の封筒にきれいなお札を入れて渡すだけでも失礼にはあたりません。直接手渡しはせず、一言添えて差し出すようにしましょう。
4. お布施の封筒の書き方とマナー
お布施を渡す際の封筒の選び方や書き方にもマナーがあります。失礼のないように準備しましょう。
(1)封筒の種類
お布施には、白無地の封筒か、水引が印刷されたのし袋(白黒または双銀の結び切りは避け、黄白または赤白の蝶結びが良い)を使用します。蓮の絵柄が入った仏事用の封筒も適切です。
郵便番号欄がないものを選びましょう。また、不幸が重なることを連想させる二重封筒は避けるのが一般的です。
(2)表書きの書き方
封筒の表側には、以下の情報を記入します。
- 上段: 「御布施(おふせ)」または「御礼(おんれい)」と記入します。筆ペンや毛筆で丁寧に書きましょう。
- 下段: 施主の氏名、または「〇〇家」と記入します。複数人の連名の場合は、代表者の氏名を中央に書き、その左側に小さい文字で他の連名者の氏名を書きます。
(3)中袋・裏書きの書き方
中袋がある場合は、中袋に金額と住所、氏名を記入します。中袋がない場合は、封筒の裏側に記入しましょう。
- 金額: 旧字体の漢数字(例: 壱, 弐, 参, 萬など)で記入します。「金 参萬円」のように書きます。
- 住所・氏名: 郵便番号と住所、施主の氏名を記入します。
【お布施の表書きに関する補足と当事務所の経験】
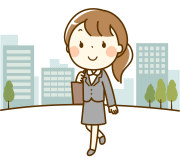
一般的には「御布施」などと記載する方が多いですが、宗派によっては「御布施」と言わない場合もあります。複数のご住職に質問させていただきましたが、やはり宗派によって書き方に違いがあるそうです。
確実な方法はご住職に確認することですが、わざわざ封筒の書き方を電話などで確認するのは、かえってご迷惑に感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、当事務所では、お客様からお預かりしたお布施を白い封筒に入れ、何も書かずにお渡ししています。間違った表書きをするよりも、何も書かない方が失礼にあたることではないと考えています。
現在まで当事務所がお客様に代わりお布施をお渡しする場合、何も書かずにお渡しさせていただいておりますが、特に何か言われたことはありません。どちらかと言いますと、形式よりも中身が重要ですので、お金の入れ忘れがないよう、きちんと確認されたほうが良いかと思います。また、お渡しする際には、今までのお礼をきちんと申し上げましょう。
もし、きちんと書いてお渡ししたいお気持ちがある場合は、出入りの石材店などに確認してみる方法もあります。
5. お布施に関する注意点とトラブル回避
お布施を渡す際に気をつけたいことや、トラブルを避けるためのポイントです。
(1)金額の確認方法
お布施の金額に迷ったら、まずは寺院に直接尋ねるのが最も確実です。直接的な表現を避け、「皆様はどのくらいお包みになっていらっしゃいますか」「お布施はいかほどがよろしいでしょうか」といった聞き方をすると良いでしょう。また、親族や詳しい方、お墓の専門家に相談するのも有効です。
(2)現金書留や振り込みは可能か?
お布施は、本来手渡しが最も丁寧な方法とされています。しかし、遠方で直接渡すのが難しい場合や、寺院の意向によっては、現金書留や銀行振り込みが可能な場合もあります。事前に寺院に確認を取りましょう。
(3)領収書はもらえない?
お布施は「感謝の気持ち」であるため、一般的な商品やサービスに対する対価とは異なり、領収書が発行されないことがほとんどです。しかし、こちらからお願いすることで発行される場合もあります。
ご住職にお願いし、なるべく領収書を頂きましょう。(お金の受け渡しは、書類で残した方が後々のトラブルを未然に防げます。)
(4)高額請求されたと感じたら
「お布施」という名目であっても、一般的な相場を著しく超える金額を請求されたと感じる場合は、まず冷静にその内訳や理由を確認しましょう。納得できない場合は、その場で即答せず、一度持ち帰って家族や弁護士、国民生活センターなどの専門機関に相談することを検討してください。
・高額な離檀料(お布施)を請求された場合の対処法は、【高額離檀料請求】墓じまい対処法 で詳しく解説しています。
6.まとめ

墓じまいにおけるお布施は、ご住職や寺院への感謝の気持ちを表す大切な行為です。相場がないため戸惑うことも多いですが、事前に情報を集め、不明な点は直接寺院に確認することが、円満な墓じまいの鍵となります。
お布施の金額、渡すタイミング、封筒の書き方など、適切なマナーを守ることで、ご住職との良好な関係を維持し、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。もしお布施や離檀に関して不安な点があれば、一人で悩まずに専門家にご相談ください。
お布施について(現在の状況)

(令和7年現在)
この記事を作成し10年以上の経ちましたが、現在でも、お布施はいくら渡せば良いですか?と聞かる事が多々あります。お布施の金額は確かにいくら?と言うものはありません。基本的にはお気持ちの範囲でお渡しするものです。
しかし、一定の相場というものも現実にはあり、例えばご供養をして頂いて数千円をお渡しるするのは失礼かと思います。基本的には3万円~5万円程度が相場と言えます。
この相場は今でも特に変わりはありません。ちなみにご住職の紹介センター等でお願いした場合も、お布施3万円+お車代5千円程度になりますので、恥ずかしくない額としては3万円程度と言えるかと思います。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)