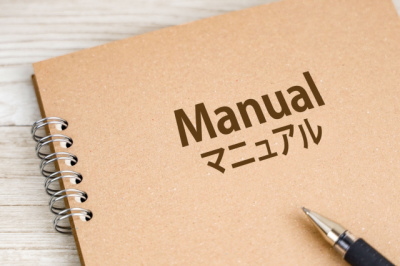近年、「墓じまい」を選択する方が急速に増えています。
厚生労働省の発表によると、墓じまい・改葬の件数は2004年度の約6.8万件から、2022年度には約15.1万件と、わずか20年足らずで倍以上に増加していることが明らかになっています。
この現象の背後には、現代社会特有の様々な理由と背景が存在します。
このページでは、墓じまいが増加している社会的な背景と主な理由を深く掘り下げ、墓じまいがもたらすメリット・デメリット、さらには今後考えられる動向や後悔しないためのポイントについて、お墓専門の行政書士が分かりやすく徹底解説します。
1.墓じまいが社会的に増加している背景と主な理由
墓じまいの件数が近年、急速に増加している背景には、少子高齢化や核家族化といった社会構造の変化が大きく影響しています。具体的には、以下の点が主な理由として挙げられます。
(1)核家族化・少子高齢化による「承継者問題」

現代社会では、昔ながらの大家族制度が減少し、核家族化が進んでいます。これにより、先祖代々のお墓を継ぐ人がいなくなる「承継者不在」の問題が顕在化しています。また、少子化により子供の数が減り、お墓を継ぐ世代がいなくなる、あるいは複数のお墓を継ぐ負担が増えるという状況も、墓じまいを考える大きな要因となっています。
ご自身が亡くなった後、お墓が無縁墓になってしまうことを案じ、元気なうちに墓じまいを選択する方が増えているのです。
→ 承継者問題については、【お墓の承継トラブル】Q&A・事例と対策 で詳しく解説していますのでご参照ください。
(2)寺院や墓地にかかる「経済的負担」の増大

特に寺院墓地の場合、お墓の管理費の他に、お布施や寄付など、金銭的な負担が続くことに難しさを感じる方が少なくありません。 檀家としての付き合いが希薄になる中で、これらの負担が重く感じられ、墓じまいを検討するきっかけとなることがあります。
墓じまいの費用全般や、お布施、離檀料に関する具体的な情報は、以下の記事で詳しく解説しています。
→ 墓じまいの費用全般については、【墓じまい費用】安く抑える方法と相場
→ 費用負担の具体的な話し合いについては、 【墓じまい費用】誰が負担?相場・内訳と話し合い
→ お布施については、 【墓じまいのお布施】相場・渡し方・注意点
→ 離檀料については、 【離檀料の相場】墓じまい・改葬時の注意点
(3)お墓への価値観の変化と「多様な供養方法」の普及
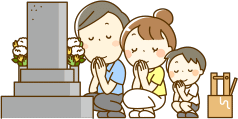
現代では、「先祖代々のお墓に入るべき」という伝統的な考え方にとらわれず、個人の価値観に基づいた多様な供養の形が受け入れられるようになりました。永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨など、承継者を必要としない、あるいは管理の手間が少ない供養方法が普及したことも、墓じまい増加の大きな要因です。
新しい供養先については、以下の記事をご参照ください。
→ 改葬先の選び方: 【改葬先】選び方と失敗しない注意点
→ 永代供養墓について: 【永代供養墓】基礎知識・選び方
→ 納骨堂について: 【納骨堂とは】選び方・費用・注意点を解説
→ 樹木葬について: 【樹木葬】基礎知識・選び方
→ 散骨について: 【散骨の基礎知識】費用・注意点を解説
(4)遠方からの管理負担の増加

進学や就職を機に地元を離れ、都市部に定住する人が増えた結果、実家や故郷にあるお墓が遠方になり、お墓参りや管理が大きな負担となるケースが増えています。特に高齢になると、遠方へ移動すること自体が困難になるため、墓じまいを検討する方が多くなっています。
→ 遠方のお墓の墓じまいについては、【遠方のお墓】墓じまい手続きの流れと注意点 で詳しく解説しています。
2. 墓じまいをするメリット(得られる安心と負担軽減)
墓じまいには、様々な心理的、物理的なメリットがあります。主なメリットは以下の通りです。
(1)将来の「無縁墓化」を回避できる
お墓の承継者がいない、あるいは今後いなくなる可能性が高い場合でも、墓じまいをして永代供養墓などに改葬することで、ご先祖様のお骨が無縁仏となることを防ぎ、安心して永続的な供養を続けることができます。
(2)子孫への精神的・経済的「負担を軽減」できる
お墓の管理は、年間管理費の支払い、清掃、法要の手配など、子孫にとって継続的な精神的・経済的負担となります。墓じまいをすることで、これらの負担を将来の世代に引き継ぐことなく解消できます。
(3)自身が元気なうちに「終活」として心の安心を得られる
ご自身が元気なうちに墓じまいを行うことは、自身の「終活」の一環としても非常に有効です。将来への不安を解消し、ご自身や家族が安心して暮らせる心のゆとりを得ることができます。
→ 終活としての墓じまいについては、【墓じまいと終活】後悔しない進め方 をご覧ください。
(4)新しい供養の形を選択できる自由度
墓じまいを機に、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨など、ご自身の価値観やライフスタイルに合った新しい供養の形を自由に選択できる機会が生まれます。これにより、より現代に即した供養を実現できます。
3. 墓じまいをするデメリット(考慮すべき点と注意)
メリットがある一方で、墓じまいには事前に考慮しておくべきデメリットや注意点も存在します。
(1)予想外の「費用」が発生する可能性
墓じまいには、墓石の撤去費用、新しい供養先にかかる費用、寺院へのお布施(離檀料を含む場合あり)など、様々な費用が発生します。事前に詳細な見積もりを取らずに進めると、予想外に高額な費用がかかり、後悔する可能性があります。
費用を安く抑える方法や、具体的な費用の内訳については、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)寺院や親族との関係性における「トラブル」のリスク
墓じまいは、寺院や親族にとってデリケートな問題であり、伝え方や進め方を誤ると、感情的な対立やトラブルに発展するリスクがあります。特に、寺院からの高額な離檀料請求や、親族間での意見の相違が原因となるケースが少なくありません。
トラブルを避けるための具体的な対策は、以下の記事で詳しく解説しています。
→ ご住職への話し方: 【墓じまい】ご住職への話し方
→ 離檀で揉めないポイント: 【墓じまい・離檀】最初の相談で揉めないポイント
→ 高額離檀料請求への対処法: 【高額離檀料請求】墓じまい対処法
→ トラブル事例集: 【墓じまいトラブル事例集】原因と予防策
(3)手続きの複雑さと時間・労力の問題
墓じまいには、現在の墓地管理者との手続き、自治体への改葬許可申請、新しい供養先との契約、石材店の手配など、複数の関係者との調整と行政手続きが伴います。これらの手続きには時間と労力がかかり、慣れない作業にストレスを感じる方も少なくありません。
→ 墓じまいの手続きの流れについては、 お墓じまいマニュアル をご参照ください。
4. 今後の墓じまいの動向と供養先の選び方
墓じまいの増加傾向は今後も続くと予想され、供養のあり方も多様化していくでしょう。
(1)増加傾向は今後も継続か?(寺院の状況と承継者不足)
寺院の檀家離れは今後も進むと考えられ、ご住職の高齢化や承継者不足といった寺院側の問題も顕在化しています。これにより、墓じまいのニーズはさらに高まる可能性があります。
(2)納骨堂・霊園の経営破綻リスクと選び方
多様な供養先が増える一方で、一部の納骨堂や霊園では経営破綻の事例も報告されています。長きにわたり安心して供養を続けるためには、運営母体の安定性や実績をしっかりと確認し、慎重に供養先を選ぶことが重要です。
(3)安心できる公営墓地の選択肢
費用を抑えつつ、長期的な安心を得たい場合、自治体が運営する公営墓地(永代供養墓や合葬埋蔵施設を含む)は魅力的な選択肢です。居住要件などがありますが、民間と比べて費用が安く、経営の安定性も高いため、人気を集めています。
5. まとめ:墓じまいを後悔しないために

墓じまいの増加は、現代社会の多様なニーズを反映した自然な流れと言えます。しかし、安易な決断は後悔につながる可能性もあります。
このページで解説した、墓じまいの増加背景、メリット・デメリット、そして将来的な動向を理解し、事前に十分な情報収集と計画を立てることが何よりも重要です。
特に、費用、寺院や親族との関係性、行政手続きといった各側面における注意点を把握し、対策を講じることで、円満で後悔のない墓じまいを実現することができます。
もし、墓じまいに関する不安や疑問、手続きの複雑さでお困りの場合は、お一人で抱え込まず、お気軽にお墓専門の当事務所までご相談ください。豊富な経験と専門知識を持つ行政書士が、あなたの状況に合わせた最適なアドバイスとサポートを提供し、安心して墓じまいを完了できるようお手伝いいたします。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)