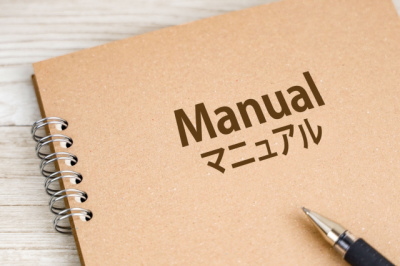近年ではお墓に埋葬する方よりも散骨を行う方が多くなっています。
海洋散骨が主に行われていますが、散骨について具体的に定められた法律は無い為、散骨を行う手続き等も特に定められていません。又、散骨を行う場合、散骨業者に必ず依頼する必要があるものでもありません。
ここでは、散骨についての基礎知識を解説させて頂きます。散骨を考えられている方は、参考にご覧ください。
1. 散骨は、違法ですか?
散骨は、法律的にはどの様に考えられているのでしょうか?
墓地、埋葬に関する法律では「埋葬又は、焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない。」と明記されておりますが、散骨と埋葬は異なりますので、上記法律には当てはまらないことになります。
散骨に対する法務省の見解として「葬送の為、節度持って行われる限り違法ではない。」との話がありますが、実際に法務省の公式な見解として、その様な言葉は見つかりません。又、具体的に示された通達等の文書も存在しておりません。一方、厚生労働省から、散骨事業者に向けた「散骨に関するガイドライン」が提示されています。
散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)抜粋
1 目的
本ガイドラインは、散骨が関係者の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生等の見地から適切に行われることを目的とする。
2 定義
本ガイドラインにおける用語の定義は次のとおりとする。
(1) 散骨 墓埋法に基づき適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、墓埋法が想定する埋蔵又は収蔵以外の方法で、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為
3 散骨事業者に関する事項
(1) 法令等の遵守
散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)、刑法(明治40年法律第45号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、海上運送法(昭和24年法律第187号)、民法(明治29年法律第89号)等の関係法令、地方公共団体の条例、ガイドライン等を遵守すること。
(2) 散骨を行う場所
散骨は、次のような場所で行うこと。
① 陸上の場合 あらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く。)
② 海洋の場合 海岸から一定の距離以上離れた海域(地理条件、利用状況等の実情を踏まえ適切な距離を設定する。)
(3) 焼骨の形状 焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと。
(4) 関係者への配慮 散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、地域住民、周辺の土地所有者、漁業者等の関係者の利益、宗教感情等を害することのないよう、十分に配慮すること。
上記、ガイドラインについて散骨の適法性等を述べる言葉はありませんが、①実際に多くの散骨が行われている事、②ガイドラインにより遵守法令も述べられている事、などから法令、ガイドライン等に従って行う限り、散骨は違法にはならないと考えられます。
2. 節度をもって行う散骨とは?
上記で述べられている節度を持って行う散骨とは、どの様なことか要約して解説させて頂きます。
- 遺骨は粉末化する。 感情面、宗教面を考慮し遺骨をそのまま撒くことはしません。
- 地域の状況を配慮し理解を得る。 海洋散骨の場合は、釣場、交通の要所など地域の状況を配慮します。
- 自然環境を配慮して行う。 自己所有地以外に撒く場合、所有者等の了承を得る必要があります。
- 家族、親戚などの了承を得ておく。 後々、親族間等の問題にならない様に、理解を得ておくことが大切です。
法令等を除き周辺環境等に配慮して散骨を行う事が、節度を持って行うことになります。
3. 散骨する場所は?
散骨する場所としては、海への散骨が一番多くなっております。散骨と言えば海洋散骨をイメージされる方が多いかと思います。その他、山での散骨を行う方もおります。海外の場合は、ヘリコプター等で山頂に行き空中から遺骨を撒く散骨などもあります。
尚、珍しい散骨方法として宇宙葬というものがあり、遺骨の一部を衛星ロケットで打ち上げ、地球の周回軌道まで飛ばす方法が取られます。アメリカの企業が行っている葬送ですが、日本にも代理店が有り、費用は百万円程度になるそうです。
→ 散骨のより詳細な種類や方法については【散骨マニュアル】手続き・費用・注意点 をご覧ください。
4. 散骨のメリット・デメリット
散骨は、その自由さから選ばれることが多い一方で、考慮すべき点もあります。
- 従来の墓石建立や維持管理にかかる費用を抑えられる。
- お墓の継承者が不要となり、将来の負担を軽減できる。
- 故人や遺族の「自然に還りたい」という願いを叶えられる。
- 特定の宗教・宗派にとらわれず、自由に供養の形を選べる。
- 故人の遺骨が手元に残らず、お墓のような「特定の心の拠り所」がなくなる場合がある。
- 親族間の理解や同意が非常に重要となり、トラブルの原因となることもある。
- 散骨できる場所や行為には法律やガイドラインによる制限がある。
5. 散骨にかかる主な費用
散骨にかかる主な費用は、以下の3つに大別されます。
(1)遺骨の粉骨費用
遺骨を粉末状にするための費用です。専門業者に依頼する場合に発生し、一般的に遺骨一体につき1万円〜3万円程度が相場です。
(2)散骨実施費用
散骨を専門業者に依頼する際に発生する費用です。委託散骨、合同散骨、チャーター散骨といった方法によって費用は大きく変動します。
- 委託散骨: 遺骨を業者に預けて代行してもらう形式で、3万円〜5万円程度が相場です。
- 合同散骨: 複数のご家族が同じ船に乗って散骨を行う形式で、5万円〜10万円程度が相場です。
- チャーター散骨: 船を貸し切り、ご家族だけで散骨を行う形式で、15万円〜30万円以上が相場です。
(3)墓じまいからの散骨で発生する費用
現在お墓に遺骨が埋葬されている場合は、散骨を行う前に墓じまいが必要です。この際、墓石の撤去費用や閉眼供養のお布施などが別途発生します。墓石撤去費用は20万円〜100万円程度、閉眼供養のお布施は3万円〜10万円程度が目安です。
→ 墓じまいから散骨への手続きや費用詳細は【墓じまいから散骨へ】手続きの流れと注意点 をご覧ください。
→ 詳細な散骨費用については【散骨マニュアル】手続き・費用・注意点 をご覧ください。
6. 散骨を行う上での基本的な注意点
散骨をスムーズに行い、後々のトラブルを防ぐために、特に以下の基本的な点に注意が必要です。
(1)関係者との十分な話し合いの重要性
散骨は一度行うと元に戻すことは出来ません。そのため、散骨を行う前に家族、親族と良く話し合い、全員の同意を得てから行いましょう。後々、親族間でのトラブルにならないよう、事前の合意形成が最も重要です。
(2)遺骨の粉骨の必須性
遺骨をそのままの形で散骨することは法律上認められていません。必ず2mm以下のパウダー状に粉骨する必要があります。
(3)散骨場所と環境への配慮の重要性
個人の私有地や公共の場所での無許可散骨はトラブルや法的問題につながる可能性があります。自然環境保護の観点から、遺骨以外のもの(副葬品など)を一緒に散骨しないといった配慮も重要です。
(4)信頼できる業者選びの重要性
散骨業者を選ぶ際は、厚生労働省のガイドラインに沿った運営をしているか、実績や料金の明確さなどを確認し、信頼できる業者を見極めることが大切です。
(5)将来的な心の拠り所の検討
散骨後は、遺骨を再度供養する場所がなくなります。遺族の心の拠り所として、手元供養や永代供養墓への一部納骨なども選択肢となります。
→ 散骨に関するより詳細な注意点や業者選びの具体的なチェックリストは【散骨マニュアル】手続き・費用・注意点 をご覧ください。
7. まとめ:安心して散骨を行うために

散骨は、故人の尊厳と遺族の想いを大切にする新しい供養の形として注目されています。しかし、その自由さゆえに、正しい知識と準備が不可欠です。特に、法律上の解釈、適切な場所の選定、遺骨の粉骨、そして何よりもご家族・ご親族との十分な話し合いが、後悔のない散骨を実現するための鍵となります。
ご自身での手続きや、業者選びに不安がある場合は、お墓の手続き専門家(行政書士など)に相談することも有効な手段です。専門家のサポートを得ることで、手続きの負担を軽減し、安心して散骨を進めることができます。
散骨において不明点がありましたら、お墓の専門行政書士までお気軽にお問合せ下さい。ご相談だけでも大丈夫です。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)