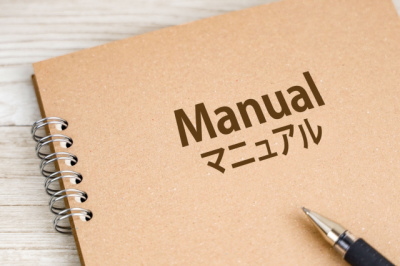お墓じまいを、ご自身の「終活」の一つとして考えられる方が近年、非常に多くなっています。
お墓じまいを、ご自身の「終活」の一つとして考えられる方が近年、非常に多くなっています。
「お墓の承継者がいないので無縁墓になってしまう」「子供にお墓を継がせると負担をかけてしまう」といった理由から、元気なうちに、ご自身でご先祖様のお墓をきちんと整理しておきたいと考える方が増えているのです。
この記事では、この「墓じまい」と「終活」がなぜ深く関連するのか、終活の視点から墓じまいを考える意義と具体的な準備のポイントについて、お墓専門の行政書士が分かりやすく解説いたします。
1. 終活とは?なぜ「墓じまい」とセットで考えるべきか
終活とは、ご自身が亡くなった場合に、残された家族が困らないように財産や身の回りのことを整理したり、万が一の際の葬儀や供養、お墓など、希望をエンディングノートなどで伝えたりする、一種の「人生の身支度」と言えるでしょう。
(1)終活の基本的な要素と「お墓」への影響
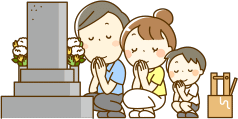
終活の内容は人によって様々ですが、主に以下の要素が含まれます。
相続財産の分配など、法的な効力を持つ意思を残すものです。お墓や仏壇などの祭祀財産は相続財産とは異なりますが、誰が承継するかを遺言書で指定することで、残された家族間のトラブルを避けることが可能です。遺言書は、ご自身の希望を明確に残す有効な手段です。
法的効力はありませんが、葬儀や墓じまい後のご遺骨の最終的な供養方法の希望、連絡先、延命治療に関する意思など、家族に伝えたいことを自由に書き残すものです。これは、お客様ご自身の意思を明確にし、残された家族が迷うことのないようにするための大切なツールです。
家族が相続手続きを行う際に一番困ることは、財産関係がどこに、どれくらいあるのか分からない場合です。預金通帳、貸金庫の情報、不動産の権利書、株の通知書など、遺族が把握できるようファイルにまとめておけば、相続手続きがスムーズに行えます。お墓(祭祀財産)は相続財産とは異なりますが、終活として両方を整理することが、残された家族の負担軽減につながります。
(2)なぜ「お墓」は終活の重要な一部なのか

終活を行う大きな理由の一つは、「子供や兄弟に迷惑を掛けたくない」という思いです。お墓の問題は、まさにその「迷惑をかけたくない」という思いと直結します。
もし、お墓をそのままにしておくと、将来的には「子供」や「兄弟」が承継することになります。維持管理費も承継された方が、その支出をする事になります。例えば、子供が一人(女子)の場合には「嫁ぎ先の墓」と「ご両親の墓」を管理する事になります。先祖代々の墓が別に有る場合は、管理する墓が更に増え3箇所になります。
3箇所になりますと、寺院などに支払う維持管理も、年間4万円~6万円程度になります。又、お子様が承継した後に、お墓を整理しようとすると撤去費等の費用が発生します。結局、お子様に迷惑を掛けない様に、エンディングノート等を残していても、お墓の整理が出来ていないと様々な問題が発生する場合があります。
※寺院や霊園によっては、承継者変更届なども必要な場合があります。その際には、印鑑証明書や戸籍の提出なども求められる場合があり、手続なども、複雑になる場合があります。
2. 終活としての「墓じまい」具体的な検討ポイント
終活の一部として墓じまいを考える場合、どのような点に注目し、何を検討しておくべきでしょうか。
(1)お墓を継ぐ人がいない場合の選択肢
お墓を継ぐ人がいない場合、現在の墓地をそのままにしておくと将来的に無縁墓になってしまう可能性があります。このような事態を避けるために、終活として墓じまいを検討する方が非常に多くなっています。
・新しい供養の選択肢としては、承継者が不要な永代供養墓 (【永代供養墓】基礎知識・選び方)、納骨堂(【納骨堂とは】選び方・費用・注意点を解説)、樹木葬 (【樹木葬】基礎知識・選び方)、散骨 (【散骨の基礎知識】費用・注意点を解説)などが考えられます。それぞれの特徴や費用、メリット・デメリットを理解し、ご自身の希望に合った供養方法を選ぶことが大切です。
(2)お墓を継ぐ人がいる場合の考え方
お子さんなどお墓を継ぐ人がいる場合でも、承継してもらうかどうかを家族間で話し合っておくことが大切です。「子供に金銭的・精神的負担をかけたくない」という思いから、承継者がいる場合でも墓じまいを選択し、永代供養墓などに改葬するケースも増えています。特に、一人娘が嫁いだなどの理由で承継が難しい場合は、早めにお墓じまいを検討することも一つの選択肢となります。
・【お墓の承継】基本と法律 も参考にしてください。
(3)生前に行っておくべき準備と手続きの概要
終活として墓じまいをスムーズに進めるためには、事前の準備が非常に重要です。
ご自身の希望する供養方法(永代供養、散骨など)を、家族に明確に伝えておきましょう。エンディングノートに記載するだけでなく、口頭でも話し合い、理解を得ておくことが大切です。
ご自身に家族がいない場合や、より確実に希望を実行してほしい場合は、死後事務委任契約を信頼できる専門家と結んでおくことが有効です。
墓じまいには費用がかかりますので、そのための準備も行っておきましょう。
・費用の詳細や相場については、【墓じまい費用】誰が負担?相場・内訳と話し合い 、費用を安く抑える方法は、【墓じまい費用】安く抑える方法と相場 の記事も参考にしてください。
お墓じまいの手続きは下記を参考にご覧下さい。
・お墓じまいマニュアル で全体の流れをご確認いただけます。また、【遠方のお墓】墓じまい手続きの流れと注意点 も、ご参照ください。
3. 墓じまいを取り巻く近年の状況と当事務所の経験
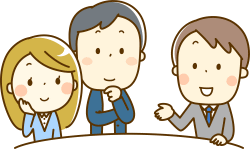
近年、お墓じまいのご相談は増加の一途を辿っています。当事務所では、50歳代~70歳代のお客様から多くご依頼を頂いており、「お墓を継ぐ人がいない」「子供に迷惑を掛けたくない」といった理由が上位を占めています。
特に、寺院墓地を墓じまいし、永代供養墓や納骨堂へ改葬される方が多く見られます。これは、寺院墓地特有の檀家としての義務や金銭的負担を理由とする場合が多いと考えられます。一方、お墓の承継者がいない方向けに、生前に契約期間を定めてお墓を維持し、その後に墓じまいを行うといった新しいサービスも霊園等で提供されています。
4. まとめ:「終活としての墓じまい」は専門家へ

「お墓じまい」は、残された家族の負担を軽減し、ご自身の終の住処について意思表示をする上で、終活の重要な要素となりつつあります。
手続きや選択肢の多様さに戸惑うのは当然のことですが、事前の準備と正確な情報収集、そして専門家のサポートを得ることで、安心して円満な墓じまいを実現できます。
もし、墓じまいや終活に関するご不安、手続きでお困りの場合は、どうぞお気軽にお墓専門の当事務所までご相談ください。お墓の専門行政書士として培った豊富な経験と知識を活かし、お客様に寄り添い、納得のいく「終活としての墓じまい」をサポートいたします。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)