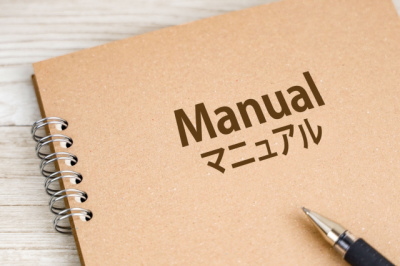・お墓じまいに際して、「費用はいくらかかるのか?」「その内訳や相場は?」「誰が費用を負担すべきなのか?」といった疑問や不安を抱える方は少なくありません。
この記事では、墓じまいの費用に関する全体像、具体的な内訳と相場、そして特に重要な「費用負担者」に関する問題を、お墓専門の行政書士が徹底的に解説し、お客様が安心して手続きを進められるようサポートいたします。
1.墓じまいの費用は誰が負担するのか?
墓じまいにかかる費用は、誰が負担すべきかというご質問をよくいただきます。お墓は相続財産とは異なり「祭祀財産」として扱われるため、その費用負担には特有の考え方があります。
(1)祭祀承継者が費用を負担する原則
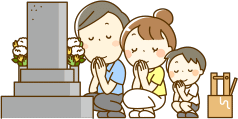
民法第897条には、系譜、祭具、墳墓(お墓)の所有権は、被相続人の指定または慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定められています。具体的には、故人の指定、慣習、または家庭裁判所の決定によって祭祀承継者が決まります。
一般的に、遺言書による指定がない場合、葬儀の喪主を務めた方や長男が祭祀承継者となるケースが多いですが、家族間で意見が対立する場合は家庭裁判所に判断が委ねられます。
墓じまいの費用は、基本的にこの祭祀承継者が負担するものと考えられています。
(2)費用分担に関する家族間の話し合いの重要性
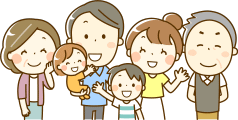
しかし、実際には墓地の維持管理費を支払っていた方(実質的な祭祀承継者であることが多い)が費用を支払うケースや、兄弟姉妹間で費用を分担するケースも当然あります。
話し合いで費用を分担する合意ができれば問題ありませんが、強制的に分担を求めることは、法律的な紛争ではないものの、人間関係の軋轢や家族間の不和につながる可能性があります。祭祀承継者が一人で費用を負担することに抵抗を感じ、墓じまいが進まないケースも考えられます。
そのため、墓じまいを検討する際は、まず「費用がいくらかかるのか」という全体像を把握し、次に「誰がどのように負担するのか」を家族や兄弟姉妹間で十分に話し合い、合意形成を行うことが非常に重要です。
改めて整理すると、争いの可能性がある場合は、被相続人が遺言書で祭祀承継者を指定しておくのが最善です。遺言書による指定がない場合は、相続人全員での話し合いで祭祀承継者を決め、話し合いがつかない場合は家庭裁判所に判断を委ねることになります。
祭祀承継者は、お墓などの祭祀に関する費用を負担するものと考えるのが第一前提ですが、相続人全員の合意があれば、費用を分担することも問題ありません。このような前提のもとで、お墓の費用負担問題について話し合いを進めることをお勧めします。
2.墓じまいに伴う費用全体の相場と内訳
墓じまいの費用は、大きく分けて「現在のお墓の撤去にかかる費用」と「新しい供養先にかかる費用」、そして「その他、行政手続きや供養にかかる費用」の3つに分類できます。ここでは、それぞれの費用について、一般的な相場と内訳を解説します。
※具体的な費用を安く抑える方法については、【墓じまい費用】安く抑える方法と相場 の記事で詳しく解説しています。
(1)お墓の撤去費用
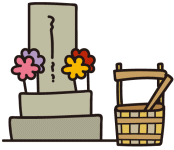
お墓の撤去費用は、墓じまい費用の大部分を占めます。墓地の広さ、墓石の大きさや種類、墓地の立地(重機が入りやすいか、手作業が必要かなど)によって大きく変動します。
一般的な和型のお墓で20万円~50万円程度、洋型で10万円~30万円程度が相場ですが、広大な敷地や特殊な状況では100万円近くになることもあります。この費用は、主に石材店に支払われます。
(2)新しい供養先にかかる費用
墓じまい後の遺骨をどこに改葬するかによって、費用は大きく異なります。現代では、少子高齢化や多様な価値観から、以下のような承継者を必要としない供養方法が主流となっています。
墓じまい後に新たに一般墓を建てる場合、墓地使用料とは別に、墓石建立費として100万円から300万円以上かかることが一般的です。これは墓石の材質やデザイン、施工内容によって大きく変動します。
都立霊園の施設変更制度を利用する場合、永代使用料や年間管理料はかからず、事務手数料のみで済むことがほとんどです。通常、数百円程度の実費で済み、費用を抑えたい場合に有効な選択肢です。
- 合祀(他の遺骨と一緒になる形式): 5万円~20万円程度。最も費用を抑えられます。
- 合葬(骨壺のまま共同で埋葬される形式): 10万円~50万円程度。
- 個別区画型(一定期間個別に安置後、合祀)や樹木葬: 20万円~100万円程度。
業者に委託する場合、5万円~。チャーター船で立ち会う場合は15万円~30万円以上かかることもあります。散骨は埋葬ではないため、改葬許可証は不要です。
(3)その他の費用
- 行政手続き費用:改葬許可証の取得など、通常無料ですが、自治体により数百円程度の実費がかかる場合があります。
- 遺骨の取り出し・運搬費用: 墓石の開閉・遺骨の取り出し作業費(石材店へ)、新しい供養先への運搬費。石材店のサービスに含まれる場合もありますが、別途2万円~10万円程度かかることがあります。
- 供養に関する費用(お布施など): 閉眼供養(お墓の魂抜き)、開眼供養(新しい墓の魂入れ)、納骨供養など、寺院へのお布施(3万円~5万円程度が目安ですが、寺院によって異なります)。
3.費用負担に関するトラブルを避けるために

祭祀承継者に関する問題や、それに伴う費用負担で家族間が揉めることを避けるためには、故人(被相続人)が遺言書を作成し、相続財産の分配と併せて祭祀承継者を指定しておくことが非常に有効です。遺言書で明確に指定されていれば、相続発生後に承継者問題で争う理由がなくなり、手続きがスムーズに進みます。
もし遺言書による指定がない場合、お墓に関する費用負担の話し合いは、相続財産の分割と併せて行うことをお勧めします。例えば、相続人の一人が多額の財産を相続し、他の相続人がわずかな財産しか相続しない状況で、後からお墓に関する費用の均等な負担を求められた場合、不公平感から新たな争いが生じる可能性があります。
したがって、最初の段階で「お墓は誰が継ぐのか」「費用は祭祀承継者が負担するのか、それとも取得財産額に応じて分担するのか、あるいは均等に負担するのか」など、具体的な取り決めを話し合っておくことが重要です。
改めて整理すると、争いの可能性がある場合は、被相続人が遺言書で祭祀承継者を指定しておくのが最善です。遺言書による指定がない場合は、相続人全員での話し合いで祭祀承継者を決め、話し合いがつかない場合は家庭裁判所に判断を委ねることになります。
祭祀承継者は、お墓などの祭祀に関する費用を負担するものと考えるのが第一前提ですが、相続人全員の合意があれば、費用を分担することも問題ありません。このような前提のもとで、お墓の費用負担問題について話し合いを進めることをお勧めします。
4.墓じまいの費用負担 まとめ

墓じまいの費用は、墓地使用者(契約者)が負担するケースが多いですが、兄弟姉妹間で分担されることもあります。
先祖代々の墓やご両親の墓など、埋葬されている方によって関係する親族も異なるため、墓じまいを検討する際は、まず費用全体を確認し、その上でご自身で全額を負担するのか、それとも分担を求めるのかを家族や兄弟姉妹間で十分に話し合ってから進めることが重要です。
一方的に費用分担を期待して墓じまいを進めてしまうと、後々家族間で「トラブル」(法律的な紛争ではないものの、感情的な対立や不和)になる可能性がありますので、十分にご注意ください。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)