

 近年、ご自身の「終活」の一つとしてお墓じまいを検討される方が非常に多くなっています。
近年、ご自身の「終活」の一つとしてお墓じまいを検討される方が非常に多くなっています。
「お墓の承継者がいないため無縁墓になってしまうのではないか」「子供にお墓を継がせることで負担をかけてしまうのではないか」といった理由から、元気なうちに、ご自身でご先祖様のお墓をきちんと整理しておきたいと考える方が増えています。
この記事では、お墓の承継に関する具体的なトラブル事例やよくある疑問について、Q&A形式で分かりやすく解説します。お墓専門の行政書士が、皆様の疑問を解消し、円満な解決へ導くための実践的なアドバイスを提供いたします。
1. 【Q&A】お墓の承継者問題:具体的な事例と解決策
Q1: お墓を承継する人(祭祀承継者)は誰がなれるの?

A1: お墓の承継者(祭祀承継者)は、主に以下の3つのパターンで決定されます。
お墓を所有していた故人が生前に特定の人物を承継者として指定していた場合、その方が承継者となります。この指定は口頭でも遺言書でも可能ですが、後々のトラブルを避けるためには遺言書による書面での指定が推奨されます。
承継者は必ずしも配偶者や親族である必要はありませんが、寺院や霊園によっては親族以外の承継を認めていない場合もありますので、事前確認が重要です。
上記の指定がない場合、「慣習」によって承継されることになります。「慣習」とは一般的に通用している「しきたり」などを指し、多くの場合、長男が承継するという慣習が主流です。しかし、地域や家庭によっては異なる慣習がある場合もあります。
上記いずれにも該当せず、話し合いでも承継者が決まらない場合は、最終的に相続人などが家庭裁判所に「調停や審判の申立て」を行い、裁判所が適切と判断する人物が承継者となります。
→ 詳しくはこちら:「【お墓の承継】基本と法律」をご参照ください。
Q2: お墓を承継するための手続きはどうすればいい?
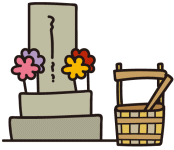
A2: お墓の承継自体に行政上の特別な手続きはありませんが、所有する墓地の管理者に「墓地使用者の変更届」などの手続きを行う必要があります。
知事などへの「承継者の変更による承認申請」を行い、使用許可証の書き換えが必要になる場合があります。(詳細は霊園を管理する自治体に確認が必要です。)
→ 都立霊園の手続き等については、【都立霊園】墓じまい・改葬手続き代行 をご覧ください。
各霊園の管理事務所に連絡し、所定の承継手続きを行う必要があります。必要な書類や手続きは霊園によって異なりますが、一般的には使用許可証や承継者の印鑑証明書などが求められます。
一般的には、承継者が檀家としての地位を承継するものとみなされ、檀家としての義務(維持管理費用など)も負担することになります。ただし、法的には祭祀承継者が必ずしも檀家の地位を引き継ぐ義務はないとされています。
しかし、寺院墓地では檀家となることを前提に墓地の使用を認めていることが多いため、檀家となることを拒否した場合、墓地の使用を拒否される可能性もあるので注意が必要です。
※墓地の承継手続きには、故人の墓地使用許可証の提出を求められる場合があり、承継手続き完了後、使用許可証が再発行された場合は紛失しないように保管しておくことが重要ですです。将来、納骨や墓地返還などを行う際に必要になります。
Q3: 姉弟で承継を希望。長男以外でも承継は可能ですか?

A3: 法律的には、長男以外の方でもお墓を承継することは可能です。
故人が遺言書などで承継者を指定していた場合はその指定に従い、指定がない場合は家族や地域の慣習によって決まりますが、多くの場合、ご家族や親族間で話し合いで決められることが多いかと思います。
最も大切なことは、ご家族でよく話し合うことです。この世で生きている子孫たちが笑顔で仲良く暮らしていることを、何よりも故人やご先祖様が望んでいるはずです。十分な話し合いを行い、円満に解決することを目指しましょう。
Q4: 嫁いだ娘でもお墓を承継できますか?

A4: はい、嫁いだ娘さんでもお墓を承継することはできます。墓地の管理者(寺院や霊園)に相談すると良いでしょう。
近年では、お墓の承継に対する考え方も多様化しており、嫁いだ娘さんが実家のお墓を承継するケースも増えています。承継後、娘さんの実家のお墓を改葬して同じ敷地内に2基の墓石を建てたり、「両家墓」を作ったりするなどの工夫が必要になるかもしれません。
Q5: 兄弟間で意見が合わない場合、どうしたらよいですか?

A5: 兄弟間でお墓の承継者が決まらない、または管理方法などで意見が合わない場合は、以下の点を検討してください。
家族全員で集まり、それぞれの意見や希望を共有することが第一歩です。感情的にならず、冷静に話し合うために、中立的な第三者(親戚等)を交えることも有効です。
承継後の維持費や管理の負担について現実的に検討し、納得のいく分担案を提示することも解決の糸口になります。
話し合いで解決が難しい場合や、法的な手続きが必要になる段階では、適切な専門家にご相談いただくことで、必要な情報やサポートを得られる場合があります。家族・兄弟等で揉めてしまい仲が悪くなるのは悲しいことです。お互いに傷つけあうよりも第三者(弁護士、あるいは家庭裁判所の調停)に任せた方が良い結果になることもあります。
Q6: 承継者がいない場合、お墓はどうなるのでしょうか?
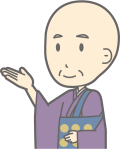
A6: 承継者がいない場合、お墓は将来的には「無縁仏」として扱われる可能性があります。
このような事態を避けるために、生前に以下のような選択肢を検討する方が非常に多くなっています。
現在のお墓を撤去し、寺院や霊園が永続的に供養・管理してくれる永代供養墓に移す方法です。承継者が不要なため、後世に負担をかけません。
これらも承継を前提としない新しい供養の選択肢です。それぞれの特徴や費用、メリット・デメリットを理解し、ご自身の希望に合った供養方法を選ぶことが大切です。
Q7: 遠方に住んでいるため、定期的にお墓参りに行けないのですが、承継する意味はありますか?
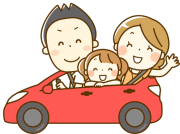
A7: 遠方に住んでいてもお墓を守っていくことは、ご先祖様の供養になります。
管理がきちんとされている寺院・霊園であれば、お墓も清潔に保たれていますので、たまにしかお参りに行けなくても安心です。もし、距離が大きな負担になるようでしたら、墓じまいをしてご自宅の近くに改葬することも一つの方法です。
永代供養墓などの合葬墓であれば、多くの方がお参りに来ますので、故人も寂しくないのではないでしょうか。
→ 関連記事:【遠方のお墓】墓じまい手続きの流れと注意点 や 【遠方のお墓】改葬手続きの流れと手順 もご参照下さい。
Q8: 生前にお墓の承継について決めておくことは可能ですか?

A8: はい、生前にお墓の承継について決めておくことは可能ですし、強く推奨されます。
民法897条で定められているように、祭祀承継者は、故人の意思によるものが最優先にされています。
その意思を明確にするには、遺言書を作成して祭祀承継者を指定しておくことが最も確実な方法です。また、後で揉めないように、生前に家族で十分に話し合い、合意形成をしておくことが非常に重要です。
終活の一環として、墓じまいの具体的な希望や、墓じまい後のご遺骨の最終的な供養方法などもエンディングノートに整理して記載しておくことで、残された家族が迷うことなく、ご自身の意思を尊重した対応が可能になります。
→ 関連:【墓じまいと終活】後悔しない進め方
Q9: お墓を承継したくない場合、どのようにすれば良いですか?
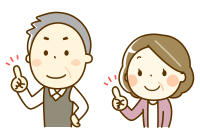
A9: お墓の承継を望まない場合も、放置せずに早めに検討・行動することが重要です。
承継者がいない、または承継したくないという状況であれば、元気なうちに墓じまいを検討し、永代供養や散骨など、ご自身や家族が納得できる新たな供養方法を選ぶのが良いでしょう。
承継者がいるにもかかわらず、個人的な事情で承継したくない場合は、他の親族に承継を依頼することも考えられます。その際は、管理費などお墓の維持に関する費用を分担する方法も検討できます。
お墓の承継は、維持管理費用などの義務も負担する場合が多く、また、墓地区画を転売し換金することも原則出来ません。 そのため、承継を拒否したい場合は、早期に家族と話し合い、専門家にも相談して解決策を探ることが大切です。
2.まとめ:お墓の承継トラブルを避けるために

お墓の承継に関する問題は、現代社会において避けて通れない課題の一つです。承継者の決定、具体的な手続き、そしてそれに伴う費用や税金など、様々な側面で疑問や不安が生じることは少なくありません。
家族間の感情的な対立や、将来的な負担を避けるためには、早めに家族や親族で話し合い、具体的な承継方法や供養のあり方を検討することが非常に重要です。
祭祀承継者の指定や、承継を前提としない供養方法の選択など、選択肢は多様です。このQ&Aで解説した具体的な事例と解決策が、皆様のお墓の承継に関するお悩みを解消し、円満な解決への一助となれば幸いです。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)













