


「すべてを墓地に納めず自宅で供養したい」「散骨はするが、一部の遺骨は手元に残しておきたい」とお考えの方にとって、手元供養は故人を身近に感じられる選択肢です。しかし、手元供養には、将来的な遺骨の管理や、ご家族の負担といった重要な注意点があります。
このページでは、手元供養を行う際に「知っておくべきこと」と「注意点」について、お墓専門の行政書士が具体的に解説します。後悔のない手元供養を実現するために、ぜひ最後までご覧ください。
1. 手元供養とは?その魅力と増加する背景

手元供養とは、遺骨の全部または一部を自宅や身近な場所に保管し、供養する方法です。核家族化の進行や墓地の承継問題、多様な供養方法へのニーズの高まりを背景に、「故人をいつでも身近に感じたい」「費用を抑えたい」「お墓を持たない選択をしたい」といった理由から、近年選ばれる方が増加しています。
ミニ骨壺やアクセサリー、オブジェなど、様々な手元供養品が普及し、供養の形も多様化しています。
2. 将来のために考えておくべきこと:遺骨の管理と書類
(1)将来、遺骨を埋葬する際に必要になる書類
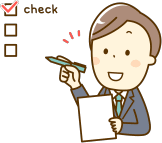
手元供養をしている遺骨を将来的に墓地へ埋葬する場合、埋葬許可証が必要になります。火葬時に発行されるこの書類は、遺骨の身元を証明する重要な公的書類であり、紛失した場合は、火葬を行った自治体または火葬場に相談して再発行手続きを行う必要があります。
ご自身が元気なうちは先のことと考えがちですが、遺骨は将来的に以下のいずれかの方法で適切に供養される必要があります。
- 霊園等と契約し、お墓に埋葬する(改葬手続き)。
- ご家族が引き続き手元供養を継承する。
- 散骨や永代供養墓など、別の方法で供養する。
遺骨を放置することはできませんので、ご家族で将来について話し合っておくことが大切です。
(2)証明書類はきちんと保管しておく

遺骨を将来的に埋葬する際に慌てないよう、関連する証明書類はきちんと保管しておくことが極めて重要です。特に、以下の書類は大切に保管し、ご家族にも保管場所を伝えておきましょう。
- 埋葬許可証(火葬許可証):火葬後に発行される、埋葬に必須の書類です。火葬済みである旨が記載された火葬許可証が、そのまま埋葬許可証となります。
- 埋葬証明書:現在お墓に埋葬されている遺骨を墓じまいして手元供養にする場合、元の墓地管理者から発行してもらう書類です。将来、再度お墓に埋葬する際に必要となることがあります。
- 分骨証明書:遺骨の一部を分骨して手元供養する場合、分骨元(墓地管理者や火葬場)から取得する書類です。この分骨証明書も、将来その遺骨を埋葬する場合に必要となることがあります。
手元供養自体に改葬許可証は不要ですが、将来墓地へ納める可能性を考慮し、上記のような関連書類は必ず保管してください。これらの書類がない場合、将来の埋葬手続きが困難になるだけでなく、再発行に時間や手間がかかることがあります。
→ 改葬許可申請書の取得・記入方法については【改葬許可申請書】取得・記入方法と必要書類 をご覧ください。
→ 分骨に関する基礎知識については【分骨の基礎知識】知っておきたい手続きと費用 をご覧ください。
3. 手元供養を行う際の注意点と家族への配慮
(1)ご遺骨を将来どうするのか?明確に考えておく
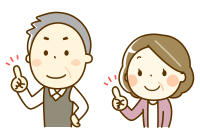
手元供養された遺骨を「誰が」「いつまで」「どのように」管理するのか、具体的な見通しを立てておくことが重要ですし、遺骨の量によっては将来の供養方法に影響することもあります。手元供養は、故人を身近に感じられる反面、将来的な管理の責任が発生します。
ご自身に何かあった際、誰が遺骨の管理を引き継ぐのかを明確にしておく必要があります。お子様がいる場合は、その意思も確認しておきましょう。
いつかは永代供養墓への納骨、散骨、または新たな墓地への埋葬を検討する時期が来るかもしれません。保管期間や最終的な供養方法についても、具体的な計画を立てておくことで、残された家族の負担を軽減できます。
→ 散骨に関する基礎知識については【散骨の基礎知識】費用・注意点 を解説をご覧ください。
(2)保管する人の希望を明確に残しておく
ご自身の死後、手元供養している遺骨をどのようにしてほしいか、その具体的な希望を明確に残しておくことが、残されたご家族への最大の配慮となります。
遺骨の保管場所、将来の希望(例:家族に引き継いでほしい、〇年後に永代供養墓に納めてほしい、特定の方法で散骨してほしいなど)、連絡先などを具体的に記載しましょう。
遺言書を作成し祭祀承継者の指定をしておきます。その承継者の方にご自身の希望を伝えておくことも一つの方法です。(公正証書遺言がお勧めです。)
ご家族がおらず、ご自身で最終的な供養方法(例:永代供養、散骨)を決定したい場合は、生前に霊園や散骨業者と契約を結んでおくことも可能です。せっかく手元で大切に供養された遺骨です。その後の供養もきちんと行われるよう、事前に準備を進めましょう。
(3)ご遺骨を処分することは原則できません

手元供養している遺骨であっても、その扱いには法律上の注意が必要です。遺骨は「もの」とは異なり、原則としてゴミとして処分することはできません。
・不法投棄・不法埋葬の禁止
遺骨を墓地以外の場所に無断で埋葬したり、公園や私有地に捨てたりする行為は、死体遺棄罪や墓地埋葬法違反に問われる可能性があります(死体遺棄罪は3年以下の懲役)。
・自宅保管は問題なし
自宅で遺骨を保管すること自体は、法律上の埋葬には当たらないため、問題ありません。また、いつまでに埋葬しなければならないという法的義務もありませんので、永続的に自宅で手元供養を続けることも可能です。
・散骨の扱い
散骨については、墓地埋葬法で明確に定められていませんが、厚生労働省の見解や社会的な慣習により、節度を持って行う限りは違法ではないとされています。ただし、粉骨(パウダー状にすること)が必須であり、許可された場所で行う必要があります。
手元供養された遺骨の最終的な供養方法は、引き続き自宅保管するか、永代供養墓への埋葬、または散骨のいずれかを選択することになります。
4. 手元供養を行う場合の流れ
一部の遺骨を手元供養するのか、全ての遺骨を手元供養するのかを決定します。
![]()
散骨を伴う分骨の場合、事前に分骨を行うか、散骨業者による粉骨後に分骨するのかを検討します。
![]()
遺骨を納める手元供養用のケースや容器を購入します。多種多様なデザインがあります。
![]()
埋葬許可証、埋葬証明書、分骨証明書などの重要書類を適切に保管します。特に墓じまいからの手元供養では、お墓の管理者から証明書を忘れずに取得しましょう。
5. まとめ:手元供養は「その後」まで見据えて

手元供養は、故人を身近に感じ、心の安らぎを得られる素晴らしい供養方法です。しかし、その選択をする際には、「その後」を見据えた準備と、ご家族との十分な話し合いが不可欠です。
特に、将来的に遺骨をどうするのか、必要な書類は何か、そしてご自身の希望をどのように伝えるのかは、残されたご家族の負担を大きく左右します。
手元供養が一時的なものなのか、永続的なものなのか、最終的な供養の形はどうするのか、ご家族としっかり話し合い、明確な方針を決めておくことで、将来の不安を解消し、故人も安らかに供養されることでしょう。
お墓や供養に関するご不明な点、将来設計に関するご相談がありましたら、お墓専門の行政書士がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
→ お墓に関するよくある質問は【お墓の手続き】よくある質問Q&A をご覧ください。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)













