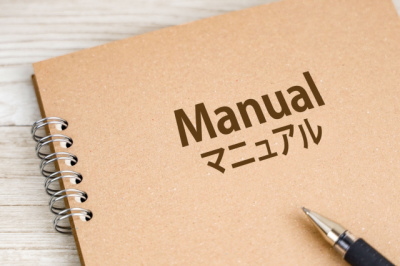・改葬(お墓の引越し)を行う上で、避けて通れないのが行政手続きです。特に「改葬許可証」の取得は、遺骨を移動させるために法律で定められた必須の手続きです。
この改葬許可証を取得するためには、現在お墓がある市区町村役場に申請を行い、様々な書類を提出する必要があります。手続きは複雑に感じられるかもしれませんが、一つずつ進めれば難しいものではありません。
この記事では、改葬許可証の申請手続きに焦点を当て、申請書の取得方法から具体的な記入方法、そして必要となる書類について、分かりやすく詳細に解説します。これからご自身で手続きを進められる方は、ぜひ参考にしてください。
1. 改葬許可申請書の取得方法
改葬許可申請書は、現在お墓がある市区町村役場の窓口で入手する方法と、各自治体のホームページからダウンロードする方法が一般的です。
(1)役場窓口での入手
役場の担当部署(福祉課、戸籍住民課など、自治体により異なります)に改葬許可申請書の用紙があるか確認し、受け取ります。窓口で質問することも可能です。
(2)ホームページからのダウンロード
多くの自治体は、公式ホームページで改葬許可申請書の様式を公開しています。「〇〇市 改葬許可申請書 ダウンロード」といったキーワードで検索すると見つけやすいでしょう。ダウンロードして印刷し使用できます。
(3)郵送での依頼
遠方にお住まいの場合など、郵送で申請書用紙を送ってもらうことも可能です。事前に役場に連絡し、郵送での申請書請求が可能か、必要な手続き(返信用封筒の送付など)を確認してください。
申請書を入手する際に、手続き全体の流れや必要書類についても合わせて確認しておくとスムーズです。
2. 改葬許可申請書への記入方法(項目別の詳細解説)
改葬許可申請書には、主に以下のような項目を記入します。自治体によって様式や項目が若干異なる場合がありますが、基本的な内容は共通しています。
① 死亡者の本籍・住所・氏名・性別
埋葬されている故人(遺骨の主)の情報です。
- 本籍・住所:死亡時の本籍と住所を記入します。
- 氏名・性別: 故人の氏名と性別を記入します。
- 不明な場合:戸籍などが手元になく、本籍や住所が不明な場合は、「不詳」と記入できる場合があります。事前に役場の担当者に確認してください。
② 埋葬又は火葬の場所・年月日
現在、遺骨が埋葬されている(または火葬された)場所とその年月日に関する情報です。
- 場所:現在、遺骨が埋葬されている墓所の正確な住所を記入します。
- 年月日:現在の場所に埋葬された年月日(または火葬年月日)を記入します。正確な年月日が分からない場合は、「不詳」と記入します。
③ 改葬の理由・場所
改葬を行う理由と、新しい改葬先の情報です。
- 改葬の理由:なぜ改葬するのか、その理由を簡潔に記入します。「墓地移転の為」「新規に墓地を購入した為」など具体的な理由を記入します。
- 場所: 新しい改葬先の寺院や霊園の住所、名称を記入します。
④申請者の情報(住所・氏名、死亡者との続き柄、墓地使用者等との関係)
改葬許可申請を行う申請者自身の情報です。
- 住所・氏名: 申請者の現在の住所と氏名を記入します。
- 死亡者との続き柄:故人から見た申請者の続柄(例:「子」「孫」など)と、申請者から見た故人の続柄を記入する場合があります。
- 墓地使用者等との関係:現在のお墓の所有権者(契約者や祭祀承継者など)との関係を記入します。申請者自身がお墓の所有権者であれば「本人」と記入します。所有権者以外の方が申請する場合は、所有権者の承諾書等が必要になります。
⑤埋葬の事実証明
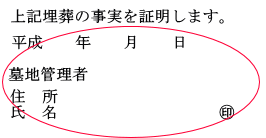
申請書の所定の欄、または自治体指定の別用紙にて、現在遺骨が墓所に埋葬されていることを、墓地管理者(寺院の住職、霊園の管理者など)に証明してもらう必要があります。
申請書のこの項目に、墓地管理者の記名・押印をもらいます。事前に申請書の記入項目のうち、管理者証明欄以外の項目(①~④など)は記入しておいたうえで、管理者に証明をお願いするとスムーズです。
3. 改葬許可申請に必要な添付書類
改葬許可申請には、申請書以外にもいくつかの添付書類が必要です。必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的には以下のような書類が求められます。
・埋葬(納骨)事実証明書(原本):現在のお墓の管理者(住職、霊園等の管理者)が発行する書類です。、墓所に改葬許可申請に記載した遺骨が埋葬されている事実を証明してもらう書類です。改葬許可申請書に証明欄がある場合は不要になります。
・受入れ証明書(原本)または使用許可証(原本提示):新しい改葬先の管理者が発行する書類で、遺骨を受け入れることを証明するものです。既に新しい墓地などの使用契約を結んでいる場合は、通常、使用許可証の原本提示でも申請可能です。
・墓地使用者の同意書(申請者が墓地使用者以外の場合):墓地の所有権者でない方が申請する場合、自治体により所有者の承諾書・同意書の添付を求められる場合があります。
・遺骨者の死亡記載のある戸籍:自治体により、お墓に埋葬されている方の死亡記載のある戸籍を求められる場合があります。
・その他:申請者の住民票、遺骨者と申請者の続柄がわかる戸籍なども求められる場合があります。
・委任状(手続きを他者に委任する場合):行政書士などの専門家に手続きを代行してもらう場合に必要です。
これらの書類は、発行に時間がかかるものもありますので、早めに準備を開始することをお勧めします。必要書類の正確なリストは、必ず申請先の市区町村役場に事前に確認してください。
4. 改葬許可申請書の提出先と注意点
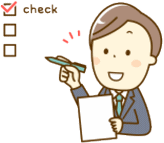
申請書と必要な添付書類が全て揃ったら、現在お墓がある場所の市区町村役場の担当部署に提出します。提出は窓口への持参、または郵送で行うのが一般的です。
- 提出先:現在お墓がある場所の市区町村役場の担当課。
- 提出方法:窓口持参 または 郵送。
- 許可証の発行:申請内容に不備がなければ、改葬許可証が交付されます。自治体によって即日交付される場合と、数日から1~2週間程度かかる場合があります。日程に余裕を持って申請しましょう。
- 不備への注意: 書類に不備があると申請が受理されず、手続きが遅れる原因となります。提出前に各書類と記入内容をしっかりと確認することが重要です。不明な点は事前に役場に問い合わせましょう。
5. まとめ:正確な手続きでスムーズな改葬を

改葬許可証の取得は、改葬手続きの中でも特に重要なステップです。申請書の記入や必要書類の収集には手間がかかりますが、この記事で解説したポイントを押さえ、正確に進めることで、スムーズに手続きを完了させることができます。
もし手続きに不安を感じる場合や、ご自身で行うことが難しい場合は、(例:墓地管理者が不明、お墓が遠方の場合など)場合は、お墓の手続きを専門とする行政書士などの専門家に相談することも有効な手段です。
専門家のサポートを得ることで、手続きの負担を軽減し、安心して改葬を進めることも可能です。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)