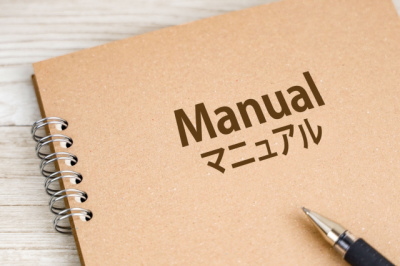「お墓が遠方にあり、お参りに行くのが困難なので、自宅の近くに改葬したい」、「将来、お墓を継ぐ者がいないため、今のうちに遠方のお墓を整理し、新しい供養の形に移したい」など、遠方にあるお墓の改葬(お墓の引越し)を検討される方は少なくありません。
遠方からの改葬では、通常の改葬手続きに加え、現地訪問の制約、遺骨の長距離運搬、関係者との遠隔でのやり取りなど、特有の課題が生じます。
この記事では、遠方のお墓を「改葬」(お墓の引越し)する際の具体的な流れと手順、そして発生しうる費用や注意点について、お墓専門の行政書士が分かりやすく解説いたします。
※遠方の墓じまいを行う場合は、【遠方のお墓】墓じまい手続きの流れと注意点 の記事もご参照ください。
1.遠方から改葬する際の準備と注意点
遠方にあるお墓の改葬をスムーズに進めるためには、事前の準備と関係者への丁寧な配慮が非常に重要です。
(1)新しい供養先(改葬先)の決定と契約

まず、ご遺骨の新しい供養先を決めることから始めます。改葬先は、新しい一般墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨、手元供養など、多岐にわたります。遠方の場合、事前にインターネットや資料請求で情報収集を行い、ある程度の候補を絞り込んでから、現地見学や契約に進むと効率的です。
新しい供養先が決まったら、契約を結び、改葬先の霊園が遺骨を受け入れることを証明する「受入証明書」を取得しておきましょう。これは後の行政手続きで必要になります。(墓地使用許可証の原本提示でも可)
※お墓選びについては、こちらの記事【お墓選び】相談・サポート をご覧ください。
(2)現在の墓地管理者への相談と了承
改葬先が決定したら、現在お墓がある寺院や霊園の管理者に、改葬したい旨を相談し、了承を得る必要があります。特に寺院墓地の場合、離檀に関する手続きや費用(離檀料など)についても話し合うことになります。遠方のため直接訪問が難しい場合は、電話や書面で丁寧にお話しし、理解を得るよう努めましょう。
※ご住職への話し方や離檀に関する注意点は、【改葬手続き】寺院と円滑に進めるポイント の記事もご参照ください。
2.遠方からの改葬手続きの流れと手順
遠方のお墓から改葬を行う場合、郵送でのやり取りや遠隔での調整が多くなるため、通常の改葬以上に正確な手続きと計画が求められます。
(1)改葬許可証の取得

遺骨を別の場所へ移動させる「改葬」を行うには、現在お墓がある自治体(市区町村)から「改葬許可証」を取得することが法律で義務付けられています。申請には、主に以下の書類が必要となります(自治体により異なる場合があります)。
- 改葬許可申請書
- 現在の墓地管理者が発行する「埋葬(納骨)証明書」
- 改葬先の「受入証明書」または「使用許可証」
遠方の場合でも郵送での申請が可能な自治体が多いですが、事前に確認が必要です。
※改葬許可証の取得方法や手続きの詳細は、【改葬許可申請書】取得・記入方法と必要書類 の記事で詳しく解説しています。
(2)石材店の手配と墓石の撤去(お墓じまいを伴う場合)

改葬に伴い、現在のお墓を撤去する場合は、墓石の撤去作業を依頼する石材店を選定します。遠方のため、現地での打ち合わせが難しい場合は、電話やメールでのやり取りに慣れている業者を選ぶと良いでしょう。石材店との契約後、墓石の撤去作業と墓地の整地が行われます。
※墓じまいにおける石材店選びのポイントは、【墓じまい】石材店の選び方と費用 の記事で詳しく解説しています。
(3)遺骨の取り出しと運搬
改葬許可証を取得し、日程を調整したら、現在の墓地で閉眼供養(お墓の魂抜き)を行います。その後、石材店によってお墓が開けられ、ご遺骨を取り出します。取り出したご遺骨は、新しい供養先へ運搬します。遠方への運搬は、ご自身で行う(飛行機、車、電車など)か、専門業者に依頼する方法があります。
ご遺骨が破損しないよう、骨壺の梱包を厳重に行い、水が溜まっている場合は水抜きをしておくことも重要です。
(4)新しい供養先での納骨と手続き

新しい供養先に到着したら、改葬許可証を提出し、ご遺骨を納骨します。納骨式や開眼供養を行う場合は、事前に手配しておきましょう。
※納骨については、【納骨の基礎知識】時期・場所・手順を解説 で詳しく解説しています。
(5)墓地の返還手続き(お墓じまいを伴う場合)
墓石の撤去と墓地の整地が完了したら、墓地の管理者(寺院や霊園)に更地になったことを確認してもらい、墓地使用権の返還手続きを行います。
3.遠方からの改葬で特に注意すべき点と対策
遠方にあるお墓を改葬する際には、一般的な改葬に加えて特有の注意点があります。
(1)情報収集と計画の徹底
現地に何度も足を運べないため、事前にインターネットや電話で徹底的に情報収集を行い、全体の流れ、費用、必要書類を把握しましょう。不明な点は、各関係機関(寺院、霊園、自治体)に問い合わせて確認することが重要です。
※改葬手続きについては、改葬(お墓の引越し)マニュアル も参考にしてください。
(2)コミュニケーションの重要性
遠方からであっても、墓地管理者である寺院のご住職や霊園の担当者、石材店とは、丁寧で密なコミュニケーションを心がけましょう。連絡を怠ったり、一方的に物事を進めようとしたりすると、トラブルの原因となる可能性があります。書面でのやり取りに加え、必要に応じて電話で直接話す時間も確保しましょう。
(3)費用と日程の余裕
遠方の場合、移動費や宿泊費が追加で発生することがあります。また、郵送でのやり取りは時間がかかるため、全体的にスケジュールに余裕を持つことが重要です。想定外の費用や遅延が発生する可能性も考慮し、早めの着手をお勧めします。
※改葬にかかる費用相場や内訳は、【改葬費用】お墓の引越しにかかる費用と相場 も参考にしてください。
(4)専門家への相談とサポートの検討
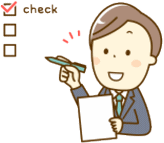
遠方のお墓の改葬に関する手続きは、複雑さに加え、物理的な移動の制約や関係者との調整など、お客様ご自身で全てを行うには大きな負担が伴います。
- 手続きが複雑で何から始めれば良いか分からない。
- 遠方なので、何度も現地に行くのが難しい。
- 寺院や親族にどのように説明すれば良いかわからない。
- 時間的な余裕がない。
このような場合は、お墓の手続きを専門とする行政書士に相談することを検討しましょう。当事務所は、九州、四国、東北地方など、全国各地の遠方のお墓の改葬をサポートした実績があります。お客様のご自宅にいながら、書類作成から関係機関との連絡調整、現地立会いまで一貫して代行し、お客様の負担を最小限に抑え、円滑な改葬をサポートいたします。
4.まとめ:遠方のお墓の改葬も、計画と専門家のサポートで安心

遠方にあるお墓の改葬は、ご遺骨の供養の形を変える大切なプロセスです。距離という課題があるものの、適切な情報収集、計画的な準備、そして何よりも関係者との丁寧なコミュニケーションが成功の鍵となります。
ご自身で全てを行うことが難しいと感じる場合は、専門家である行政書士のサポートを積極的に活用することをお勧めします。お客様の状況に合わせた最適なアドバイスと、手続きの一貫代行を通じて、ご負担なく、安心して遠方のお墓の改葬を完了できるよう、当事務所がお手伝いいたします。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)