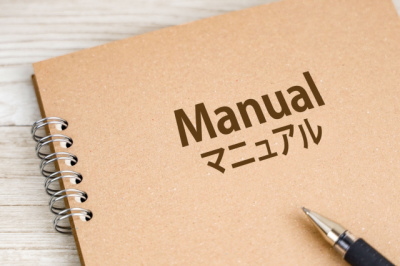故人の遺骨を複数の場所に分けて供養する「分骨」。手元供養、別のお墓への納骨、散骨など、供養の選択肢が多様化する中で、分骨を検討される方も増えています。
分骨は比較的自由に行えるイメージがありますが、遺骨の管理には重要な法的側面や、ご家族間の合意形成といった注意点があります。また、火葬時に分骨する場合と、既にお墓に埋葬されている遺骨を分骨する場合とで手続きが異なります。
このページでは、分骨を検討する上で「知っておきたい基礎知識」として、その意味や理由、費用、そしてスムーズに進めるための具体的な手続きと注意点について、お墓専門の行政書士が分かりやすく解説します。
1. 分骨とは?その意味と増える理由
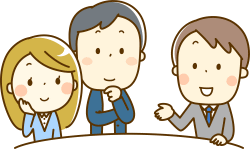
分骨とは、故人の遺骨を二つ以上に分けて、それぞれ別の場所に納めることを言います。全てのお骨を一つの場所に納めるのではなく、複数の供養方法を選択したい場合に分骨が行われます。
近年、分骨を選ぶ方が増えている背景には、以下のような多様な理由があります。
- 遠方にある本家のお墓から分骨し、手元供養や自宅近くの墓地に納めたい
- 親族間で意見が分かれ、それぞれが管理するお墓に分けて納めたい
- 一部の遺骨を本家のお墓に残しつつ、別の骨を永代供養墓や納骨堂に移したい
- 散骨や樹木葬を行うが、故人を身近に感じられるように一部の遺骨を手元に残しておきたい
このように、故人の供養に対する価値観の多様化が、分骨を選択する大きな理由となっています。
→ 分骨のより詳細なマニュアルは【分骨マニュアル】手続き・費用・注意点 をご覧ください。
2. 分骨の法的側面と家族の同意の重要性
(1)分骨に役所の許可は原則不要
分骨を行う際、原則として役所からの「改葬許可証」は不要です。改葬許可証は、墓地から別の墓地へ遺骨を移す際に必要となる書類であり、分骨とは異なります。ただし、墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条により、分骨した遺骨を墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵する際には、その出所を証明する「分骨証明書」を提出することが義務付けられています。
(2)分骨は誰でもできる?遺骨の所有権と家族の同意
分骨は、故人の遺骨を扱う重要な行為であるため、遺骨の所有権者である祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)の同意が必須です。祭祀承継者以外の人が無許可で分骨することはできません。
また、祭祀承継者であっても、ご兄弟など他の親族にも祭祀権があると考えられるため、分骨の意向について事前に十分に話し合い、同意を得ておくことが極めて重要です。後々のトラブルを防ぐためにも、口頭だけでなく、分骨の承諾書や同意書を作成し、関係者全員の署名・捺印を得ておくことを強く推奨します。
→ 祭祀承継者については【お墓の承継】基本と法律をご覧ください。
3. 分骨の手続きと必要書類
(1)火葬時に分骨する場合
故人の火葬を行う際に分骨を希望する場合、手続きは比較的シンプルです。
火葬前に、分骨を希望する旨を火葬場の担当者や葬儀社に伝えておきます。分骨用の骨壺(事前に用意し持参)を持ち込むことも伝えておきましょう。
火葬後、収骨の際に係員に分骨希望であることを改めて伝え、分骨する分の遺骨を骨壺に収めてもらいます。この際、火葬場から「分骨証明書」が発行されます。名称が異なる場合もありますが、必ず取得し大切に保管してください。
(2)お墓に埋葬されている遺骨を分骨する場合
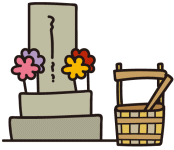
既にお墓に埋葬されている遺骨を分骨する場合は、以下の手順で進めます。
現在遺骨が埋葬されている寺院や霊園の管理者に分骨の意向を伝え、了解を得ます。同時に「分骨証明書」の発行可否や手続きについて確認し、必要な場合は発行を依頼します。
分骨した遺骨をどこに納めるか(新しいお墓、永代供養墓、納骨堂、手元供養、散骨など)を決め、その場所を確保します。分骨先の施設で必要となる書類(受入証明書など)も確認し、準備します。
お墓の管理者と石材店と連携し、墓石を開けて遺骨を取り出し、分骨用の骨壺に遺骨を移し替える作業を行います。残りの遺骨は元の骨壺に戻し、お墓を元に戻します。
分骨証明書を持参し、新しい分骨先で遺骨を納めます。この分骨証明書は、墓地埋葬法によって提出が義務付けられている書類です。 必要に応じて納骨式や供養を行います。
→ 分骨のより詳細な流れや各ステップの注意点については【分骨マニュアル】手続き・費用・注意点 をご覧ください。
(3)分骨証明書とは?法的根拠と取得方法(サンプル含む)
分骨証明書は、分骨した遺骨が故人のものであることを公的に証明する重要な書類です。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条において、墓地や火葬場の管理者は分骨を希望する者に対し、埋葬または火葬の事実を証明する書類を発行すること、また、分骨を埋蔵または収蔵しようとする者は、墓地等の管理者にその書類を提出しなければならないと明確に定められています。このため、分骨証明書は法的に必要となる重要な書類です。
・発行元:火葬場で分骨した場合は火葬場、お墓に埋葬されている遺骨を分骨する場合は元の墓地管理者(寺院、霊園管理事務所など)が発行します。
・用途:分骨先の墓地や納骨堂、永代供養施設などに遺骨を納める際に提出が義務付けられている書類です。手元供養や散骨の場合は不要ですが、手元供養は将来、別の場所で供養する際に必要となるため、大切に保管しておく必要があります。
・様式: 特定の様式は定められていませんが、死亡者氏名、生年月日、死亡年月日、火葬・埋葬場所、分骨の事実、分骨元の墓地管理者名と証明印などが記載されます。もし管理者が指定の様式を持っていない場合は、ご自身で作成した分骨証明書に署名・捺印を依頼することになります。
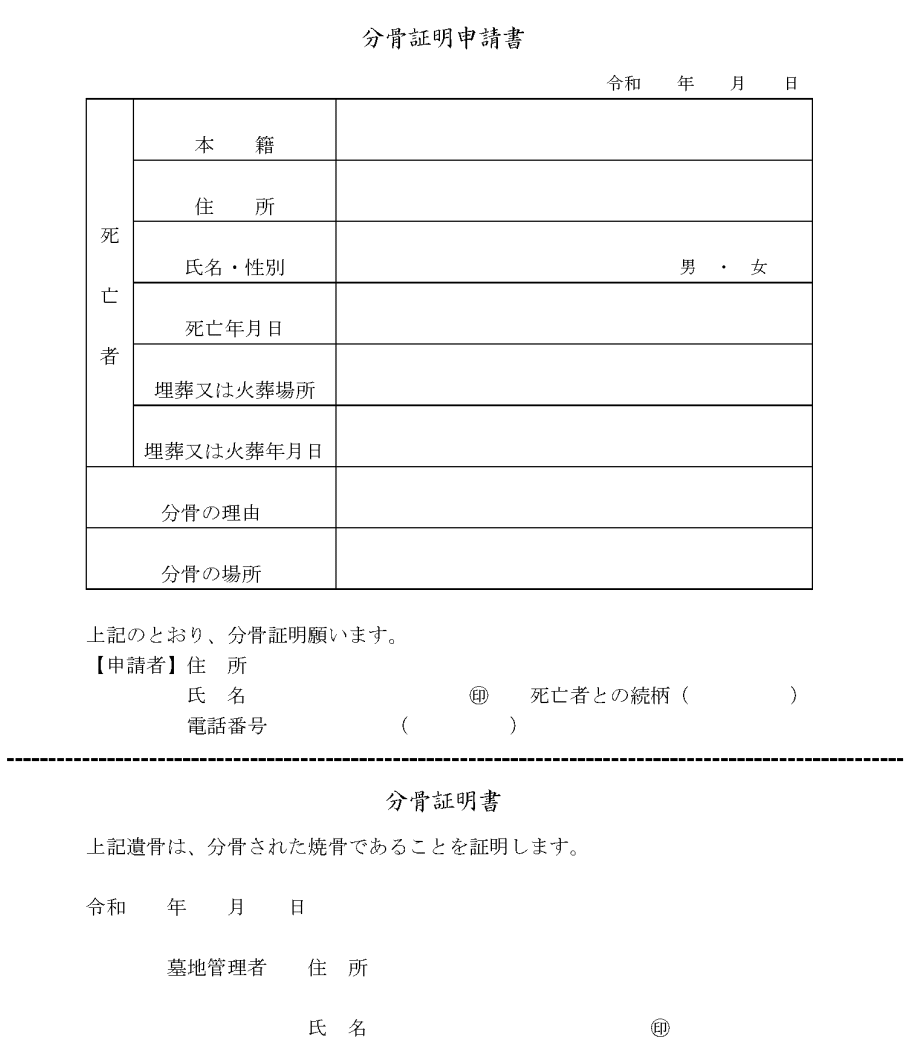
4. 分骨にかかる主な費用
分骨にかかる費用は、分骨の方法(埋葬されている遺骨か、火葬時か)、分骨先、依頼する業者などによって大きく異なります。主な費用項目を以下に挙げます。
(1)分骨先(新しい埋葬・供養方法)の費用
分骨した遺骨をどこに納めるかによって費用は大きく変動します。
新たに墓地を取得し墓石を建てる場合、100万円以上かかることが一般的です。
→ 新しいお墓の費用に関する詳細は【お墓の契約・購入】時期・費用・見学ポイント で詳しく解説しています。
合祀墓や集合墓、単独墓など形式により、数万円から数十万円程度が相場です。
→ 永代供養墓に関する詳細は【永代供養墓】基礎知識・選び方 で詳しく解説しています。
ロッカー式、自動搬送式など形式により、数十万円から百万円程度が相場です。
→ 納骨堂に関する詳細は【納骨堂とは】選び方・費用・注意点を解説 で詳しく解説しています。
埋葬方法や場所により、数万円から数十万円程度が相場です。
→ 樹木葬に関する詳細は【樹木葬】基礎知識・選び方 で詳しく解説しています。
自宅での安置、アクセサリー加工など、数千円から数十万円程度まで様々です。
→ 手元供養に関する詳細については【手元供養】注意点と知っておくべきこと で詳しく解説しています。
業者に依頼する場合、数万円から。粉骨費用なども別途かかる場合があります。
→ 散骨に関する詳細については【散骨の基礎知識】費用・注意点を解説 で詳しく解説しています。
(2)遺骨の取り出し・移し替え費用(お墓に埋葬されている場合)
現在お墓に埋葬されている遺骨を分骨する場合、墓石を開閉し遺骨を取り出す作業が必要です。
お墓の開閉作業、遺骨の取り出し、分骨用の骨壺への移し替え、お墓を元の状態に戻す作業などを石材店に依頼する費用です。一般的に2万円~5万円程度が相場ですが、墓石の大きさや構造、現地状況によって異なります。事前に見積もりを取りましょう。指定石材店がある場合は、そこに依頼します。
→ 石材店の選び方に関する詳細については【改葬】石材店の選び方と費用 で詳しく解説しています。
(3)分骨証明書の発行手数料
分骨元の墓地管理者が分骨証明書を発行する際に、手数料が必要となる場合があります。数百円から数千円程度であることが多いです。
(4)分骨用の骨壺・骨袋
分骨した遺骨を納めるための骨壺や骨袋の費用です。分骨先の規定に合ったものを用意します。小さな骨壺であれば数千円程度から購入できます。
(5)供養に関する費用(お布施・玉串料など)
分骨を行う際や新しい分骨先に納骨する際に、読経や儀式を依頼した場合にかかる費用です。
- お布施(仏式): 分骨元のお寺への御礼、分骨先の納骨供養など。お気持ちですが、一般的に数万円程度を包むことが多いようです。お車代なども必要に応じて。
- 玉串料(神式)、謝礼(キリスト教式):各宗教・宗派によって呼び方や金額の考え方が異なります。
供養を行うかどうかは、ご家族のお考えや分骨先の規定によって選択できます。
5. 分骨を行う上での注意点

分骨をスムーズに行い、後々のトラブルを防ぐために、いくつかの注意点があります。
最も重要なのは、遺骨の所有権者やご兄弟などの親族と、分骨の理由、分骨先、手続きの進め方について十分に話し合い、同意を得ることです。同意を得られたことは、書面(承諾書・同意書)で残しておくとより安心ですし、後々の言った言わないの争いを避けるためにも有効です。
分骨手続きの可否、必要書類、手続きの流れ、費用など、分骨元と分骨先の双方の管理者に事前にしっかりと確認することが必須です。
分骨証明書は、分骨先の納骨時に墓地埋葬法によって提出が義務付けられている重要な書類です。分骨元の墓地管理者から確実に発行してもらう必要があります。管理者に様式がない場合の対応なども含め、事前に確認しておきましょう。
火葬時に分骨するか、埋葬後に分骨するかによって流れが異なります。また、埋葬後の場合、遺骨の取り出しについて石材店と十分に打ち合わせましょう。
新しい分骨先が、骨壺のまま納骨できるか、骨袋に移す必要があるか、分骨証明書以外の必要書類は何かなど、納骨に関する規定を事前に確認しておく必要があります。
石材店への費用、供養料、管理費など、発生しうる費用について事前に確認し見積もりを取得しましょう。
6. まとめ:分骨を円滑に進めるために

分骨は、故人の供養に対する多様なニーズに応える方法ですが、遺骨の所有権や親族の同意、行政手続き、新しい納骨先の準備など、いくつかの重要なステップを踏む必要があります。
分骨を後悔なく、スムーズに進めるためには、事前の情報収集と計画、そして最も重要である関係者との十分な話し合いと同意が鍵となります。特に、分骨証明書の取得は、将来的なトラブルを避けるために不可欠な手続きであり、法律でその提出が定められています。
ご自身での手続きに不安がある場合や、関係者との調整が難しい場合など、複雑な事情がある場合は、お墓の手続き専門家(行政書士など)に相談することも有効な手段です。
専門家のサポートを得ることで、手続きの負担を軽減し、安心して分骨を進めることができます。
→ 分骨に関するより詳細な情報は【分骨マニュアル】手続き・費用・注意点 をご覧ください。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)