


「お墓に遺骨を埋葬しようと寺院に連絡したら、埋葬を拒否されてしまった」――このような予期せぬ状況に直面し、戸惑われる方は少なくありません。なぜ、お墓の管理者である寺院から埋葬を拒否されてしまうのでしょうか。
このページでは、寺院が埋葬を拒否する主な理由とその背景を深く掘り下げ、実際に埋葬拒否されてしまった場合の具体的な対処法を解説します。また、将来的なトラブルを未然に防ぐための事前対策についても、お墓専門の行政書士が分かりやすくご案内します。いざという時に慌てないためにも、ぜひご参考ください。
1. 寺院に埋葬を拒否される主な理由と背景
お墓に埋葬を依頼した際に寺院から拒否されるケースには、いくつかの共通する理由があります。
(1)戒名や供養を他の寺院で行った場合
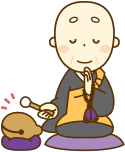
葬儀供養や戒名を、お墓を所有する寺院ではない他の寺院(ご住職)に依頼した場合に、埋葬を拒否されることがあります。特に戒名は、埋葬する寺院が故人をその寺院の仏弟子として授け、埋葬を行うという考え方があります。
そのため、他の寺院が授けた戒名では埋葬できない、あるいは戒名を付け直してほしい、と言われることがあります。これは一般的な寺院において共通の考え方と言えます。
(2)檀家としての義務を果たしていない場合
寺院墓地では檀家であることが前提となるため、護持会費の滞納や、長期間寺院への連絡・訪問がないなど、檀家としての義務を怠っていると判断された場合に埋葬を拒否されることがあります。寺院側からすれば、最低限守ってほしいルールと見なされるためです。
(3)その他(宗旨・宗派の不相違、人間関係など)
契約時と異なる宗旨・宗派に改宗していた場合や、ご住職との人間関係が悪化している場合なども、埋葬拒否の理由となることがあります。霊園の規約違反(例:ペットの埋葬不可、墓石の形状制限など)も理由となりえますが、寺院墓地においては上記のような宗教的・関係的な理由が中心です。
2. 埋葬拒否を避けるための事前対策と不幸時の対応
急な不幸があった際に埋葬拒否で慌てないよう、事前の対策と不幸時の適切な対応を知っておくことが大切です。
(1)不幸があった場合に最初にすべきこと
急な不幸があった場合、精神的に不安定な状態で埋葬のことまで気が回らないこともありますが、もし埋葬する墓地を所有(承継)している場合は、最初にその寺院のご住職に連絡することが何よりも重要ですし、その連絡が遅れた場合は、埋葬を拒否される理由にもなります。
寺院が遠方の場合でも、まず電話で状況を説明し、「葬儀供養はこちらで行っても良いか」「戒名はそちらにお願いする形で良いか」など、寺院の意向を最初に相談しましょう。これにより、納骨までスムーズに進めることができます。あるご住職は、葬儀社等に依頼する前に、まず最初に相談してほしいと話されています。
(2)ご住職との関係に不安がある場合の事前対策
もし、檀家になっている寺院のご住職を葬儀に呼びたくない、あるいは関係性に不安がある場合は、不幸が起こる前に、その関係を整理しておくことを検討しましょう。具体的には、墓じまいと離檀(寺院との縁を切ること)を事前に済ませておくという方法です。
これにより、時間的に余裕があるうちに、新しい供養先(別の霊園、永代供養墓など)を決め、安心して整理を進めることができます。実際に不幸が起きてから、全ての手続きを同時に行うことは、精神的・肉体的に大きな負担となります。
→ ご住職との口約束に関する注意点については【ご住職との口約束】お墓に関する注意点とトラブル予防 をご覧ください。
3. もし埋葬を拒否されてしまったら?(具体的な対処法)
万が一、埋葬を拒否されてしまった場合でも、感情的にならず冷静に対処することが大切ですし、いざという時に慌てないための準備も重要です。
(1)まずは冷静に話し合い、理由を確認する
まずは、失礼があったことを謝罪し、なぜ埋葬を拒否されるのか、その理由を具体的にご住職に確認しましょう。多くの場合、誤解や情報の行き違い、あるいは寺院の規則に関する理解不足が原因であることがあります。
(2)拒否が続く場合の選択肢(専門家への相談、改葬など)
話し合いで解決が難しい場合や、寺院側から戒名の付け直しや離檀を求められ、それが納得できない場合は、他の選択肢を検討することになります。
・専門家への相談:お墓の問題は法的な知識やデリケートな交渉が必要となるため、お墓専門家や弁護士に相談することを検討しましょう。行政書士は、適切な情報提供、書類作成の支援など行うことができます。弁護士は、訴訟など法的な手段が必要な場合の代理人となります。
・改葬の検討:場合によっては、現在の寺院墓地を墓じまいし、別の寺院や民営霊園、永代供養墓などに改葬するという選択肢もあります。
→ 改葬手続きの詳細は【改葬(お墓の引越し)】相談・手続代行 をご覧ください。
(3)埋葬拒否に関する法的根拠(墓地埋葬法第13条)
墓地、納骨堂、火葬場の管理者は、「正当な理由がなければ埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを拒んではならない」と墓地埋葬法第13条に定められています。
・注意点: しかし、「正当な理由」の判断は難しく、最終的には裁判所の判断になります。トラブルを避けるためには、ご住職との関係性を維持しつつ、誠実な話し合いを行うことが最善策です。無理に埋葬を求めても、その後の墓参りなどでストレスを感じることにもなりかねません。
4. まとめ:埋葬拒否トラブルを未然に防ぐために
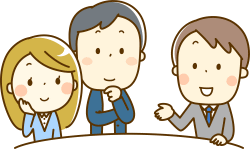
寺院から埋葬を拒否されるという事態は、事前に適切な知識と準備があれば、多くの場合避けることができます。特に、不幸があった際には、まずはお墓を管理する寺院に連絡を取り、ご住職と十分にコミュニケーションを取ることが重要です。
また、ご家族間でお墓に関する考え方や、万が一の際の対応について事前に話し合い、共通認識を持っておくことも、予期せぬトラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)













