

都立霊園とは?申込方法・要件、お墓の種類、徹底解説
 ・「お墓を建てる。」という経験は、人生で何度も行うことではありません。そのため、「都立霊園に申込むには?」「どのような要件があるのか?」「お墓の種類は?」など、分からないことや不安に感じることが多いかと思います。
・「お墓を建てる。」という経験は、人生で何度も行うことではありません。そのため、「都立霊園に申込むには?」「どのような要件があるのか?」「お墓の種類は?」など、分からないことや不安に感じることが多いかと思います。
都立霊園とは、東京都が設置している公営の霊園です。23区内に4箇所、多摩地区に3箇所、千葉県に1箇所あります。
東京都が運営しているため、信頼度が他の霊園に比べ高く、立地も比較的に良い場所にあります。また、永代使用料や管理費も比較的リーズナブルなため、人気があり関心が高まっています。
当事務所は、平成21年度開業のお墓専門の行政書士事務所です。お墓の手続きを専門とし、これまでに100件以上の墓じまい・改葬を行っております。このページでは、都立霊園の詳しい申込方法、申込要件、お墓の種類、そしてメリット・デメリットまで、お墓専門の行政書士が分かりやすく徹底解説いたします。
都立霊園への申込をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
1. 都立霊園の申込方法
都立霊園では、通常、毎年1回新規使用者の募集をしています。申込からお墓を建てるまでの流れについては、下記の流れになります。
(1)募集の公示から申込みまで
- 募集の公示:《広報東京都》6月号にて公表されます。また都立霊園公式サイトTOKYO霊園さんぽのサイトにも掲載されます。
- 申込み(6月下旬~7月上旬): 申込書を郵送、またはインターネットにて申込みが可能です。
- 受付番号通知(8月上旬): 有効な申込に対し、受付番号が通知されます。通知後、倍率が発表されます。
- 公開抽選(8月下旬):都庁にて公開抽選会が開かれます。抽選結果は、受付番号を取得した方全員に通知(9月上旬)されます(当選・補欠・落選)。また、翌日からは上記サイトTOKYO霊園さんぽにも掲載されます。当選された方には、別途、当選墓所や書類審査の日程が通知されます。
(2)資格審査から使用許可書交付まで
- 資格審査(9月下旬~10月上旬):公益財団法人東京都公園協会が指定した場所にて、当選者に対する書類審査が指定日に行われます。その際に、使用申請書を提出します。尚、合葬埋蔵施設の場合、郵送による書類審査となります。合葬埋葬施設には、樹林型、樹木型が含まれます。
- 支払い(11月上旬):納入通知書が届きます。期限までに納入がない場合、使用許可を辞退したものとみなされますのでご注意ください。
- 許可書交付(12月上旬):入金が確認されますと、使用許可書が交付されます。
(3)墓石建立
・墓石建立:使用許可書交付後、墓石の建立が可能になります。
(4)申込用紙の取得方法

- TOKYO霊園さんぽ(PDF形式)
- 東京都庁の案内コーナー
- 東京都内区市町村役所の窓口
- 千葉県松戸市役所の窓口
- 公益財団法人東京都公園協会本社
上記にて配布されています。申込みは、インターネット上での申込と、郵送での申込が可能です。インターネットの場合、申込者登録・ログインの必要があります。また登録は、申込期間の少し前から行えますので、事前登録をおすすめします。郵送の場合、期間を過ぎてしまうと受付が出来なくなってしまうので、早めに郵送するようにしましょう。
2.申込要件
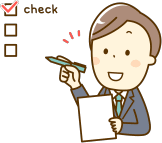
倍率の高い都立霊園。せっかく当選したのに、書類審査で失格になったりしないように、申込をする際には、資格要件をきちんと把握しておくことが、非常に大切です。それぞれの墓所により要件は変わってきますが、基本的な要件を記載していきます。
(1)一般埋蔵施設・芝生埋蔵施設・小型芝生埋蔵施設・立体埋蔵施設・長期収蔵施設の要件
- 5年以上継続して都内(八柱霊園の場合、松戸市を含む)に住んでいる。
- 現在 守っている“親族の遺骨”がある。
- その遺骨に対して、あなたは、※祭祀の主宰者である。
※祭祀の主宰者(例:葬儀の喪主を務めた。/法事の施主を務めた。/役所に死亡の届を提出した、或いは火葬の申請をした。)
(2)合葬埋蔵施設(樹木・樹林を含む)の要件
①遺骨申込
- 3年以上継続して都内(八柱霊園の場合、松戸市を含む)に住んでいる。
- 現在守っている遺骨がある。
- 遺骨に対しての祭祀の主宰者である。
②遺骨・生前申込
・生前者については、全員が3年以上継続して都内(八柱霊園の場合、松戸市を含む)住んでいる。(遺骨は除外)
・現在守っている遺骨が1体又は1体以上あり、その遺骨と親子、夫婦、兄妹関係である。
③生前申込
・生前者、また お墓に入る予定の全員が、都内(八柱霊園の場合、松戸市を含む)に、3年以上継続して住んでいる。
申込要件は、それぞれの墓所により変わりますが、基本的には上記内容となります。毎年、せっかく当選されたのに、資格不足で失格になる方が少なくありません。Tokyo霊園さんぽのサイトには、細かな各墓所の資格要件が記載されている「申込みのしおり」があります。そちらのしおりで、きちんと確認しましょう。
3. 都立霊園における墓じまい・改葬の流れ
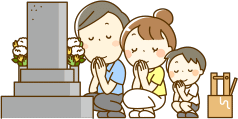
ここでは、都立霊園でのお墓の墓じまいから、改葬(お引越し)を行う際の手続きの流れを解説いたします。都立霊園特有の施設変更制度や、民間霊園への改葬、散骨を行う場合の注意点まで、詳細にご説明します。
(1)墓地返還に関する書類
都立霊園で墓地返還(墓じまい)を行うには、下記の書類を管轄の管理事務所に提出する必要があります。
① 都立霊園の規定の様式を提出する書類
最初に住所、氏名、電話番号を記入します。霊園使用許可証を参考にわかる範囲で記入します。分からない箇所は、空欄にしておき管理事務所で確認して記入した方が確実です。(この書類のみ実印を押印します。)
住所、氏名、電話番号を記入した上で押印(認印)を行います。下段の請負業者欄は、墓石を撤去する石材店になりますので、管理事務所で手続きを行う前に、石材店を決め記名押印をお願いしておきます。
石材店がお墓の撤去が完了した際に提出する書類になります。石材店にこの書類を渡す際に撤去工事の開始、完了の予定日を確認しておきましょう。(通常、届日から1か月程度の期間)
(2)改葬許可申請書類
都立霊園の場合は、「改葬許可申請に伴う埋蔵(埋葬)・収蔵 証明願」と「改葬許可申請書」が2枚綴りになっております。こちらは管理事務所に備えられている墓地台帳を確認しながら記入します。
記入後に管理事務所から「改葬許可申請書」を渡されますので、この書類を霊園の所在地を管轄する自治体(市区町村)に提出し改葬許可証を取得します。
(3)添付書類
墓地返還及び改葬には下記の書類を添付して申請を行います。
- 都立霊園の使用許可書(原本)
- 印鑑証明書(発行3か月以内のもの)(原本)
- 改葬先の受入れ証明書又は使用許可証(原本)
(4)承継者の変更がある場合
墓地使用者が亡くなり、祭祀承継者が墓じまい・改葬を行う場合、墓地承継に関する手続きが必要になります。具体的には下記の書類等を提出する必要があります。
- 被相続人(墓地所有の故人)の死亡が記載された戸籍謄本
- 承継人の6カ月以内の戸籍謄本
- 名義人(被相続人)と承継人の関係を示す戸籍謄本
- 承継人の実印と3カ月以内の印鑑証明書
- 承継使用申請書
- 墓地(霊園)使用許可証(お墓の使用権を取得した契約時に発行される書類です。)
- 葬儀の時の領収書、又は遺言書等
(5)墓じまい(都立霊園)から改葬する流れの全体フロー
① 申請書類の取得
管轄の都立霊園管理事務所から①使用終了届、②返還に関わる誓約書、③返還工事終了届の書類を(郵送、又は墓地管理事務所にて)取得します。書類が届きましたら、申請者の氏名、住所、連絡先等を記入し押印を行います。
![]()
② 石材店との契約

都立霊園は公営墓地になりますので、お墓の撤去を行う石材店を自由に決めることが出来ます。その代わりご自身が責任をもってお墓の撤去まで行う必要があります。石材店との契約が完了したら、都立霊園管理事務所に提出する「返還に関わる誓約書」に石材店の記名・押印をもらいます。また、返還工事終了届も石材店に渡しておきましょう。
ご自身で石材店を決める必要がありますが、特に心当たりがない場合にどうすれば良いか解説いたします。
- 都立霊園の近くの石材店に依頼する。:都立霊園は大きな霊園ですので、入り口付近に複数の石材店が店舗を構えています。この近くの石材店であれば書類の引渡しもスムーズに行うことができます。
- 霊園から紹介してもらう。:霊園によっては、出入りの石材店数社を紹介してもらえる場合があります。この中から石材店を選ぶのも一つの方法です。
- ご自身で石材店を選ぶ。:ネット等で調べ、評判の良さそうな石材店に依頼することも可能です。但し、石材店が遠方の場合は出張費など追加され撤去料金が高くなる場合がありますのでご注意下さい。
- 当事務所に相談する。:当事務所では、大手の石材店を始め、これまで撤去などを依頼してきた石材店とのネットワークがあります。もし、ご自身で見つけるのが不安な場合は、当事務所までご相談下さい。数社の石材店をご紹介させて頂きます。(石材店との契約はご自身の責任においてご契約下さい。
![]()
③ 改葬先との契約など
改葬許可申請を行う際には、改葬先の霊園等の使用許可証又は、受入れ証明書が必要になります。これらの書類は、通常、霊園との契約後に発行されます。又、改葬許可申請書には、改葬先の場所(霊園)を記入する欄がありますので、都立霊園管理事務所で手続きを行う前に改葬先を決めておく必要があります。
都立霊園にお墓を所有されている方が、墓じまいを行う場合、「施設変更制度」を利用し、小平・多摩・八柱霊園のいずれかの永代供養墓(合葬埋葬施設)に改葬することが可能です。募集は、通常一年に3回(仮申込は通年受付け)行われ使用料、維持管理費用も掛かりません。
・施設変更の際に提出する書類等:使用終了届(現在使用しているお墓の)、施設変更申請書、施設変更に係る誓約書。その他、①住民票(本籍記載)、②印鑑証明書(3か月以内のもの)、③使用許可証(現在のお墓の)を添付して申込を行います。この申込後、合葬埋葬施設の使用許可証が郵送で届きます(2~3か月後)。
上記、許可証の到着後、現在、お墓がある霊園の管理事務所で改葬手続きを行います。(手続き後に改葬許可申請書が発行されます。)次に、自治体(市区町村)で改葬許可申請を行い許可証を取得します(通常の場合、当日発行されます)。後は、ご遺骨を移動し合葬埋葬施設に納骨して完了となります。
民営の霊園の場合、費用は掛かりますが、ご自宅の近くに埋葬することも可能で契約後、直ぐに改葬することも出来ます。基本的には、ご自身の希望にあう霊園を選び契約することになります。ちなみに永代供養墓の費用は、合祀(他の遺骨と一緒に埋葬)5万円程度~50万円程度、合葬(共同の区画に個別埋葬)の場合は、10万円~100万円程度になります。
散骨を行う場合、自治体(市区町村)から改葬許可証は、原則発行されません。この場合、自宅保管等の形にして墓地返還手続きのみを行うことになります。
![]()
④ 墓地返還手続き及び改葬許可申請書の取得
墓地管理事務所に行く前に、添付する書類(①印鑑証明書、②都立霊園の使用許可証、③改葬先の使用許可証(受入れ証明書)及び、霊園既定の書類、実印・認印等を再度確認した上で管理事務所に向かいます。管理事務所で墓地返還に関する書類を提出し、次に、改葬に関する手続きを行います。
霊園より改葬許可申請が発行されましたら、管轄の自治体(市区町村)にて改葬許可申請を行い許可証を取得します。
![]()
⑤ 改葬日

許可証が取得できましたら、改葬日を決定します。(各関係先と事前に日程を調整しておきましょう。)
・現在のお墓(墓じまい)の連絡先
- 石材店:遺骨の取出しの為(撤去は後日行われます。)
- ご住職:閉眼供養を行う場合(お布施も忘れずに)
・改葬先の連絡先
- 霊園等:通常、改葬先の霊園等に日時の予約を行っておく必要があります。
- 石材店:納骨の為(霊園等によっては不要)
- ご住職:納骨供養を行う場合
以上、都立霊園の改葬の流れになります。
3.お墓の種類(都立霊園で利用可能な埋蔵施設)
都立霊園には、一般・芝生・壁型・立体・合葬という5種類の埋蔵施設があります。いずれも使用期限に定めはありません。
(1)一般埋蔵施設
- 一般的な平面形式の墓地。形式・方角等は 様々です。墓石は、設置されていない為、ご自身で お墓を建立する施設になります。
(2)芝生埋蔵施設
- 一面芝生の平坦地に、等間隔に埋葬施設が配置されています。ご遺骨を納める納骨室は既に設置されていますが、墓石の設置はないため、ご自身で建立します。
- また、納骨室の改造、塔婆立の設置、囲障の設置は出来ません。
- 従来の芝生埋葬施設の他に、小さく設定された「小型芝生埋葬施設」もあります。芝生埋葬施設と同様、納骨室の設置はありますが、墓石の設置はありません。納骨室の改造、塔婆立の設置、囲障の設置、また個別の線香立の設置は不可です。(共同の線香台があります。)
(3)壁型埋蔵施設
- 自然石で造られた墓石を壁面状に連続して配置した埋葬施設(平成2年から造成)。小平霊園・八柱霊園・多磨霊園にあります。墓石と納骨室の設置がされており、使用者は墓石に家名を表示することができます。
(4)合葬埋蔵施設
- 一つの お墓に多くの遺骨を共同埋葬する施設です。年間管理料は不要です。また、生前でも申し込みが可能です。使用許可日から個別に20年間預けた後、共同埋葬する「一定期間後共同埋葬」と、納骨時に共同埋葬する「直接共同埋葬」があります。
(5)立体埋蔵施設
- 青山霊園と谷中霊園に設置。使用許可日から20年間は、地上の納骨室を使用でき、その後は、地下納骨室に共同埋葬します。永代で使用出来ます。ご遺骨3体まで納骨できます。お墓を継ぐ人のいない方でも申込むことができます。
(6)樹木・樹林合葬埋蔵施設
- 小平霊園にある施設です。「死後は、安らかに自然に還りたい。」と言う要望により造設。樹林合葬は、生前申込ができます。樹木合葬は生前申込はできません。どちらも より自然に還りやすくするために、個別に布製の納骨袋に移して埋蔵されます。
(7)収蔵施設
①長期収蔵施設
ロッカー形式の墓所に遺骨を収蔵する施設。使用期間は30年間。更新可能(別途使用料)。多摩霊園に設置。
②短期収蔵施設
雑司が谷崇祖堂に家族納骨檀として設置。使用期間は5年間。更新が可能。
③一般収蔵施設
墓地を取得するまでの期間、一時的な遺骨の保管を目的として設置。使用期間は1年。更新は4回まで。多摩霊園・八柱霊園・雑司が谷霊園の3箇所に設置。
4.都立霊園のメリット・デメリット
(1)メリット
① 東京都が運営しているので、永続性という点において将来的な安心感があります。
② 比較的に管理料が安価です。
③ 宗教・宗派を問わない:在来仏教以外の方、無宗教の方でも使用できます。また都立霊園に限らず公営墓地は、ほぼ全て宗教・宗派は問いません。
④ 歴史のある墓地が多いです。
⑤ 石材店を自身で選べます。※都立霊園及び公営墓地には指定石材店はありません。
⑥ 敷地が広く、開放感がある墓地施設です。
(2)デメリット
① 競争率が高い抽選です。(最大のデメリットは、高倍率の抽選に当選しなければ使用権を取得することが出来ないという点です。)
② 生前申込がほとんど箇所では出来ない。(それぞれの霊園で異なりますので、事前確認が必要です。)
③ 資格要件がある。(申込者の居住要件、遺骨の有無などの資格要件が各霊園によって異なります。せっかく高倍率の抽選に当たったのに資格要件を満たせずに失格になる方も多いようです。必ず、申込の前に確認することをお勧めします。)
④ 宗教・宗派を問わないので、僧侶の手配は ご自身で手配、また法要施設がほとんどの箇所でないので、こちらの手配もご自身でする必要があります。
⑤ ほとんどの霊園において、希望の区画が選べないことが多い。
⑥ 都立と言っても、永代使用料は必ずしも安くはない。
(維持費は、かなり安価で納まりますが、霊園の場所、また埋葬方法によっては、都内の民間霊園よりも高価になる事もあります。例えば、歴史も古く有名人などの お墓も多い青山霊園の一般墓所の永代使用料は、約1000万円です。)
5.各都立霊園 所在地・連絡先
| 名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
| (1)青山霊園 | 〒107-0062 港区 南青山2-32-2 | 03-3401-3652 |
| (2)谷中霊園 | 〒110-0001 台東区 谷中7-5-24 | 03-3821-4456 |
| (3)雑司ケ谷霊園 | 〒171-0022 豊島区 南池袋4-25-10 | 03-3971-6868 |
| (4)染井霊園 | 〒170-0003 豊島区 駒込5-5-1 | 03-3918-3502 |
| (5)八柱霊園 | 〒270-2255 千葉県 松戸市 田中新田48-2 | 047-387-2181 |
| (6)八王子霊園 | 〒193-0826 八王子市 元八王子町3-2536 | 042-663-1533 |
| (7)多磨霊園 | 〒183-0002 府中市 多磨町4-628 | 042-365-2079 |
| (8)小平霊園 | 〒189-0012 東村山市 萩山町1-16-1 | 042-341-0050 |
6.まとめ:都立霊園の申込は、お墓専門行政書士にご相談を

都立霊園は、信頼性・安心度が高く、費用も比較的安く、立地も良いことから人気が高いのは当然と言えます。しかし、応募条件が細かく定められており、人気の有る墓地では競争率が高く、空きが出るまで募集されない場合もあります。
また、他の民営霊園と比べて手続きが複雑な面があり、墓地承継者変更手続きなどを行う場合、戸籍や住民票、印鑑証明書など、様々な書類が必要になり時間がかかることもあります。
当事務所でもこれまでに、そのような手続きを行わせて頂きましたが、特に〔伯父・伯母等の直系ではない、親族のお墓を承継者がいない為、墓じまいする〕場合、戸籍等、様々な書類が必要になり時間も掛かります。
当事務所は、開業15年の行政書士事務所であり、都立霊園の手続きについても豊富な経験と実績があります。墓地承継者変更届、墓地返還届、使用許可書の再発行、改葬許可申請、都立霊園の申込手続、都立霊園内の墓じまいから永代供養墓への改葬手続など、都立霊園に関する多様な手続きをサポートしております。
もし、ご自身での手続きが難しい、あるいは不明な点がありましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。相談無料ですので、安心してお問い合わせいただけます。
7.事務所案内(事務所実績)
お客様が選ぶ安心:豊富な実績と信頼
大塚法務行政書士事務所は、開業以来、数多くの複雑なお墓に関するご相談に対応し、お客様の不安を解決してまいりました。都立霊園の手続きに関する問題も、長年の経験と実績に基づき、最適な解決へと導きます。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)














