


両親が所有していた寺院墓地を承継することになったものの、自分自身の宗教や宗派が異なる場合、あるいは檀家になることに抵抗がある場合、「このままお墓を継いで良いのだろうか?」「故人を埋葬することは可能なのか?」といった悩みを抱える方は少なくありません。
檀家制度は日本の寺院墓地特有の慣習であり、その理解なしに進めると、予期せぬトラブルに発展することもあります。
この記事では、檀家以外の方が寺院墓地を承継し、埋葬を行う際の法的な解釈、過去の通達や判例を参考にしながら、具体的な手続き、そして実際に発生しやすい課題と円満な解決策を、お墓専門の行政書士が詳しく解説します。ご自身の状況に合わせた最適な選択をするためのヒントをぜひ見つけてください。
1. 檀家以外でも寺院墓地への埋葬は可能か?法律・通達・判例から読み解く
(1)墓地、埋葬等に関する法律 第十三条
墓地、埋葬等に関する法律(以下、墓埋法)第十三条には、以下の規定があります。
墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
この条文にある「正当な理由」が、檀家以外の方の埋葬を拒否できるかどうかの論点となります。
(2)過去の通達と判例の解釈
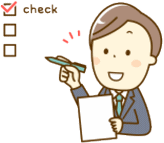
厚生労働省から内閣法制局への照会に対する過去の通達や、裁判所の判例は、この「正当な理由」の解釈に影響を与えています。
・「宗教団体がその経営者である墓地に、他の宗教団体の信者が埋葬又は埋蔵を求めたときに、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由としてこの求めを拒むことは、『正当な理由』によるものとはとうていみとめられないであろう。」
・「したがって、宗教団体が墓地を経営する場合に、当該宗教団体がその経営者である墓地の管理者が埋葬又は埋蔵の方式について当該宗派の典礼によるべき旨を定めることは許されようから、他の宗教団体の信者たる依頼者が自己の属する宗派の典礼によるべきことを固執しても、こういう場合の墓地の管理者は、典礼方式に関する限り、依頼者の要求に応ずる義務はないといわなければならない。」
つまり、法的な見解としては、「宗派が違うことだけを理由に埋葬を拒否することはできないが、寺院側は自宗派の儀式(典礼)に従うよう求めることができる」と解釈されます。
ただし、判例には諸事情を考慮し、典礼に従わない(無典礼)場合でも埋葬を拒否できないとしたケース(宇都宮地判 平24.2.15)もあります。しかし、必ずこのような判断がされるわけではなく、最終的な判断は裁判所に委ねられることになります。
2. 檀家以外の承継者が検討すべき具体的な選択肢
前章の法的解釈を踏まえると、檀家以外の承継者が寺院墓地への埋葬を希望する場合、主に以下の選択肢が考えられます。
(1)寺院の典礼に従い埋葬する
最も円満な解決策の一つは、寺院の典礼(儀式・しきたり)に従って故人を埋葬することです。
- 寺院との事前協議:事前にご住職と丁寧に話し合い、典礼の内容や、戒名の要否(寺院によっては必須の場合が多い)などを確認しておきましょう。
- 関係性の構築:今後も寺院墓地を利用する意思があるのなら、ご住職との良好な関係を築く努力も重要です。
→ ご住職への話し方の詳細は【墓じまい】ご住職への話し方をご覧ください。
→ 戒名に関する詳細は【お位牌と戒名】基礎知識と役割を解説をご覧ください。
→ 戒名なしでの葬儀・埋葬の詳細は【戒名なし】葬儀・埋葬は可能?費用と手続きを解説をご覧ください。
(2)改葬(お墓の引越し)を検討する
寺院の典礼に従うことに抵抗がある場合や、ご住職との話し合いが進まない場合は、現在のお墓を墓じまいし、別の霊園などに改葬することも有効な選択肢です。
公営霊園や多くの民営霊園は、宗教・宗派不問で利用できます。新しい供養先で、ご自身の宗派や希望に合った形式を選択できます。ただし、公営霊園には居住要件や抽選の有無、民営霊園には費用や使用規則の違いがあるため、事前確認が重要です。
→ 墓地の種類(公営・民営・寺院)の詳細は【墓地の選び方】公営・民営・寺院墓地のメリット・デメリットをご覧ください。
永代供養墓、樹木葬、納骨堂、散骨など、近年多様な供養形式が登場しています。これらは宗派不問のことが多く、承継者問題の解決にも繋がります。
→ お墓は不要か?いらない場合の選択肢の詳細は【お墓は不要か】必要か?いらない場合の選択肢をご覧ください。
→ 永代供養墓の詳細は【永代供養墓】基礎知識・選び方をご覧ください。
→ 樹木葬の詳細は【樹木葬】基礎知識・選び方をご覧ください。
→ 納骨堂の詳細は【納骨堂とは】選び方・費用・注意点を解説をご覧ください。
→ 散骨の詳細は【散骨】相談・手続代行をご覧ください。
(3)無典礼での埋葬を交渉する
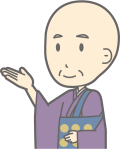
寺院との交渉力や、個別の事情によっては、無典礼での埋葬を認めてもらえる可能性もゼロではありません。しかし、一般的には寺院側が難色を示すケースが多いため、覚悟が必要です。
- 交渉の準備:寺院との交渉に進む場合は、なぜ無典礼を希望するのか、具体的にどうしたいのかを整理し、誠意をもって伝えましょう。
- 専門家への相談:難しい交渉が予想される場合や、法的手段を検討する場合は、弁護士など専門家のアドバイスを求めることも重要です。
3. 檀家以外の墓地承継、手続きの流れと注意点
檀家以外の承継者が寺院墓地を承継し、埋葬を検討する際の手続きの流れと注意点を解説します。
(1)家族・親族間での合意形成
お墓の承継は、単なる名義変更ではなく、家族・親族間の感情が絡むデリケートな問題です。トラブルを避けるために、まずは承継者候補となる人々と十分に話し合い、合意を形成することが最も重要です。
- 誰が「祭祀承継者」としてお墓を継ぐのか。
- お墓の維持管理費や将来の費用負担をどうするのか。
- 現在のお墓をこのまま維持するのか、墓じまいして別の場所へ改葬するのか。
- 故人の宗教・宗派と承継者の宗教・宗派が異なる場合の対応。
→ お墓の承継に関する詳細は【お墓の承継】基本と法律をご覧ください。
→ お墓の相続に関する詳細は【お墓の相続】ガイド|費用・税金・手続きの疑問を解決をご覧ください。
→ お墓の承継トラブルに関する詳細は【お墓の承継トラブル】Q&A・事例と対策をご覧ください。
(2)墓地管理者への連絡
家族・親族間で方針が決まったら、お墓のある寺院の管理者にご連絡し、今後の埋葬の可否や典礼の対応、承継手続きについて相談します。
- 正直かつ丁寧に:檀家ではないことや、宗派が異なること、戒名に対する考えなど、正直かつ丁寧に伝えましょう。
- 早期の相談: 後々のトラブルを避けるためにも、できるだけ早い段階で相談することが大切です。
(3)改葬を選択する場合の具体的な手順
もし寺院墓地での埋葬が難しい、または望まない場合は、改葬の手続きを進めることになります。
- 現在の墓地管理者(寺院)に改葬の意思を伝える。
- お墓を撤去する石材店を決め、契約を行う。
- 改葬先の霊園や埋葬形式を決定し、契約を行う。
- 改葬許可申請書を役所で取得し、必要な書類を準備する。
- 改葬許可取得後、関係各所と調整を行い、遺骨の取り出しと新しい供養先への納骨日時を決定する。
→ お墓じまいマニュアルの詳細はお墓じまいマニュアルをご覧ください。
→ 改葬(お墓の引越し)マニュアルの詳細は改葬(お墓の引越し)マニュアルをご覧ください。
→ 改葬許可申請書の詳細は【改葬許可申請書】取得・記入方法と必要書類をご覧ください。
→ 墓じまい費用の詳細は【墓じまい費用】誰が負担?相場・内訳と話し合いをご覧ください。
→ 改葬費用の詳細は【改葬費用】お墓の引越しにかかる費用と相場をご覧ください。
4.宗教・宗派が異なる場合の対応
ご自身の宗教・宗派と異なる寺院墓地での埋葬が難しい場合、または最初から檀家になる意思がない場合は、以下の埋葬先を検討することになります。
(1)公営霊園
都道府県や市区町村などの自治体が運営する霊園です。
- 特徴:宗教・宗派を問わず利用できることがほとんどで、費用も比較的安価な傾向にあります。
- 注意点: 居住要件などの応募条件が厳しく、人気のある霊園では抽選となり競争率も高い場合があります。
(2)民営霊園
民間企業や宗教法人が運営する霊園です。
- 特徴:宗派の制約が少ない場所が多く、応募条件も比較的緩やかです。すぐに埋葬(改葬)できる場所が多いのもメリットです。
- 注意点: 公営霊園に比べ費用が高くなる傾向があり、霊園ごとの使用規則や供養形式が細かく定められている場合がありますので、契約前の確認が必須です。
(3)永代供養墓・樹木葬
主に民営霊園や寺院が提供する、新しい供養形式です。
- 特徴: 宗教・宗派不問が一般的で、永代にわたる管理・供養を施設側が行うため、承継者がいなくても安心です。費用も一般的なお墓を建てるよりも安く済むことが多いです。
- 種類: 合祀型、集合型、個別型など多様な形式があります。
→ 永代供養墓の詳細は【永代供養墓】基礎知識・選び方をご覧ください。
→ 樹木葬の詳細は【樹木葬】基礎知識・選び方をご覧ください。
→ 納骨堂の詳細は【納骨堂とは】選び方・費用・注意点を解説をご覧ください。
(4)散骨
ご遺骨を粉末状にして海や山などの自然に還す供養方法です。
- 特徴:お墓を持たない選択肢であり、宗教・宗派を問わず行えます。費用も他の供養方法に比べて安価に抑えられます。
- 注意点:お墓参りをする場所がなくなるため、寂しさを感じる方もいます。また、親族の中に宗教的な儀式を重んじる方がいる場合、散骨に反対されることもあります。必ず家族・親族間で十分に話し合い、合意を得てから検討しましょう。
→ 散骨の詳細は【散骨】相談・手続代行をご覧ください。
まとめ:檀家以外の墓地承継は事前の準備が鍵

過去の通達や判例を見ると、檀家ではないことだけを理由に埋葬を拒否することは原則として認められないと解釈できます。しかし、現実には寺院の典礼に従うか否かでトラブルになるケースも少なくありません。
不幸があった際、
- 寺院からの拒否について争うのか?
- 寺院の典礼に従い、そのまま埋葬するのか?
- 宗派が違うので別の霊園等に埋葬し、承継する寺院墓地は墓じまいするのか?
といった選択を迫られることになります。
寺院との関係がこじれてしまうと、精神的な負担も大きくなります。そのため、ご自身の宗教・宗派が異なる寺院墓地を承継する場合は、事前の情報収集と、ご家族・ご親族、そして寺院との丁寧な話し合いが何よりも重要です。
もし、現在の寺院墓地がご自身の希望に合わない場合は、早めに墓じまいを行い、ご自身やご家族が納得できる新しい供養先へ改葬することも、後悔しないための賢明な選択と言えるでしょう。
→ 墓じまい・離檀で揉めないポイントの詳細は【墓じまい・離檀】最初の相談で揉めないポイントをご覧ください。

大塚法務行政書士事務所は、平成21年度(2009年)の開業以来、数多くの墓じまいや改葬手続き、遺言作成サポート、相続のご相談・手続き代行など、お墓に関する多岐にわたる業務を手掛けてまいりました。
豊富な実務経験と専門知識に基づき、法的な手続きだけでなく、ご家族間の調整や具体的な選択肢の検討まで、幅広い視点から親身にアドバイスさせていただきます。
お墓に関するご不明な点やご不安なことがございましたら、まずは下記の無料相談窓口よりお問い合わせください。お客様一人ひとりに寄り添い、最適な解決策を見つけるお手伝いをいたします。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)



























