

 大切なご家族が亡くなった際、供養の一環として必要になるものの一つが「お位牌」です。お位牌には、故人の戒名や没年月日が記されており、ご家族が故人を偲び、供養するための重要な仏具となります。
大切なご家族が亡くなった際、供養の一環として必要になるものの一つが「お位牌」です。お位牌には、故人の戒名や没年月日が記されており、ご家族が故人を偲び、供養するための重要な仏具となります。
また、戒名は仏教の教えに基づいて授けられるものであり、故人が仏の弟子となる証ともいえます。しかし、お位牌や戒名についての知識がないと、どのように準備すればよいのか分からないことも多いでしょう。
この記事では、お位牌や戒名の基本的な役割や種類、選び方、必要性などについて詳しく解説していきます。供養の準備をする際の参考になれば幸いです。
→ 戒名が不要な場合の注意点について詳しく知りたい方は【戒名なし】葬儀・埋葬は可能?費用と手続き を解説をご覧ください。
1.お位牌とは?
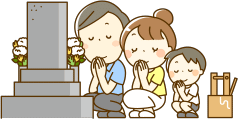 お位牌とは、亡くなった方の「仏名、没年月日、俗名、没年齢が記された木牌の仏具」です。お仏壇は、ご先祖様の霊がこの世に帰ってきた時の仮住まいであり、お位牌は、ご先祖様や故人の霊が宿る依代(よりしろ)と言えます。
お位牌とは、亡くなった方の「仏名、没年月日、俗名、没年齢が記された木牌の仏具」です。お仏壇は、ご先祖様の霊がこの世に帰ってきた時の仮住まいであり、お位牌は、ご先祖様や故人の霊が宿る依代(よりしろ)と言えます。
そのため、浄土真宗を除いた宗派では、基本的にお位牌は必ず必要となります。
(1)お位牌の種類
お位牌には、以下のような種類があります。
- 白木の位牌(仮位牌):亡くなってから四十九日の忌明けまで祭壇に祀る位牌です。
- 本位牌:漆塗りの「漆位牌」や、黒檀・紫檀で作られた「唐木位牌」などがあります。
- 寺位牌:寺院や寺院位牌堂に安置するために作られる位牌です。
(2)白木の位牌と本位牌について
白木の位牌は仮の位牌であり、四十九日の忌明けをもって菩提寺に納められ供養・お焚き上げされます。そのため、喪中の間に本位牌を仏具店で購入しておく必要があります。本位牌は、忌明けの法要の際に「入魂供養」を行ってもらい、供養後の忌明けに仏壇に安置します。
(3)お位牌の選び方
お位牌は長期に渡り仏壇に安置するものです。なるべく耐久性の高い木材を使用したもの(黒檀、紫檀など。)を選ぶ方が良いかと思います。位牌の大きさは、仏壇のサイズに合わせる必要があります。(近年、コンパクトな仏壇を選ぶ方も多くなっておりますので、仏壇の大きさも考えた上で、選ぶようにしましょう。)
(4)古くなった位牌の処分
古くなった位牌を処分する場合、一般的には魂抜きを行いお焚き上げします。石材店や仏具店などでは、位牌の処分を引受けている場合もありますので、処分をお考えの場合は、店舗に確認してみて下さい。(店舗によっては供養を行った位牌のみを引受ける場合もあります。)
2.戒名とは?

戒名は仏教において、仏の弟子としての証となる名前です。浄土真宗では「法名」、日蓮宗では「法号」と呼ばれます。元来の意味は、仏教者として守るべき生活や心の規範を受けた人に与えられる名前でした。
一般的には、人が亡くなった際に戒名料を納め、菩提寺や葬儀を執り行って頂いた、ご住職から頂く名前とも言えます。
(1)戒名を授かる時期
本来、戒名は生前に授かるものでしたが、現在では亡くなった際に授かることが一般的です。仏教では、俗名(生前の名前)のままでは仏の世界に行けないと考えられているため、死後に戒名を授け、故人を浄土へと導きます。
(2)戒名を付けてもらう際に伝える情報
故人の生前の人柄を反映した戒名をいただくために、住職には以下の情報などを伝えると良いでしょう。
- 故人の生前の名前(俗名)
- 故人の性別
- 故人の没年月日
- 故人の経歴や生前の社会的立場
- 希望する戒名(希望する名前の要素がある場合)
故人の名前の一文字を入れたり、故人をよく知る住職であれば、その人柄をふまえた戒名をつけてくださいます。例えば、昭和の歌姫、美空ひばりさんの戒名は「唱院美空日和清大姉」です。
(3)戒名の構成
戒名は一般的に四つの要素から成り立っています。
戒名の最初に付けられる称号です。社会的貢献度や寺院への貢献度が高い人に付けられます。
仏門を極めた人に付けられるもので、故人の人格や生前の活動を表す部分です。
本来の戒名はこの部分です。故人の俗名(人柄)や経文・自然に関する文字などの1文字をとり2文字で付けるのが一般的です。
仏教に帰依した人の尊称で故人の性別や身分によって付けられるます。また亡くなった年齢により位号が定められます。
- 信仰心が深い人:居士(男)、大姉(女)
- 出家せずに仏道を納めた人:信士(男)・信女(女)
- 7歳~15歳:童子(男)・童女(女)
- 2歳~3歳:孩子(男)・孩女(女)
(4)実際の構成例
実際には下記の様な戒名となります。
◇◇院〔院号)〇〇◆◆(道号・戒名)居士・大姉(位号)
◆◆(戒名)信士・信女
◆◆(戒名)童子・童女(孩子・孩女)
(5)生前戒名
近年では「生前戒名」を受ける方も増えています。これは、死後の手続きを簡略化するだけでなく、仏教徒としての人生を意識する目的もあります。
3.お位牌とお性根入れ

お墓、お仏壇、お位牌も買ってきただけでは、ただの石や木の置物です。お性根入れ(開眼供養・開眼法要・御魂入れ・御霊入れ)とは、これらのオブジェに魂を宿らせる儀式です。魂を宿らせることで、礼拝をする対象であるお墓・お仏壇・お位牌へと生まれ変わります。
お性根入れは、基本的に菩提寺のご住職による読経を行ってもらいます。
通常、お墓やお仏壇・お位牌を購入する際に、販売店からお性根入れについて説明がありますが、インターネットなどで購入した場合は説明がないことが多いため、ご自身で依頼先を確認する必要があります。
→ 開眼供養・閉眼供養の詳細は【開眼供養・閉眼供養】意味と進め方 を解説をご覧ください。
4.お位牌の価格と戒名料
(1)お位牌の価格
お位牌の相場は、それぞれの種類によってもちろん様々ですが、1~5万円くらいが相場になります。1万円以下のものもありますが、長年使用する事を考慮に入れて、また耐久性を重視すれば、1万円以下のものは避けたほうが良いと思います。
(2)戒名料
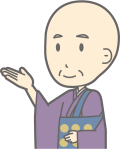
戒名料は、戒名の位の高さや宗派、寺院の格式によって異なります。
例えば・・
- ○○院××××居士・大姉・信士・信女の場合、70万円から100万円以上。
- ××××居士・大姉・信士・信女の場合、50万円から80万円。
- ××××信士・信女の場合、30万円から50万円です。
浄土真宗は、戒名の付け方が他宗派とは異なり、○院釋×は50万円以上、釋○○は10万円から30万円が相場のようです。
これらの金額はあくまで目安であり、事前に菩提寺に確認することが大切です。
5.お位牌と戒名の必要性
(1)お位牌の必要性
お位牌は、仏教の発祥地であるインドには元々なく、中国儒教の習慣が日本に伝わったものです。そのため、厳密には「必ず作らなければならない」ものではありませんが、故人の魂が宿る依代として、残されたご家族の心のよりどころとなります。
(2)戒名の必要性
菩提寺があり、仏式で葬儀や法要を行う場合は、戒名が必要となります。無宗教や故人の意思によっては戒名を授からない場合もありますが、日本では故人の魂が迷わずに浄土へ行けるよう、戒名が必要という考え方が広く根付いています。
お位牌や戒名について悩んだ場合は、後々のトラブルを防ぐためにも、ご家族や菩提寺のご住職とよく話し合うことが重要です。
→ 戒名が不要な場合の注意点について詳しく知りたい方は【戒名なし】葬儀・埋葬は可能?費用と手続き を解説をご覧ください。
6.まとめ

様々な社会生活の変化などにより、お墓事情も変化をしています。少子化、高齢化、核家族など、お墓を継承していく事が難しい、また子供たちにお墓継承の苦労を掛けたくないと本人が永代供養や散骨を望むことも増えています。
しかしながら、やはり、大切な家族が亡くなったら、無事に極楽浄土へ旅立ち、そして魂が宿る依代であるお位牌に手を合わせ、故人を思い出すとともに、ご先祖様への感謝を伝えたり、精神的に支えてもらうと言う考え方をする日本人は、未だ多く存在すると思います。
お位牌・戒名は、もちろん故人のためのものでありますが、残された家族の心のよりどころであり、悲しみを乗り越えて前向きに生きて行くためにも必要性はあると思わずにはいられません。
大塚法務行政書士事務所は、平成21年度(2009年)の開業以来、数多くの墓じまいや改葬手続き、遺言作成サポート、相続のご相談・手続き代行など、お墓に関する多岐にわたる業務を手掛けてまいりました。
お墓に関するご不明な点やご不安なことがございましたら、まずは下記の無料相談窓口よりお問い合わせください。お客様一人ひとりに寄り添い、最適な解決策を見つけるお手伝いをいたします。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)


























