

 ・お墓を選ぶ際によく耳にする「永代使用権」と「永代供養」。
・お墓を選ぶ際によく耳にする「永代使用権」と「永代供養」。
どちらも「永代」という言葉がつくため混同されがちですが、その意味や内容は全く異なります。この違いを理解しないままお墓選びを進めてしまうと、後で「こんなはずではなかった」と後悔することにもなりかねません。
この記事では、お墓の専門家である行政書士が「永代使用権」と「永代供養」それぞれの定義、費用、承継の必要性、そしてそれぞれの墓地の特徴や選び方までを分かりやすく徹底解説いたします。
初めてお墓を検討する方にも役立つ内容になっていますので、ぜひご参考にしてください。
1.永代使用権と永代供養の違いとは?
「永代使用権」と「永代供養」は言葉が似ているため混同されやすいですが、その本質は大きく異なります。それぞれの定義を理解することで、お墓選びの選択肢が明確になります。
(1)永代使用権の定義

お墓を建てる」「お墓を買う」という言葉がよく使われますが、実際にお墓を建てる土地は、通常「墓地使用権」を得ることであり、土地の「所有権」を得ることにはなりません(永代使用権を得た土地の区画上に建立されたお墓の石材部分には所有権があります)。
つまり、**「永代にわたりお墓を建てる土地を使用できる権利」**を得るという意味になります。永代使用権の権利については特に法律で明記されているわけではなく、内容や義務・制限等は契約により決定します。
通常、墓地購入後、毎年維持管理料を支払うことになりますが、支払いが滞ると永代使用権が一定の期間後に消滅する場合がありますので、細かく内容を確認しておく必要があります。
なお、永代使用権は承継者がいる限り代々引き継げますが、第三者に譲渡することは通常できず、承継者がいない場合、権利は消滅することになります。
(2)永代供養の定義
ご遺骨が永代にわたり供養(管理・埋葬)されることを言います。永代供養墓などでは、墓地管理者(寺院や霊園)が建立した墓地に遺骨を埋葬し、その遺骨を永代にわたり供養してもらうことになります。あくまでも遺骨管理の委託契約になりますので、永代供養墓等の所有権は通常ありません(例外はあります)。
「永代」と聞くと永久をイメージするかもしれませんが、実際には一定の契約期間(13回忌、33回忌など)が設定されていることが多く、期間満了後は合祀墓に移されるのが一般的です。
(3)永代使用権と永代供養の比較
以下の表で、両者の主な違いを比較します。
| 項目 | 永代使用権 | 永代供養 |
|---|---|---|
| 対象 | 墓地(土地)の使用権利 | 遺骨の供養と管理サービス |
| 所有権 | なし(土地の所有権は得られない) | なし(遺骨の管理委託) |
| 費用 | 永代使用料+毎年維持管理費が発生 | 初期費用一括払いが多い(管理費不要) |
| 承継者 | 必要(いないと権利消滅の可能性) | 不要(管理者が供養・管理を行う) |
| 遺骨の扱い | 原則として個別墓に埋葬、自由に供養 | 合祀されることが多い(期間後) |
| 墓石 | 個別に建立することが多い | 形式による(共同墓、納骨堂など様々) |
2.永代使用権の墓地の特徴とメリット・デメリット
永代使用権を購入できる墓地は、寺院墓地、公営墓地、民営墓地など様々です。ここでは、伝統的なお墓を建立する際に得る永代使用権の墓地について解説します。
(1)永代使用権で利用する墓地の形式
永代使用権で購入する墓地は、基本的に区画単位で利用し、その上に伝統的なお墓(和型、洋型など)を建てる形になります。永代使用権を購入した場合、その墓地は原則として永代にわたり使用できますが、土地そのものの権利を取得するわけではなく、あくまで使用権のみが与えられます。
(2)永代使用権購入のメリット
- お墓の継承:お墓を代々承継することが可能となり、将来お墓を探す心配がありません。
- 伝統的な供養:従来のお墓を建てるため、家族の歴史を刻む場所としての意味合いが強く、伝統的な供養を重視する方に適しています。
- デザインの自由度: 個別にお墓を建立するため、墓石のデザインにこだわりたい方に適しています。
- 管理清掃の安心感:寺院や民営墓地の場合、お墓の管理清掃が行われることが多く、安心して埋葬ができます。
(3)永代使用権購入のデメリット
- 承継者問題:永代使用権購入後に墓地の承継者がいない場合は、無縁墓になる可能性があります。
- 費用負担:墓地の維持管理費が毎年発生し、支払いが滞ると永代使用権が消滅する場合があります。
- 都心部での高額化:都市部では土地が限られているため、永代使用料が高額になる傾向があります。
- 転売不可:永代使用権は第三者に譲渡することができません。
(4)永代使用権購入時に確認すべきポイント
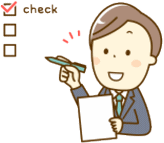
永代使用権を購入する場合は、契約書、使用規則等の条件をよく確認しておく必要があります。使用権の期間、承継者がいない場合の対応、維持管理費の支払い方法、永代使用権の消滅条件など、契約を行う前に条件等を理解しておくことが大切です。
永代使用権は、基本的に墓地承継者がいることを前提に契約します。もし承継者がいない場合、墓地を管理するための代替案(永代供養墓に改葬するなど)を考えておく必要があります。承継者がいなくなる可能性も考慮し、将来的な対応方法を墓地管理者に相談しておくと安心です。
墓地購入した場合、通常、管理費や維持費が定期的に発生します。この費用は墓地の清掃や草刈りなどお墓の保守管理に使用されます。契約時に維持管理費の金額、使用内容なども確認しておきましょう。
お墓を訪れる際の交通アクセスも重要な要素です。遠方の墓地を選んだ場合、将来、遠くに住む家族が訪れるのが不便になる可能性があります。特に高齢の家族がいる場合は、アクセスの良さを重視することが望ましいです。
永代使用権の購入を決める前に、墓地の清潔さや管理状態を現地で確認することが重要です。定期的に手入れが行われているか、墓地内の設備が整っているかをチェックし、安心して使用できるかを確認しましょう。
3. 永代供養墓地の特徴とメリット・デメリット
永代供養墓は、主に承継者がいない方や、代々に渡り墓地を管理することが難しい方を対象にした供養方法です。墓地を購入するのではなく、遺骨の供養を依頼する形になります。
(1)永代供養で利用する墓地の形式
永代供養墓は、寺院や霊園が運営し、埋葬後、管理者が代わりに供養を行い、無縁になることを防ぎます。これにより、後継者の問題が解消され、安定した供養を受けることができます。永代供養墓には、以下のような様々な形式があります。
- 合祀墓(共同墓):他の遺骨と一緒に埋葬される形式。最も費用が安価。
- 集合墓・集合個別墓:一定期間個別に安置後、合祀される形式。
- 個別墓:一定期間個別のスペースで供養後、合祀される形式。
- 樹木葬:樹木を墓標とする自然志向の形式。
- 納骨堂:屋内施設に遺骨を安置する形式。都市部に多い。
- 公営永代供養墓: 自治体が運営し、比較的安価だが条件がある場合が多い。
・詳細な永代供養墓の種類と費用相場については、【永代供養墓】基礎知識・選び方をご覧ください。
(2)永代供養墓地のメリット
- 承継者不要:後継ぎがいなくても供養が継続されます。
- 管理負担がない: 寺院や霊園が管理・供養を行うため、遺族の清掃や管理の手間が不要です。
- 費用が明確:初期費用を一括で支払うことが多く、その後の維持管理費が発生しない場合がほとんどです。
- 多様な選択肢: 納骨堂や樹木葬など様々なタイプがあり、個人の希望に合わせて選択可能です。
- 宗教・宗派不問: 多くの永代供養墓は、特定の宗教や宗派を問わず受け入れています。
(3)永代供養墓地のデメリット
- 遺骨の個別性が薄れる:合祀される場合や、一定期間後に合祀される場合、他の遺骨と一緒になることに抵抗があると感じる方もいます。一度合祀されると、後から遺骨を取り出すことはできません。
- 墓石の制限:従来のお墓と違い、墓石のデザインや設置場所に制限がある場合があります。
- 寺院との関係が希薄になる: 寺院が運営する永代供養墓でも、一般の檀家のような深い付き合いがなくなることが多いです。
(4)永代供養墓購入時に確認すべきポイント

永代供養墓の場合、契約期間経過後に遺骨が他の遺骨と一緒に埋葬されることがあります。合祀されるタイミングや方法について、事前に契約内容を確認し、不明点があれば墓地管理者に質問しておきましょう。
永代供養墓を選ぶ際のアクセスも重要です。遠方にある場合、特に高齢の家族が墓参りに行くのが困難になる可能性があります。交通の便が良い場所を選ぶことをお勧めします。
契約前に、管理費や供養料などの料金体系を確認しておくことが必要です。永代供養墓によっては、初期費用の他にも維持費用や年会費が発生する場合がありますので、しっかり把握しておきましょう。
永代供養墓を運営する寺院や霊園の信頼性も重要なポイントです。評判や過去の実績をインターネットで調べたり、口コミを参考にしたりすることをお勧めします。
永代供養墓の選び方としては、家族の状況や希望に合わせて選ぶことが大切です。もし将来的に承継者の問題が心配であれば、永代供養墓は非常に安心できる選択肢となるでしょう。
4. 永代使用権と永代供養、どちらを選ぶべき?【チェックリスト】
永代使用権の墓地を契約するか、永代供養の墓地と契約するか、どちらが良いかご自身の状況に応じて選択できるよう、チェックリストを掲載します。
(1)将来の承継者の有無を確認
将来、家族・親族等でお墓を承継していく人がいるかどうかを考えましょう。承継者がいる場合、どのようにお墓を引き継ぐか?について話し合い、意思・希望をしっかり伝えておくことが重要です。一方、承継者がいない場合は、永代供養墓などの選択肢を検討することが安心につながります。
(2)費用や維持管理の負担を確認する
購入時の費用やその後の維持管理費について、予算に合った選択肢を検討しましょう。永代使用権の場合、年間の管理費が発生するため、長期的に支払いが可能かを確認しておくことが大切です。永代供養墓の場合は、初期費用に加えて供養費が必要なケースがあるため、契約内容をよく確認しましょう。
(3)立地やアクセスの良さを考える
お墓を訪れる際の交通の便や距離も重要な要素です。遠方の地域にお墓を選んだ場合、実際に足を運ぶのが難しくなることも考慮する必要があります。特に高齢の家族がいる場合や将来の状況を見据えると、アクセスの良い場所を選ぶのが望ましいでしょう。
5. 永代使用権と永代供養の未来の形
近年、社会や文化の変化に伴い、伝統的な墓地の考え方も大きく変わりつつあります。永代使用権と永代供養の選択肢は、今後どのように変化していくか考えていきましょう。
(1)永代使用権の未来
永代使用権は、墓地区画を使い続ける権利を得ることにより、代々に渡ってお墓を継承していくことが可能な制度です。しかし、人口減少や核家族化の進行などが影響し、今後の永代使用権にも様々な変化が見込まれます。
①少子化と承継者の問題
日本では少子化が進行しており、子供がいない家庭や親族が少ない場合、永代使用権を維持することが難しくなる可能性があります。この問題に対処するため、墓地管理者は、承継者がいない墓の管理を続ける方法を提案し始めています。
例えば、永代供養のオプションを組み込むことで、永代使用権と供養の両方を提供するなど、現在でもこのような方法で一部行われていますが、今後ますます増加していくものと考えられます。これは霊園のみならず、寺院墓地も将来的に主流になっていく可能性があります。
②都市部での土地不足と高額化
都市部では土地が限られているため、永代使用権の取得が非常に高額になる可能性があります。現在でも都心の一等地では永代使用権が1千万円を超える墓地もあります。
このような墓地は、将来的にも高級なブランド墓地として運営されていくことになり、一方、地方では永代使用権が無料の墓地もあり、今後、低価格な墓地と高級な墓地とでさらに二極化していくことが考えられます。
③お墓のデジタル管理化
お墓の状態をスマートフォンやパソコンで確認できるようになることで、お墓の維持管理が行いやすくなります。遠方の場合も、ご自身のお墓を画面上で確認でき、お参りも可能であれば、さらに利便性も向上します。
このような状態が普及すれば、永代使用権を取得しご自身のお墓を持ちたいという方も増えるのではないでしょうか。
(2)永代供養の未来
永代供養は、承継者がいない場合や、代々に渡ってお墓の管理が難しい場合に選ばれる供養方法です。近年では、永代供養がより一般的になりつつあり、今後もその需要は増加すると予想されます。
①高齢化社会と永代供養の需要増
日本は急速に高齢化が進んでおり、特に高齢者が増えている現状では、承継者がいない場合に永代供養が選ばれるケースが増加しています。例えば、納骨堂や樹木葬などの選択肢は、従来のお墓に比べて管理が容易で、承継者がいなくても問題ありません。
将来的には、永代供養墓地の種類がさらに多様化し、遺族の希望に合わせた選択肢がさらに増えることが予想されます。
②文化の変化と永代供養の進化
近年、樹木葬、海洋散骨など、従来の墓地形式にとらわれない供養方法が増加しています。このような供養方法は、自然環境や墓地に対する意識の変化によって選ばれるようになりました。
永代供養の形式もこの流れを受けて進化し、より環境に優しい方法や、より個人の好みに応じた、新しい供養スタイルもこれから登場していくものと思われます。
③デジタル化と永代供養の広がり
永代供養墓の分野でもデジタル化が進むと予想されます。例えば、仏壇の代わりにデジタルメモリアルが設置されるケースが増え、供養の様子を家族がオンラインで確認できるようになるかもしれません。
さらに、AIを活用して、故人に関する情報を管理し、個別に最適な供養方法を提案するサービスも登場する可能性があります。
(3) 未来の選択肢としての融合
未来の墓地制度では、永代使用権と永代供養の融合がより進む可能性があります。たとえば、永代使用権を持っている場合でも、承継者がいない場合には、永代供養墓とするなど、承継者が途切れた場合も困らないような仕組みを提供することで、どちらのニーズにも対応できるようになります。
これにより、柔軟で多様な選択肢が提供され、家族の状況に合わせた供養方法が選べるようになるでしょう。
(4)結論
永代使用権と永代供養は、今後の社会の変化に合わせて進化し、より柔軟で便利な供養の選択肢を提供していくものと思われます。少子化や高齢化、そして都市化が進む中で、これらのシステムがどのように変化するのかに注目し、将来のニーズに合わせた供養方法を選ぶことが重要です。
将来的には、技術革新や文化の変化によって、これまでにない新しい供養の形が誕生するかもしれません。
4.永代使用権と永代供養の違い まとめ

永代使用権と永代供養の違い等について、まとめさせて頂きました。永代使用権とは、どのようなものか?どのような権利があるのか?等のご質問や永代供養についてのお墓の悩みなどもご相談頂くことがあるため、ここで詳しく解説させて頂きました。
当事務所は、お墓の手続きを専門として10年以上の経験がある行政書士事務所になります。お墓の手続きに関するご相談や手続代行のご依頼を頂いております。
もしお墓のことで分からないことがありましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。お墓に関するアドバイスから手続代行まで幅広い範囲でサポートさせて頂きます。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)



























