


法要(法事)は、故人の冥福を祈り、その魂を供養するための重要な仏教儀式です。特に、故人が無事に極楽浄土に往生できるよう祈る「追善供養」には、遺族が故人との繋がりを再確認し、心の整理をつけるための大切な意味合いも含まれています。
この記事では、法要の基本的な目的や意味、初七日から年忌法要までの時期と種類、法要の準備から当日の進行の流れ、参列する際の服装マナーまで、法要に関する基礎知識を網羅的に解説します。これから法要を執り行う方、あるいは参列される方のために、ぜひご参考にしてください。
1.法要とは?供養の目的と意味
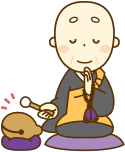
法要とは、故人の霊を供養し、安らかな成仏を願う儀式です。法事や追善供養とも呼ばれています。この法要を行うことで故人は無事に極楽浄土に往生することができるとされています。
また法要を行うことは、故人との繋がりを深める儀式として、遺族の心の整理もつけられるように行われます。
仏教では、死者が成仏するには段階を経るとされ、そのため法要は、その過程において重要な意味を持つとされています、特に重要なのは「初七日」や「四十九日」といった最初の回忌法要になります。
2.法要の時期と種類(初七日~四十九日)
仏教では、死後7週間(中陰)は、あの世とこの世を死者がさまよっているとされ、そのため初七日を始めとし7日ごとに7回の法要が行われます。
(1)初七日(しょなぬか)
亡くなった日から7日目に行われる法要す。故人があの世にへ向うための準備が整うように祈ります。仏教では7日ごと霊が進むとされており、その始めである初七日は重要な意味をもちます。
現代では、葬儀当日に火葬後、初七日法要を繰り上げて行うことが一般的です。
(2)初七日~四十九日までの法要
初七日以降も7日ごとに法要が行われますが、現在は省略されることが多く、遺族のみで供養を行うことが一般的です。
- 二十七日(ふたなぬか)死後14日目
- 三十七日(みなぬか)死後21日目
- 四十七日(よなぬか)死後28日目
- 五十七日(いつなぬか)死後35日目
- 六十七日(むなぬか)死後42日目
この法要は、僧侶と遺族の少人数で行われますが、僧侶を呼ばずに遺族だけで行われる方も多くおります。
(3)四十九日
七十七日が(なななぬか)四十九日になります。四十九日は「満中陰」とも呼ばれ、あの世に向かう死者の運命が決まる日とされています。このため、四十九日法要は重要であり、仏教の中でも大きな節目とされています。この四十九日法要をもって喪明けとなります。
寺院で行われることが一般的です。僧侶に読経してもらい故人の成仏を願います。供物として、お花や食べ物を準備し、法要後に親族があつまり食事会が行われます。お墓をもっている方は、この日に納骨される方が多くなっております。
→ 納骨の時期や手順の詳細は【納骨の基礎知識】時期・場所・手順 を解説をご覧ください。
3.月忌法要と年忌法要の時期・種類
(1)月忌法要
故人の命日に毎月行う供養で、「月命日」とも呼ばれます。故人を偲び、その霊を慰めるための行事で、ご家族が仏壇に手を合わせる機会になります。
(2)年忌法要
故人の命日の同月同日を「祥月(しょうつき)命日」といいます。年忌法要は、この祥月命日に行われます。
- 一周忌(いっしゅうき):死後1年目(満1年)
- 三回忌(さんかいき):死亡年を含め3年目(満2年)
- 七回忌(しちかいき):死亡年を含め7年目(満6年)
- 十三回忌(じゅうさんかいき):死亡年を含め13年目(満12年)
- 十七回忌(じゅうしちかいき):死亡年を含め17年目(満16年)
- 二十三回忌(にじゅうさんかいき):死亡年を含め23年目(満22年)
- 三十三回忌(さんじゅうさんかいき):死亡を含め33年目(満32年)
- 五十回忌(ごじゅっかいき):死亡年を含めて55年目(満54年)
- 百回忌(ひゃっかいき):死亡年を含め100年目(満99年)
一周忌と三回忌は盛大に行われ、七回忌以降は規模を縮小し内輪で行われます。一般的には、三十三回忌で弔い上げとして最後の法要にする方が多くなります。
4.法要までの流れ(準備)
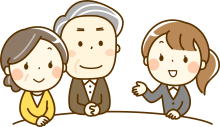
一周忌、三回忌は、規模の大きな法要になります。準備にも時間が掛かりますので、早めに計画をたて進めて行くことが大切です。ここでは、法要を行うまでの流れについて解説いたします。
(1)施主の決定と寺院への連絡
法要の主催者である「施主」を決め、故人の菩提寺に連絡して法要を依頼します。
(2)日時の決定(半年前~3ヶ月前)
ご住職の予定も事前に確認した上で日時を決めて下さい。年回忌は、祥月命日になりますが参列者の都合も考慮し土日に法要を行う方もおります。この日にちの変更は、命日よりも必ず前にすることが習わしになっています。
(3)会場・参列者の決定
法要は、菩提寺で行われることが一般的ですが、自宅、斎場やホテルなどで行われる方もおります。参列者の人数と予算に合せて会場を決める必要があります。但し、法要後に墓参りを行いますので、会場とお墓のある場所の行き易さも考えて決めましょう。
誰を招待するか、家族・親族と話し合って決めます。一周忌や三回忌は親族以外に友人・知人を招くことも多いです。
(4)案内状の送付(1ヶ月前~2週間前)
参列者が決まったら、日時、会場、会食の有無などを記載した案内状を送付します。様々な書き方がありますが、ここでは一例として下記に掲載します。
案内状(参考例)
謹啓
桜の便りが聞かれる頃となり、春の暖かな陽射しに心も和らぐ季節となりました。皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、このたび故〇〇〇〇 の 〇回忌法要を下記のとおり執り行いたく存じます。
生前の故人には格別のご厚誼を賜り、皆様に支えられたことに深く感謝申し上げます。つきましては、節目の供養を共にしていただければ幸いに存じます。
ご多忙な中まことに恐縮ではございますが、ぜひご参列賜りますようお願い申し上げます。なお、ご出席いただけます場合は、〇月〇日までに同封のはがきでお知らせくださいますようお願い申し上げます。
敬具
記
日時:令和〇年〇月〇日(〇曜日)〇時より
場所:〇〇寺院・東京都〇〇〇〇〇・・・
電話番号:〇〇(〇〇〇〇)〇〇〇〇
令和〇年〇月〇日
施主〇〇 〇〇
(5)引き物・料理の手配
引き物は、参列者への手土産にするものです。参列者の人数が決まった段階で用意する様にします。表書は「粗供養」、「志」と記載し、施主の姓、故人の戒名、〇回忌を記載します。手土産にする品物は、海苔、お菓子、お茶、タオルなど、持ち帰りやすい品を用意します。基本的には1家族につき1つの引き物をお渡しします。
一周忌、三周忌などの大きな法要では、参列者をもてなす会食が行われます。この会食を「お斎(おとき)」と呼びます。仕出しを利用するか、料亭で行う場合は、あらかじめ予約しておく必要があります。このお斎は、本来、精進料理とされていましたが、近年では、あまりこだわらずに一般的な料理が提供されています。尚、お斎を省略する場合は、折り詰めとお酒を用意し、引き物と一緒に参列者にお渡しします。
(6)供物・お布施の準備
お花、お線香、故人の好物などの供物、そしてご住職へのお布施を用意します。お布施の目安は3万円~5万円程度になります。その他、ご住職に出向いて頂いた場合は、お車代もお渡しします。こちらの目安は、5千円~1万円程度になります。更にお斎をご住職が欠席する場合は、ご膳料(目安は1万円程度)をお渡しします。
(7)法要・会食の準備
当日、施主は参列者より早めに会場に行き、法要や会食の準備を行います。受付や引き物の配布、ご住職、参列者への接待など、施主を中心に事前に役割をきめておきましょう。
5.法要の進行
法要は下記の流れにより進められます。参考にご覧下さい。
① 遺族・参列者の入場・着席:遺族、参列者が最初に入場・着席し、僧侶の入場を待ちます。
② 僧侶の入場・着席:遺族・参列者は黙とうして僧侶を迎えます。
③ 施主の挨拶
④ 僧侶の読経
⑤ 遺族・参列者の焼香:僧侶の進行に従い、施主⇒遺族⇒参列者の順に焼香を行います。
⑥ 僧侶の法話
⑦ 施主の挨拶
⑧ お墓参り:僧侶、施主、参列者の全員でお墓参りを行います。
⑨ 会食場への移動・会食
⑩引き物の配布・解散
最後に施主が参列者に一言お礼を述べて解散となります。
6.法要の服装とマナー
(1)服装について

法要の服装に決まりはありませんが、三回忌までは正式な喪服を着用することが礼儀といえます。現代では、正式な喪服を着用する方は少なく、略喪服を選ぶ方が多くなっております。参列者の方も三回忌まで略喪服を着用します。
三回忌以降は、喪服ではなく地味目の平服を着用して問題有りませんが、施主・親族側が参列者より軽装では失礼にあたります。もし施主側が平服を着用する場合は、案内状に平服でお越しくださいと一言添えておきましょう。
略喪服の例(参考)
- 男性:黒のスーツ、または、紺、グレーのダークスーツ。白いワイシャツ。ネクタイ、靴下、靴は黒。
- 女性:黒、紺、グレーのアンサンブル・ワンピース。バックや靴は黒。
- 子供:制服があれば制服を着用。無い場合は黒、紺、グレーなどの地味な色の服を着用。
(2)お布施について
僧侶にご供養をして頂いた際に、お布施をお渡しします。お布施は和紙で包むか、白い封筒または市販の不祝儀袋に入れてお渡しします。表書きは筆で「お布施」と書くのが正式ですが筆ペンなどで書いても問題ありません。
(3)納骨法要について
納骨法要を執り行う場合、主催者は参列者へ感謝の気持ちを伝える簡単な挨拶をしましょう。
→ 納骨の基礎知識の詳細は【納骨の基礎知識】時期・場所・手順 を解説をご覧ください。
→ 開眼供養・閉眼供養の詳細は【開眼供養・閉眼供養】意味と進め方 を解説をご覧ください。
7.神道の追悼(霊前祭・霊祭)
神道では仏教の法要にあたるものとして、霊前際・霊祭を行います。葬儀の翌日に翌日際を行い、亡くなった日から十日後ごとに追悼の儀を行います。
- 翌日際(現在では省略する方が多い。)
- 十日祭(仏教の初七日にあたる)
- 二十日際、三十日際、四十日祭
- 五十日際(仏教の四十九日にあたる)
- 百日際(現在では省略する方が多い。)
(1)五十日際
五十日祭をもって忌明けになります。神道では重要な霊祭にあたり、親族・友人などを招き盛大に行われます。通常、墓前や自宅の霊前に供物を供え、神官の祭司奏上、玉串奉奠となります。さらに当日または翌日に清祓の儀を行います。
(2)式年祭
仏教での年忌法要にあたります。一年祭から二年、三年、五年祭となり、次は10年祭となります。50年祭までは10年ごとに、50年祭以降は、百年祭、二百年祭と続いて行きます。実際に儀式が行われるのは、五十年祭までになりますが、二十年祭までとすることが多い様です。なお、仏教のお斎と同じように祭式の後は「直会(なおらい」という食事会を開くことが一般的です。
8.キリスト教式の追悼
キリスト教の場合、仏教や神道のような決められた儀式はありませんが、実際には、日本の風習に合せて行う方も多い様です。
(1)カトリックの場合
カトリックでは、亡くなった日から三日目、七日目、三十日目に追悼ミサを行うことが一般的です。遺族、親族、友人などを招き協会でミサを行います。ミサ終了後には、「茶話会」で菓子や軽食を提供し参列者をもてなします。なお、一般的には、これ以降のミサは一年ごと行われています。
カトリックで11月を「死者の月」とされ、11月2日は万霊節になります。この万霊節では死者を弔うため特別なミサが教会で行われます。
(2)プロテスタントの場合
プロテスタントの場合、記念式をを行うことになります。死後一か月目の「昇天記念日」に記念式を行う方が多いようです。その後の4~5年目までは、毎年の昇天記念日に追悼の会も行うことが一般的です。
9.法要のQ&A
正式な喪服は、男性の場合、黒羽二重染め抜き五つ紋着、羽織、洋装は黒のモーニングなどになります。女性の場合は、染め抜き五つ紋の着物、洋装は黒のアフタヌーンドレスなどになります。
現代では、この様な服を用意されている方も少ないかと思います。ですので、基本的には、黒のスーツやワンピースなど地味目の服装であれば問題はないと思われます。年回忌が進むごとに地味目の平服でも問題ありません。
女性の場合、結婚指輪以外のアクセサリーは外して参列します。化粧や香水も控えめにします。バックも黒などの地味目の色を選び、爬虫類のものはタブーとされています。
男性の場合、白いワイシャツ以外は、全て黒色系のものを選択しておけば良いかと思います。ネクタイ、靴下、靴など。あまり汚れていては、失礼になります。なるべくクリーニングに出した綺麗なもので参列しましょう。
インターネットを検索するとあいさつ文例も沢山でてきますので、参考にするのも良いかと思います。但し、あまり長すぎるものは、参列者にも迷惑になります。
基本的には、①参列者へのお礼の言葉、②遺族の近況報告、③おもてなししたいという気持ち。この3点を盛り込み簡潔に挨拶する方が良いかと思います。
あくまでも、参列頂いた方へのお礼が中心になります。この言葉は、必ず伝えておくことが大切です。
現在では、法要も簡略化されてきています。大きな法要(四十九日、一周忌、三回忌)をお行い、後は、お墓参りや仏壇にお供えして供養する方も多いかと思います。
大切なこと、故人を偲ぶ気持ちです。あまり形式にとらわれることなく、親しい身内だけでおこなうことも良いのではないでしょうか。但し、親族からクレームが来ないように、法要をどの様に行うのか説明もしておきましょう。
菩提寺が特になく、お呼びする僧侶に心当たりがない場合は、石材店や霊園から紹介してもらうか、お坊さん紹介センターなどに依頼する方法もあります。
お坊さん紹介センターの場合、戒名を授けて貰うことも可能です。
これは、どの様に行うかで金額が異なります。身内でのみで行う場合、掛かる費用は、お布施、食事代となりますが、親族・友人知人などを招待して大規模に行うと、会場の使用料、お土産代、食事代なども掛かることになります。
どの規模で行うべきか、家族、親族で、よく話し合われた方が良いかと思います。
身内だけならまだしも、参列者をお招きする場合は、不手際がないように計画的に進める必要があります。
早目に、寺院に連絡し予定を確認した上で、法要の日程を決めて行きます。参列者の人数が把握出来たら、会場や会食の場も早めに予約しておきましょう。
当日は、お墓に供物を供え、僧侶への挨拶、参列者への挨拶など行うことが沢山ありますので、こちらも事前に準備した上で、時間に余裕を持っておこないましょう。
基本的には、浄土真宗以外の宗派では、卒塔婆を建てるしきたりがありますが、現在では省略される方も多いかと思います。(寺院によります。)
卒塔婆供養を行う場合は、予め寺院にお願いをしておきましょう、費用は一本3千円~5千円程度になります。
卒塔婆は、年忌法要以外のお盆、お彼岸など、いつ建てても問題ありません。また、一回の法要で一本という訳ではなく複数本建てることも可能です。
10.法要の基礎知識 まとめ

法要は、故人を供養するための大切な儀式ですが、その形式は時代とともに簡略化される傾向にあります。
大切なことは、盛大な法要を行うことではなく、故人を偲ぶ気持ちです。この記事で解説した法要の基礎知識を参考に、ご家族・ご親族とよく話し合い、故人を想う気持ちを形にできる、納得のいく供養の仕方を選んでください。
大塚法務行政書士事務所は、平成21年度(2009年)の開業以来、数多くの墓じまいや改葬手続き、遺言作成サポート、相続のご相談・手続き代行など、お墓に関する多岐にわたる業務を手掛けてまいりました。豊富な実務経験と専門知識に基づき、法的な手続きだけでなく、具体的な選択肢の検討まで、幅広い視点から親身にアドバイスさせていただきます。
お墓に関するご不明な点やご不安なことがございましたら、まずは下記の無料相談窓口よりお問い合わせください。お客様一人ひとりに寄り添い、最適な解決策を見つけるお手伝いをいたします。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)



























