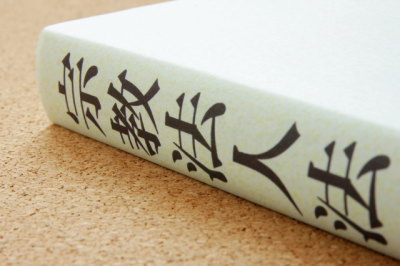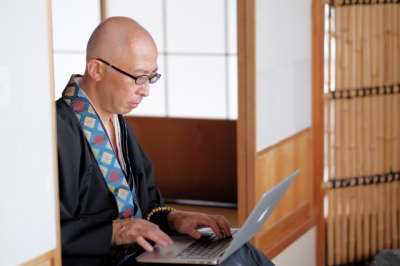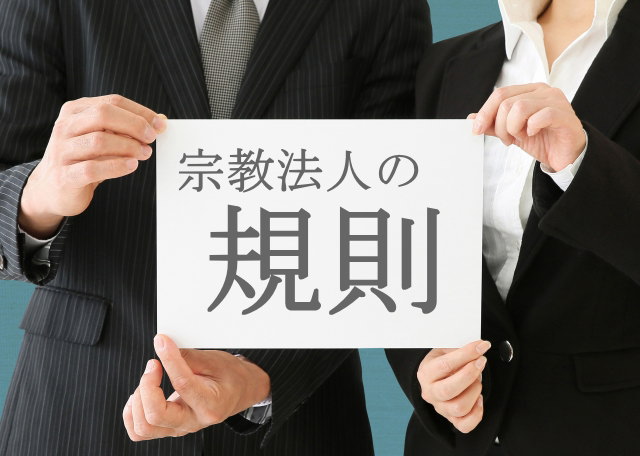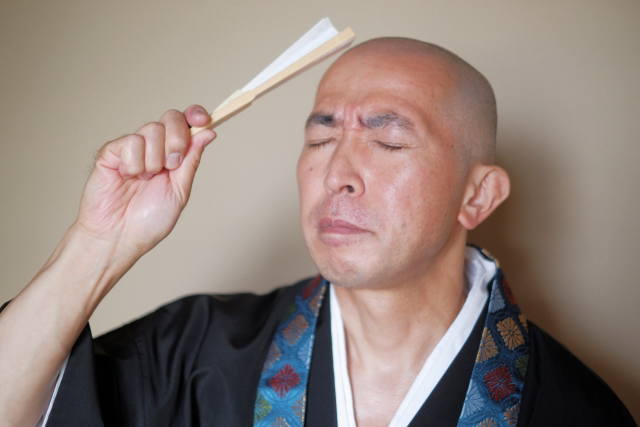墓地を円滑に運営していく上で、「墓地使用規則」は欠かせないものです。しかし、何を書けばいいのか、どこまで詳細に定めるべきかと悩む墓地管理者の方も少なくありません。この記事では、厚生労働省から通知されている「墓地経営・管理等の指針について」を参考に、墓地使用規則(契約約款)の作成ポイントを解説します。具体的なひな形を提示しながら、各条文の意図や注意点を詳しく説明。これを読めば、寺院・霊園の安定的な運営と、利用者との信頼関係を築くための第一歩を踏み出せるでしょう。1. 墓地使用規則(契約約款)とは?なぜ作成・整備が必要なのか(1)法的根拠と寺院運営における重要性墓地使用規則は、寺院や霊園と墓地使用者との間で交わされる契約の内容を定めたものであり、民法上の契約約款にあたります。厚生労働省の「墓地経営・管理等の指針について」という通知でも、契約の明確化を図る観点から、その作成が推奨されています。この規則を整備しておくことは、墓地の適正な管理運営を行う上で不可欠です。(2)規則がないことで発生するトラブル墓地使用規則が曖昧であったり、書面化されていない場合、以下のようなトラブルが発生しやすくなります。管理料の滞納に対する対応が不明確になる。承継手続きのルールがなく、使用者の代替わりで混乱が生じる。墓じまいや返還時の手続きや費用負担で揉める。墓石の大きさやデザインに関するルールがなく、景観が乱れる。明確な規則を定めておくことで、これらのトラブルを未然に防ぎ、関係者全員が安心して墓地を利用できるようになります。2. 厚生労働省の指針に基づく「墓地使用規則」のひな形と解説厚生労働省の指針において、表題は「墓地使用契約約款」または「使用契約書」とすることが望ましいとされています。(墓地使用規則という名称になっている場合が多いですが、実際には契約約款であるため、このような表題にすることが適切であろうと述べられています。)第1条 目的(目的)第1条 本定款は財団法人〇〇〔宗教法人△△〕が経営する墓地(以下「墓地」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定め、その使用及び管理が適切に行われることを目的とする。解説)この条文では、何のために規則が定められているのかを明確にすることが重要です。また、墓地使用契約は双務契約であるため、使用者に一方的に義務を課すような規定は好ましくないとされています。第2条 墓地の使用(墓地使用)第2条 使用者は、次に掲げる墓地の区画(以下「墓所」という。)を契約成立後〇年間〔第8条又は第9条の規定により契約が解除されない限り、継続して〕使用する権利を有する。使用墓所2 使用者は、経営者に届け出て、墓所内に使用者の親族及び縁故者の焼骨を埋蔵することができる。3 使用者は、墳墓の設置、焼骨の埋蔵その他墓地本来の使用目的以外の目的のために墓所を使用してはならない。4 使用者は、経営者の承諾を得ずに墓所の使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該墓所を使用させてはならない。解説)使用者の義務だけでなく、権利も明記することで使用者保護の観点から規定を設けるべきであるとされています。墓地使用期間については「永代」とされている場合が多いですが、管理料の不払い等が発生すれば契約解除が想定されるため、「契約が解除されない限り継続して」という表現が適切です。具体的な有効期間を設け、契約更新を行う制度は、無縁化した墓地の円滑な整理を考慮した場合、今後の墓地契約の1つの形となり得るとも記載されています。第3条 使用料(使用料)第3条 使用者は、経営者が定める期日までに使用料〇円を支払わなければならない。解説)使用料と管理料を個別に規定し、墓地使用料が墓地の場所を使用するための対価であることを明確にします。これにより、使用料不払い時に経営者による解除要件を適用しやすくなります。第4条 墓所の管理(墓所の管理)第4条 墓所の清掃、除草等については、当該墓所の使用者がその責任を負う。2 墓所の環境整備その他の管理(前項にきてするものを除く。)については、経営者がその責任を負う。解説)墓地の管理について責任の範囲を明確に記載します。墓所の清掃等以外の責任は経営者が負うこととし、後述する管理料の根拠となります。近年、地震や台風などの自然災害が増加しているため、不可抗力に対する経営者の免責事項も定めておくことが必須となります。第5条 管理料(管理料)第5条 経営者は、前条第2項に要する費用に充てるため、別に定めるところにより使用者に対して毎年管理料を請求するものとし、使用者はこれを支払わなければならない。2 経営者は物価の変動等により、当該時点における管理料によっては前項に規定する費用を賄うことができなくなったとき、又はその確実な見込が生じたときは、必要かつ相当と認められる範囲内において、管理料を改定することができる。この場合において、経営者は改定後の額及び改定の具体的な理由を明記して、使用者に対し、事前に書面により通知するものとする。解説)管理料の使途を明確にせず使用者に支払義務を課すことは妥当ではありません。何のために管理料を取るのかを明確にする必要があります。管理料の一括払いは柔軟な対応が困難であることから望ましくないとされ、使用者の所在を把握する上でも毎年の管理料を請求する方式が規定されました。管理料改定の際には、改定後の額と具体的な理由を書面で通知することも重要です。第6条 契約の更新(契約の更新)第6条 墓所を使用する権利を有する期間を経過した後も継続して墓所を使用しようとする者は、当該期間が経過する〇年前から、経営者に対して契約更新の申込をすることでができる。2 前項の申込があった場合おいて、前条第1項に規定する管理料の支払義務が履行されている場合には、経営者は前項の申込を承諾しなければならない。解説)これは墓地使用期間が定められている場合の規定です。(契約が解除されない限り使用できるとした場合は不要。)墓地使用契約の有期限更新制は、これからの墓地のあり方の1つのモデルとして提示されています。第7条 使用者の地位の承継(使用者の地位の承継)第7条 使用者の死亡により、使用者の祭祀承継者がその地位を承継して墓所の使用を継続する場合には、当該祭祀承継者は、すみやかに別記様式による地位承継届出書に住民票の写しを添えて経営者に届出を行う者とする。2 使用者の祭祀承継者が墓所の使用を継続しない場合には、書面をもって経営者にその旨を届け出るものとする。解説)墓地使用権は、祭祀承継者に承継されるものであるため、経営者の承認等は定めていません。しかし、誰が承継したかを把握する必要があるため、承継者に住民票の写しを添えて必要書類を提出することを明確に義務付けています。→ 墓地承継手続きの具体的な流れや必要書類については【墓地承継手続】必要書類・添付書類を解説 も参考にしてください。第8条 使用者による契約解除(使用者による契約解除)第8条 使用者は、書面をもっていつでも契約を解除することができる。2 前項の場合においては、使用者は既に支払った使用料及び管理料の返還を請求することはできない。ただし、墓所に墓石の設置等を行っておらず、かつ焼骨を埋葬していない場合において、使用者が既に使用料を納付しているときは、契約成立後〇日以内に契約を解除する場合に限り、経営者は、当該使用料の〇割に相当する額を返還するものとする。3 第1項の場合において、契約解除の日の属する年「度」の管理料を納付していないときは、使用者は当該管理料を支払わなければならない。解説)墓地使用に関する契約であるため、使用者の都合等により、いつでも契約が解除できることとされています。契約の終了につながる重要事項であるため、書面による意思表示を求めることが適当です。→具体的な離檀届や墓地返還届のひな形については【離檀届・墓地返還届】ひな形と手続き・記載例 をご参照ください。第9条 経営者により契約の解除(経営者により契約の解除)第9条 経営者は、使用者が使用料を所定の期日までに支払わなかったときは、書面をもって、契約を解除できる。2 前項に規定する場合のほか、使用者が次の各号の一に該当する場合には、経営者は相当の期間を定めて債務の履行を催告し、その履行がないときには、書面をもって契約を解除することができる。一 〇年間管理料を支払わなかった場合二 第2条第3項に規定する使用の目的に違反して墓所を使用した場合三 第2条第4項の規定に違反して墓所を使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該墓所を使用させた場合。解説)使用料の不払いは重大な契約違反であるため、催告を規定せずに書面をもって解除できるとされています。一方、第2項については、管理料の不払いなど、比較的軽微な債務不履行であることから、まずは催告し履行を促すものとしています。管理料の不払い期間については、1年では短すぎると考えられています。第10条 契約の終了及びこれに伴う措置(契約の終了及びこれに伴う措置)第10条 契約は、次に掲げる場合に終了する。一 墓所を使用する権利を有する期間が経過した後、第6条第一項に規定する契約更新の申込がなされなかったとき二 第7条第2項の届出があったとき三 前2条の規定により契約が解除されたとき2 契約が終了したときは、使用者であった者又はその祭祀承継者(次項及び第4項において「元使用者等」という。)は、速やかに墓所内に設置された墓石等を撤去し、墓所内に埋蔵された焼骨を引き取るものとする。3 本使用者等が義務を履行しない場合において、契約終了後に〇年を経過した場合には、経営者は、墓石等を墓地内の所定の場所に移動し、及び法令の規定による改葬手続を経て埋蔵された焼骨を墓地内の合葬墓又は納骨堂に移すことができる。4 前項の場合においては、経営者は実費を元使用者等に請求することができる。解説)どのような場合に契約が終了するか、契約が終了した場合の措置について規定されています。使用者の義務を定めるとともに、その義務が履行されない場合の対応策についても具体的に規定しておくことが重要です。→ 無縁墓改葬に関する詳しい手続きについては「【無縁墓改葬】手続き相談・代行」をご参照ください。署名・捺印以上につき、使用者、経営者双方合意の上、墓地使用契約書を締結したので、これを証するため本書2通を作成し、署名捺印の上、各自1通を保管する。【使用者】 氏名 ㊞住所電話番号【経営者】 財団法人 〇〇〇〇理事長 ㊞所在地電話番号解説)契約書であることから、当事者双方が署名捺印し各自1通保管することになります。3. 墓地使用規則と合わせて整備すべき関連書類円滑な墓地運営のためには、墓地使用規則だけでなく、以下の関連書類も合わせて整備しておくことが重要です。(1)墓地承継届墓地の使用者が亡くなった際、祭祀承継者がその地位を引き継ぐための書類です。承継者を明確にすることで、将来的なトラブルを防ぎます。→ 関連記事:【墓地承継手続】必要書類・添付書類を解説(2)離檀届・墓地返還届墓じまい等により墓地を返還する際に、使用者から書面で正式な意思表示を受けるための書類です。後々の「言った、言わない」のトラブルを回避するために役立ちます。→ 関連記事:【離檀届・墓地返還届】ひな形と手続き・記載例(3)墓石簿・墓地台帳墓地、埋葬等に関する法律に基づき、墓地管理者が備え付け・保存を義務付けられている帳簿です。使用者の氏名、住所、使用開始年月日などが記録され、墓地運営の基礎となります。→関連記事:【墓石簿・墓地台帳】記載事項と作成方法を解説4. 規則作成・変更時の注意点と専門家活用のメリット(1)墓地使用規則作成・変更の注意点墓地使用規則の作成や変更を行う際は、以下の点に注意が必要です。曖昧な表現を避ける:「良識に従う」「常識の範囲内で」といった曖昧な表現はトラブルの元となります。具体的な数値や行動を明記することが重要です。法令との整合性: 墓地、埋葬等に関する法律など、関連法令に違反しない内容で作成する必要があります。利用者への周知:新しい規則を適用する際は、必ず利用者(檀家・墓地使用者)に周知し、合意形成を図ることが求められます。書面での個別通知や掲示板への掲示、ウェブサイトでの公表などが考えられます。(2)専門家(行政書士)に相談するメリット墓地使用規則の作成・変更は、専門的な知識が必要となり、ご自身で行うには多くの時間と労力がかかります。お墓の手続きに精通した行政書士に相談するメリットは以下の通りです。法的観点からの規則整備:法律や過去の判例に基づいた、有効かつ公正な規則案を提案することで、後々のトラブルリスクを軽減できます。書類作成の手間と時間を削減:複雑な条文作成や手続きを代行することで、住職や関係者の負担を大幅に軽減します。利用者との円滑な関係構築に貢献: 専門家が客観的な視点で規則を整備することで、利用者に「公平なルールが定められている」という安心感を提供し、関係性を良好に保つことに貢献します。5. まとめ|適切な規則で安心の寺院・霊園経営を墓地使用規則は、単なるルールブックではなく、寺院・霊園と利用者双方を守るための重要な契約書です。現在の寺院運営の課題や将来の展望に合わせた適切な規則を整備することで、安定した墓地経営に繋がります。しかし、その作成や見直しには専門的な知識が必要となるため、ご自身だけで対応するのは難しい場合もあります。当事務所では、宗教法人の法務サポートを行っております。個別の状況に応じた最適な墓地使用規則の作成・見直しを支援いたします。→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから