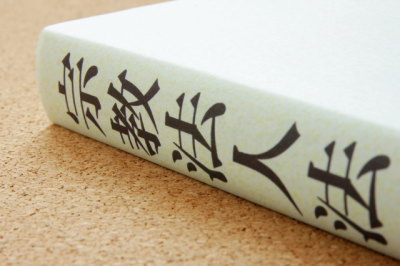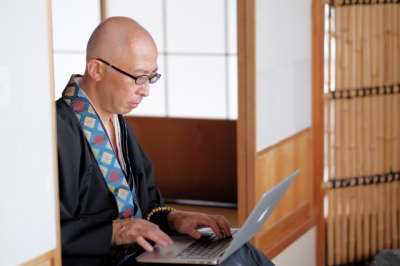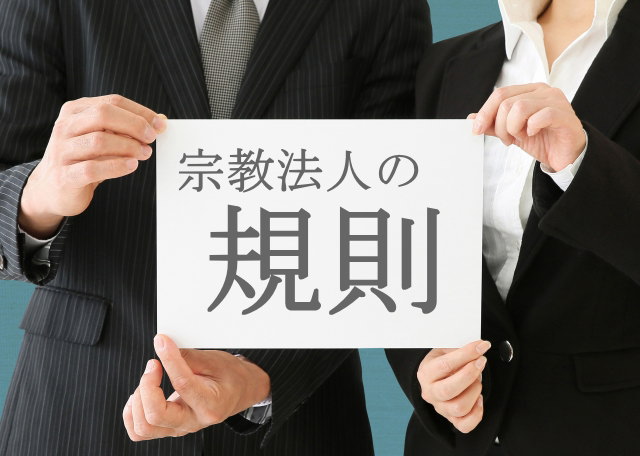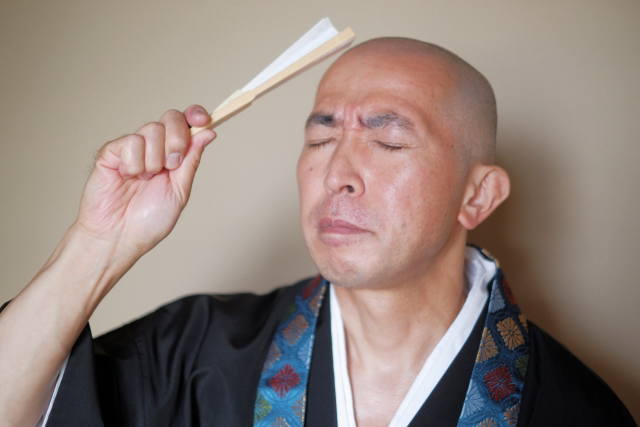指定寄付金とは?

「令和6年能登半島地震で被災した寺院を復旧させたいが、寄付金は集まるだろうか…」「寄付者に税制上のメリットを提供する方法はないか?」そうお考えではありませんか?
災害で被災した公益的な施設等の復旧のため、宗教法人等が募集する寄付金は、一定の条件を満たすことで「指定寄付金」として認められ、寄付者が税制上の優遇措置を受けられる特例措置が設けられています。
この記事では、この「指定寄付金制度」について、申請の対象者、対象となる施設、具体的な手続きの流れ、必要な書類までを専門家が分かりやすく解説します。
1. 指定寄付金制度とは?特例措置の概要とメリット
(1)指定寄付金の定義と令和6年能登半島地震の特例
「指定寄付金」とは、宗教法人等の公益事業を行う法人に対する寄付金で、公益の増進に寄与し緊急を要する特定の事業として財務大臣の指定を受けたものを言います。
通常、国宝や重要文化財の修理・防災施設設置費用等が対象となりますが、令和6年能登半島地震により滅失・損壊した宗教法人の施設等も、特例措置として指定寄付金の対象となりました。これにより、一定の要件を満たし、所轄庁の確認を受けたものは、寄付者が税制上の優遇措置を受けることができ、寄付が集めやすくなります。
(2)寄付者が受けられる税制上の優遇措置
この制度を活用した場合、寄付者は以下の税制上の優遇措置を受けることができます。
- 個人の場合: 所得金額の40%または寄付金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得金額から控除できます。
- 法人の場合:寄付金の全額を損金の額に算入できます。
- 申請期限: 令和6年能登半島地震の指定寄付金制度の申請期限は、令和9年12月31日までになります。
(3)制度申請の対象となる宗教法人
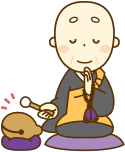
指定寄付金制度の申請を行えるのは、能登半島地震により被災した建物等を所有する下記の宗教法人です。
- 単立宗教法人
- 包括宗教法人
- 被包括宗教法人
自ら所轄庁に申請する方法、または包括宗教法人が申請する方法があります(併用は不可)。
2. 指定寄付金制度の申請対象となる施設
(1)建物・構築物等の要件と具体例
指定寄付金として募集対象になるのは、以下の要件をすべて満たす建物・構築物等です。
- 要件(a): 宗教法人が専ら自己の宗教活動または公益事業の用に供していた建物等であること(個人所有は不可)。
- 要件(b): 能登半島地震により建物等が滅失または損壊し、補修なしには建物等として本来の機能を果たさない、または利用の継続が困難であること。
【注意】収益事業に使用していた建物は対象外です。
具体的な施設例
仏教系
(建物) 本堂、客殿、庫裏、観音堂、薬師堂、僧堂、檀信徒会館、仏具庫、内陣、堂内荘厳、納骨堂、位牌堂、書院、教職舎、持仏堂、稲荷堂、土蔵、経蔵等。
(構築物) 鐘楼、山門、参道、土塀、太鼓楼、灯籠、地蔵、祠、石碑、仁王像等。
神道系
(建物)社殿、本殿、拝殿、祝詞殿、幣殿、覆殿、境内神社社殿、祖霊社社殿、神具庫、祭器庫、社務所、随神舎、参集殿、宝物殿、神楽殿、神社会館、祈祷殿、神輿庫、授与所、御旅所、参籠所等。
(構築物)手水舎、絵馬堂、鳥居、玉垣、石碑、忠魂碑、透塀、寄付石碑、狛犬、灯籠、社号標、記念碑、随神像等。
キリスト教系
(建物)礼拝堂、教会、牧師館、会堂、修道院、伝道所、小神学校、神学校、教職舎、信徒育成所、信徒修行所、記念館、会館、納骨堂、事務所等。
(構築物)塀、門扉、十字架等。
付属設備
暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機等。
(2)その他固定資産と土地について
- その他固定資産:仏具や仏像など、建物等が損壊したことに伴って損壊した場合が対象となります。地震発生時に実在し、建物に設置されていたことが確認できる必要があります。
- 土地:敷地の整地や地盤改良など、原状回復事業の一環として要する費用が対象となります。
3.寄付金の募集限度額と募集期間
(1)募集限度額の計算方法
募集限度額は、対象施設の原状回復にかかる費用から、自己資金、借入金、補助金を差し引いた額となります。
【注意】銀行等の借入金を指定寄付金で返済することは認められていません。
(2)募集可能な期間
所轄庁の確認を受けた日の翌日から3年以内で、寄付金の募集要項で定めた日までとなります。
4. 指定寄付金制度の申請手続きの流れ
(1)宗教法人が自ら申請する場合
①事前準備
建物等の調査、寄付金を募集する必要性等の検討を行います。(所轄庁との事前打合せも行います。)この結果、募集条件に該当し必要性もありと判断した場合、寄付金用の口座開設、寄付の募集方法を検討・決定します。
②所轄庁への申請
申請書類一式を作成し添付書類を添えて所轄庁へ申請を行います。
〔添付書類〕
・申請年度収支予算書、前年度、前々年度の収支計算書
・能登半島地震により滅失・損壊をしたことを証明する書類(被災届出証明書等)
・見積書等の資料(工事請負契約書、工事見積書等)
③募集開始と情報公開
申請が所轄庁より妥当なもの判断された場合、確認書が交付されます。(確認日の翌日から募集の開始が可能となります。)尚、募集を開始から終了するまでの期間については、毎月ごとに寄付金の件数、金額等の公開、一年ごとに原状回復の実績、収支実績の公開を行う必要があります。(ホームページ等により)
④所轄庁への報告
募集開始後は、下記の報告を所轄庁に行う必要があります。
ⅰ)年次報告(会計年度終了後4か月以内)
ⅱ)募集終了報告(目標額に達した場合、募集期間終了後1か月以内)
ⅲ)募集終了後事業報告(募集終了後、原状回復が完了するまで会計年度終了後4か月以内)
ⅳ)完了報告(原状回復完了後1か月以内)
〔添付書類〕
・収支明細書、通帳の写し等
(2)包括宗教法人が取りまとめて申請する場合
包括宗教法人が被包括宗教法人を取りまとめて申請する場合、まず被包括宗教法人が所轄庁に対し副申申請を行います。その後、包括宗教法人が各被包括宗教法人から集めた書類を取りまとめ、所轄庁へ確認申請を行います。
5. まとめ:指定寄付金制度を復旧支援に活用する

指定寄付金制度について解説させて頂きました。能登半島地震による特例の指定寄付金制度を利用するには、地震により建物等が滅失・倒壊したこと、募集できる寄付の金額は自己資金等差し引いた額であることなどの制限もありますが、通常の寄付と比べ税制上のメリットもある指定寄付金制度を利用する事で寄付が集めやすくなるとも言えます。
但し、寄付の募集等については、自ら行う必要がありますので、ホームページ等により幅広い方に寺院等の現状について知って頂くこと(情報発信)も必要になります。(包括宗教法人にて一括して行う場合を除く。)どの様に進めるべきか?一度検討されて見ては如何でしょうか。
当事務所は、宗教法人の事業運営に関するサポートを行っております。もし、ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。
→ 事業運営や規則変更に関する詳細は、宗教法人の法務(運営・管理)サポート のページをご覧ください。
 「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。
「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。
もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。
・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。
※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)