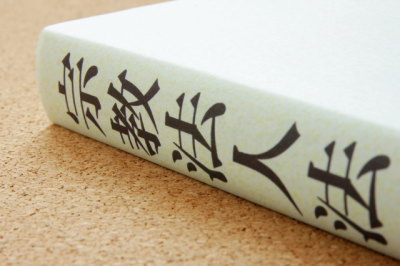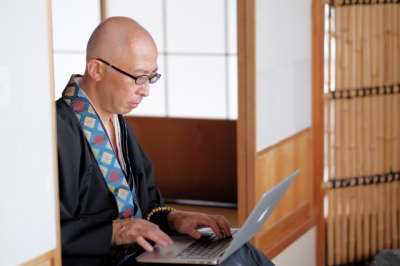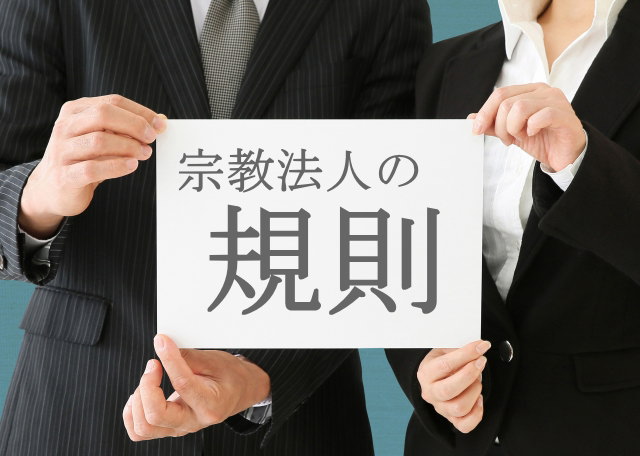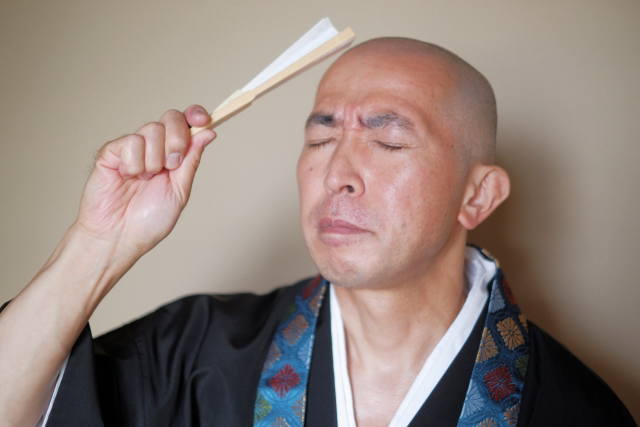宗教法人法第25条には、事務所に備え付けておくべき書類として「事務処理簿」が定められています。
しかし、「事務処理簿」の具体的な記載内容について、明確な規定がないため、どのように作成すれば良いか分からずお困りの方も多いのではないでしょうか?
この記事では、当事務所が行政機関に直接確認した内容を基に、事務処理簿の作成方法を分かりやすく解説します。
1. 事務処理簿とは?宗教法人法上の位置づけ
事務処理簿は、宗教法人法第25条に基づき、事務所に備え付けておくことが義務付けられている書類の一つです。
→ 宗教法人が備え付けるべき書類は【宗教法人】備付・保存書類の義務と作成方法 の記事で詳しく解説しています。
文化庁の「宗教法人の管理運営」によると、宗教法人の事務とは「第三者との取引や、財産の管理など世俗的な業務の一切」を指すとされています。なお、この備え付け義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2. 行政機関に直接確認した、事務処理簿の記載内容
事務処理簿の具体的な内容が不明確であるため、当事務所が直接行政機関に確認したところ、以下のような回答を得られました。
(1)A県の回答
最初は、金銭的な支出等について話されていましたが、それでは収支計算書等と同じになるのでは、ないでしょうか?と聞いてみました。
宗教法人で8千万円以下の収入の場合、収支計算書の作成は免除されており、それ以上の場合は、収支計算書を作成する訳ですから、同じもの記載する意味はあるのでしょうか?と更に質問しました。
結果、基本的には事務処理簿の内容については、宗教法人側の自主的な運営に任せているので、行政側で指導するものでもないという回答でした。
要は、事務処理簿の備付けは法的な義務ではあるが、行政側は内容について関わらないということになります。これでは何を記載すれば良いか?わからないままなので、更に文化庁 宗務課に電話で直接確認しました。
(2)文化庁宗務課の回答
最初の方は、県と同じようなことをお話しされていましたが、結局、不明確なままで、その後詳しい担当者に代わりますとのことで、再度お聞きしました。
回答は、事務処理簿の趣旨としては、代表役員等が交代した場合や亡くなった場合など、その事務処理簿を見ればわかるようにしたもの。要は引き継ぎ日誌のようなもの。例えば、檀家から預かりものや何か一時的な対応をしたものなど事務処理簿に記載しておくことにより、代表役員に何かあった場合スムーズに引き継ぎが行えるように記載しておくものが事務処理簿の趣旨であるとのことでした。
→ 宗教法人の承継手続きは【宗教法人の承継】手続き・注意点を解説 でも詳しくご紹介しています。
行政側としては、特に記載する内容を定める訳ではなく、その内容は宗教法人によるということは県と同様の回答でした。
3. 事務処理簿の作成項目と記載例(当事務所の推奨)
上記の趣旨を踏まえ、当事務所では、事務処理簿に以下の項目を記載することをお勧めします。
項目案:
- 番号
- 処理年月日
- 区分(例:檀家からの預かり物、業者との打ち合わせなど)
- 事務内容(詳細な記録)
- 備考
例えば、以下のように記載することで、事務処理簿がより引き継ぎに役立つものになります。
記載例:
- 番号:01
- 処理年月日:2025年8月19日
- 区分:檀家対応
- 事務内容:〇〇家より、墓地使用権の承継手続きについて相談あり。必要書類を案内し、後日再度連絡する旨を伝える。
- 備考:〇〇様(〇〇-〇〇-〇〇)
4. まとめ:事務処理簿を備え付けることの重要性
事務処理簿は法律で備え付けが義務付けられており、代表役員の交代時などにスムーズな引き継ぎを可能にする重要な役割を果たします。行政から内容について細かく指導されることはないものの、罰則の対象となるため、文化庁が示す「引き継ぎ日誌」の趣旨を理解し、適切に作成・保管することが不可欠です。
当事務所では、事務処理簿の作成を含め、宗教法人の運営に関する法務サポートを行っております。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
 「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。
「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。
もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。
・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。
※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)