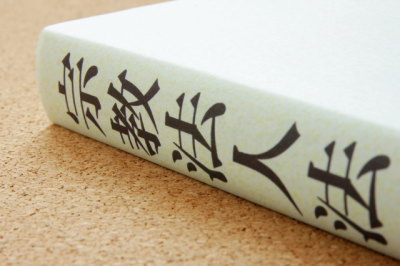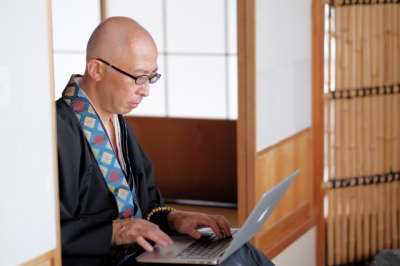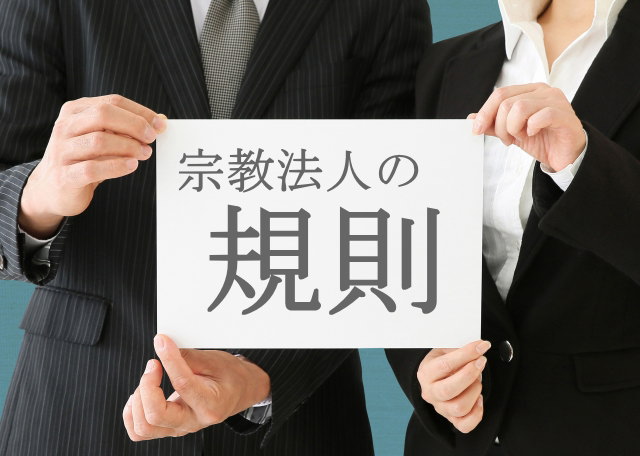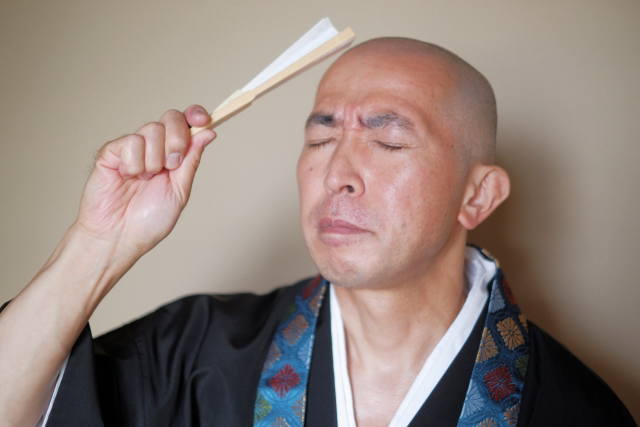宗教法人の《財産処分》の公告について解説

「境内地を売却したいが、どうすれば良いか…」「宝物を処分するのに、信者に知らせる必要があるの?」そうお考えではありませんか?
宗教法人が行う特定の財産処分については、宗教法人法第23条により、事前に信者や利害関係人に対して公告を行うことが義務付けられています。この手続きを怠ると、過料の対象となるだけでなく、行為が無効になるリスクもあります。
この記事では、財産処分の公告手続きについて、法律上の根拠、具体的な手続きの流れ、記載すべき内容、そして注意点までを専門家が分かりやすく解説します。
1.財産処分で公告が必要になる行為(宗教法人法第23条)
(1)公告が必要な行為の概要
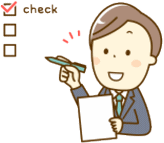
宗教法人法第23条により、宗教法人が特定の行為を行おうとするときは、少なくとも1ヶ月前に信者や利害関係人に対し、その要旨を示して公告を行うことが義務付けられています。この手続きを怠ると、同法第88条により10万円以下の過料に処される可能性があります。
公告が必要な行為は以下の通りです。
(2)不動産・宝物の処分、担保の供与
①不動産の処分:土地、建物、立竹木等の譲渡(売却など)、交換、賃貸借(長期)、地上権、地役権の設定など。
②宝物の処分:歴史上、信仰上、重要な価値を有する財産の処分等。
③担保の供与:不動産、宝物について抵当権や質権の設定、譲渡担保の提供等。
(3)借入または保証
④借入:銀行等からの借入(当該会計年度内の収入で償還する一時的な借入を除く)。
⑤保証:第三者の債務に対する保証人等。
(4)主要な境内建物の新築・改築など
⑥新築、改築、増築、移築、除却(取壊し)、著しい模様替え等。
(5)境内地の著しい模様替え、用途変更など
⑦境内地の著しい模様替え
⑧主要な境内建物又は境内地の用途変更等
(6)【根拠法令】宗教法人法
(財産処分等の公告)
第二十三条 宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。
一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
二 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。
三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。
四 境内地の著しい模様替をすること。
五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の第二条に規定する目的以外の目的のために供すること。
(行為の無効)
第二十四条 宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。
2.公告手続きの流れと記載すべき内容
(1)財産処分の一般的な流れ

財産処分の手続きは、各宗教法人の規則で定める必要があります。一般的には、以下の流れで進めます。
①規則変更の手続き(必要に応じて)。財産処分の内容によっては、事前に規則変更が必要となる場合があります。
→ 規則変更に関する詳細は【宗教法人の規則変更】手順・手続き を解説をご覧ください。
②責任役員会の議決。
③総代会の同意。
④包括宗教団体の承認等。
⑤公告の実施。
⑥財産処分の実行。
⑦財産台帳の整理と登記変更(必要に応じて)。
公告に対し反対意見が特にない場合は、財産処分を行い財産台帳の整理も行います。又、処分した財産が宗教法人の基礎財産である場合は、基本財産の変更登記を行い登記後に所轄庁への登記事項届出も行います。
(2)公告に記載すべき内容
公告を行う際には、以下の内容を記載します。
- 財産の処分・担保の提供:処分する物件、価格、相手先、処分の目的、方法、年月日など。
- 借入・保証:借入金額または保証債務額、目的、相手先、条件など。
- 境内建物の新築・改築など: 建物の名称、建坪、理由、所要経費、工事計画など。
- 境内地の著しい模様替え: 模様替えの概要、面積、理由、所要経費など。
- 境内建物、境内地の用途変更:変更の概要、理由、経費など。
3. 公告手続きの注意点と罰則
(1)公告の期間と方法
公告期間は規則で定められた期間になりますが、財産処分の場合は1ヶ月前に行う必要があります。公告の方法は、規則で定める方法(機関紙、事務所の掲示板等への貼付け等)に従います。
(2)公告を行わなかった場合の罰則
公告を行わずに行った行為は、宗教法人法第24条により無効と定められています。ただし、善意の相手方または第三者に対しては、その無効をもって対抗することができません。また、公告義務に違反した場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。
(3)公告確認証明書の作成
公告を行った証拠として、状況写真(公告文の提示状況)の撮影及び公告確認証明書を作成し信者・利害関係人の方から公告を確認した事実として署名・押印を頂いておきましょう。(確認者3名以上)
4. まとめ:適正な手続きが法人の信頼を守る

公告を行うべき項目は法律で定められています。これを怠ると、行為の無効や過料といった罰則に繋がるだけでなく、法人の信頼を損なうことにもなりかねません。適正な手続きを行うことが、法人の健全な運営と、将来的なトラブルを未然に防ぐ上で非常に重要です。
当事務所は、宗教法人様に対する法務サポートを行わせて頂いております。もし、ご不明な点等がありましたら、お気軽にご相談下さい。
→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
 「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。
「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。
もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。
・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。
※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)