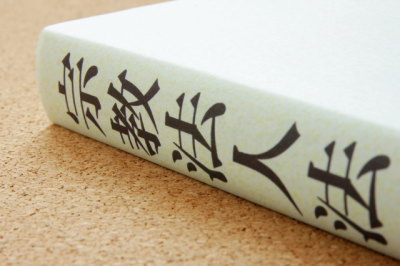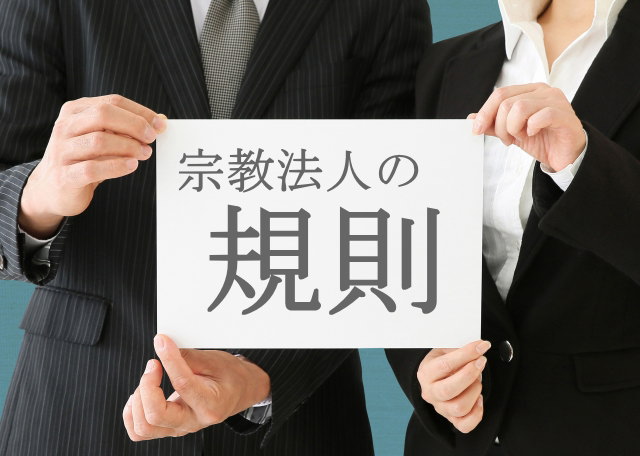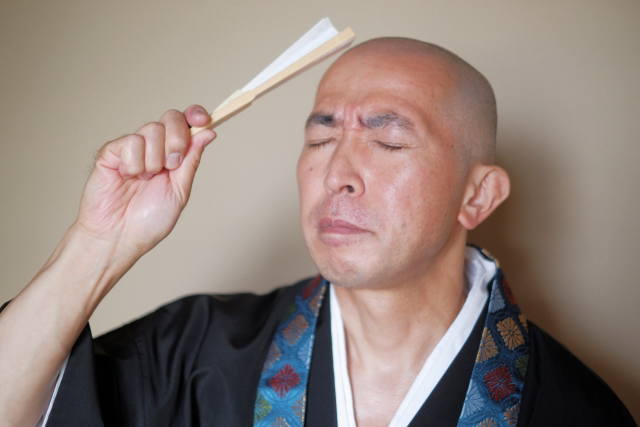墓石簿(墓地台帳)の根拠条文
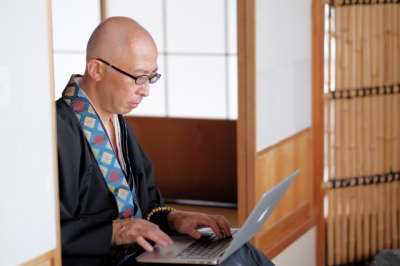
「墓地台帳を備え付ける義務があるのは知っているが、何を、どこまで記載すれば良いのか分からない…」
そうお悩みではありませんか? 墓地台帳(墓石簿)は、墓地、埋葬等に関する法律によってその備え付けが義務付けられている、非常に重要な帳簿です。正確な管理を行うことで、将来的なトラブル防止にもつながります。
この記事では、墓地台帳に記載すべき事項を、根拠となる法律の条文からわかりやすく解説します。また、効率的な作成方法のポイントや、専門家である行政書士に相談するメリットもお伝えしますので、ぜひご一読ください。
1. 墓地台帳(墓石簿)の備付けは法律上の義務
(1)墓地、埋葬等に関する法律 第15条・第16条
墓地を経営する場合、「墓地、埋葬等に関する法律」により、墓地台帳(墓石簿)等の備付けが義務づけられています。
・【第15条】 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。
・【第16条】 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5箇年間これを保存しなければならない。
(2)墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第7条
また、法律の具体的な内容を定めた施行規則 第7条には、帳簿に記載すべき事項が挙げられています。
【第7条】 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
1.墓地使用者等の住所及び氏名
2.第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
3.改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
→ 備付け・保存書類の義務全般については【宗教法人】備付・保存書類の義務と作成方法 も参考にしてください。
2. 墓地台帳(墓石簿)に記載すべき事項の整理
上記法律の条文内容を、よりわかりやすく整理したものが以下になります。
- 【墓地使用者等】 氏名・住所
- 【死亡者】 氏名・住所・本籍・性別・死亡年月日
- 【死産の場合】 父母の氏名・住所・本籍・分べん年月日
- 【埋蔵等の年月日】 埋葬・埋蔵・収蔵の年月日
- 【改葬に関する事項】 許可を受けた者の氏名・住所、死亡者との続柄、墓地使用者等との関係、改葬の場所及び年月日
これらの記載事項は、墓地の適正な管理運営を行う上で、最低限必要となる情報です。
→ 墓地使用者等との関係を円滑に進めるためには【墓地使用規則】契約約款の指針・ひな形を解説 も併せてご確認ください。
3. 【ひな形】墓地台帳(墓石簿)の作成サンプル
墓地台帳には様々な形式がありますが、一つの参考として、上記の記載事項を網羅したサンプルを提示します。状況に合わせて追加項目等を設定してご活用ください。
| 番号 | 墓地使用者 | 死亡者 | 埋 葬 | 改 葬 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① |
【 氏 名 】 〇〇 〇〇 【 住 所 】 【死亡者との続き柄】 |
【 氏 名 】 〇〇 〇〇 【生年月日】 【死亡年月日】 |
【年月日】 |
【年月日】 【 氏 名 】 【 住 所 】 【死亡者との続き柄】 【墓地使用者との関係】 【改葬先の場所】 |
|
| ② |
【 氏 名 】 【 住 所 】 【死亡者との続き柄】 |
【 氏 名 】 【生年月日】 【死亡年月日】 |
【年月日】 |
【年月日】 【 氏 名 】 【 住 所 】 【死亡者との続き柄】 【墓地使用者との関係】 【改葬先の場所】 |
|
| ③ |
【 氏 名 】 【 住 所 】 【死亡者との続き柄】 |
【 氏 名 】 【生年月日】 【死亡年月日】 |
【年月日】 |
【年月日】 【 氏 名 】 【 住 所 】 【死亡者との続き柄】 【墓地使用者との関係】 【改葬先の場所】 |
4. 備付け義務を果たすための専門家活用メリット
墓地台帳(墓石簿)の備付けは、日々の管理業務の一部ではありますが、専門的な知識と正確な対応が求められる業務です。お墓の手続きに精通した行政書士に相談するメリットは以下の通りです。
(1)法的リスクの軽減と確実な作成
法律の条文は専門的で、解釈を誤ると義務を果たせない可能性があります。専門家が法的観点から書類の作成や管理方法をアドバイスすることで、罰則リスクを軽減できます。
(2)電子化による管理の効率化
墓地台帳の電子化は、膨大な情報の管理・更新を効率化し、長期的な運営の負担を減らします。当事務所では、電子化のサポートも行っております。
(3)円滑な運営体制の構築
備付書類を適切に整備することは、運営の透明性を高め、寺院・霊園と利用者双方の信頼関係を築く基礎となります。専門家の客観的な視点で体制を構築することで、円滑な運営に貢献します。
5. まとめ|正確な帳簿管理で健全な墓地運営を

墓地台帳(墓石簿)の備付けは、墓埋法に定められた義務であり、その正確な作成と管理は、寺院・霊園の運営の健全性を示す重要な証拠となります。
帳簿の整備は、日々の運営における手間や、法律上のリスクに直結するため、お悩みの方は少なくありません。
当事務所は、お墓の手続きを専門とする行政書士事務所として、これらの複雑な書類作成や管理方法の整備をサポートいたします。法律の専門家にご相談いただくことで、安心して本業に専念できる環境を整えることができます。
→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
 「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。
「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。
もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。
・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。
※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)