


・近年、核家族化や少子高齢化が進む中で、お墓のあり方も大きく変化しています。従来の「家のお墓」を代々継承していく形が難しくなり、「承継者がいない」「子供に負担をかけたくない」といったお悩みから、永代供養墓を選ぶ方が増えています。
当事務所でも、墓じまい後の改葬先として永代供養墓をご希望される方が最も多く、注目度の高さが伺えます。
このページでは、永代供養墓とは何かという基本的な知識から、その歴史、納骨・供養方法、種類、費用、そして後悔しないための選び方や注意点まで、行政書士が分かりやすく徹底解説いたします。永代供養墓への埋葬や改葬をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
1. 永代供養墓とは?その定義と現代のニーズ

永代供養墓とは、親族や祭祀承継者に代わり、寺院や霊園が永代にわたって供養と管理を行うお墓のことを指します。
一般的な寺院や霊園では、お墓の承継者がいない場合、お墓の購入が難しいことがありますが、永代供養墓はそのような条件を問わないため、独身の方やお子さんのいない方、または「子供にお墓のことで迷惑をかけたくない」と考える方が利用されています。費用面でも、通常のお墓を建立するよりも比較的安価に済む傾向にあります。
(1)永代供養墓が注目される理由
現代社会では、以下のような課題に対応できる点が永代供養墓の大きな魅力となっています。
- 管理負担の軽減:墓地の掃除や供養の手配など、遺族の手間が大幅に軽減されます。
- 費用の明確さ:初期費用や維持費が従来のお墓に比べて低く設定されており、金銭的な負担を抑えられます。
- 多様な選択肢:宗教や形式を問わない供養方法が増え、個人の希望や価値観に応じて選べる柔軟さがあります。
(2)永代供養と永代使用権の明確な違い
「永代供養」と「永代使用」は似た言葉ですが、その意味は大きく異なります。
・永代使用権と永代供養の違いについて、詳しくは、【永代使用権と永代供養】違い・費用・承継を徹底解説 の記事をご覧ください。
① 永代使用権とは?
寺院や霊園などにお墓を建てる「場所を借りる権利」を指します。お墓を建てると、子孫がそのお墓を承継していくため、永代にわたってその土地を使用することになります。 「お墓を買う」という表現がされますが、土地自体は借りている状態です。永代使用権は転売が禁止されており、返還についても期限が設けられ、その期間内でないと返金されない場合がほとんどです。
② 永代供養とは?
ご遺骨を埋蔵(埋葬)し、その遺骨を永代にわたって管理・供養してもらうことを言います。 「永代」と聞くと永久をイメージするかもしれませんが、実際には一定の契約期間(13回忌、33回忌など)が設定されていることが多く、期間満了後は合祀墓に移されるのが一般的です。
2.永代供養墓の歴史と社会における役割

永代供養の考え方自体は、昔から日本の仏教文化に根付いていました。しかし、現在のような永代供養墓が注目されるようになったのは、約30年前からと言われています。
当初は「家の墓を守る」という伝統的な価値観が強く、永代供養墓への抵抗感も存在しました。また、初期の永代供養墓は管理システムも未整備で、「無縁塔」との区別も曖昧な部分がありました。
(1)社会問題と永代供養墓の発展
しかし、少子化や核家族化といった社会問題が深刻化するにつれて、従来の「家のお墓」に頼らない供養の形として永代供養墓の需要が急速に高まりました。これに応える形で、永代供養墓の質も向上し、デザイン性の向上や、契約期間や供養の頻度など利用者が安心できる管理システムの構築が進んでいます。
(2)現在の永代供養墓の役割
現在では、永代供養墓は単なる供養の手段に留まらず、現代社会に適した供養スタイルとして広く受け入れられています。これにより「死後も安心できる場所」としての信頼性が高まり、従来の墓地に代わる選択肢として定着しつつあります。
3. 永代供養墓の主な種類と形式
永代供養墓には様々な形式があり、それぞれに特徴と費用相場が異なります。ご自身の希望や予算に合わせて選択することが重要です。
(1)お墓を建てるタイプ(一般墓型永代供養墓)
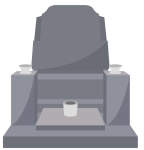
通常のお墓より規模は小さいですが、個別に墓石を建てるタイプです。カロート(遺骨を納める場所)も比較的小さく、骨壺2~3個程度まで埋葬可能です。個別にお墓を持つため、費用は他のタイプに比べて割高になる傾向があります。 「他の遺骨と一緒になることに抵抗がある」「〇〇家としてお墓を持ちたい」と考える方に向いています。
(2)永代供養塔タイプ(合葬・個別埋葬)

シンボル的な供養塔の下に遺骨を埋葬するタイプで、永代供養墓と聞いて多くの方がイメージする形式です。
供養塔の下の棚などに骨壺ごと埋蔵(埋葬)します。十数万円程度が相場と言えます。
記念碑などの大きなカロートに、他の方の遺骨と一緒に埋葬されます。骨壺から取り出して埋葬する形式や骨袋に移し替えて埋葬する形式があります。他の遺骨と一緒になるため、後から改葬することはできません。
費用は個別タイプより安価な場合が多く、NPO法人が運営する合祀タイプではご遺骨一体につき3万円程度で納骨可能なケースもあります。承継者がいないため無縁墓になることを避けたい方が選択することが増えています。
(3)納骨堂タイプ

承継者不要で永代にわたり供養されることが一般的であり、納骨堂も永代供養墓の一種と言えます。土地をあまり必要としないため、都心部の建物内に設けられていることが多く、交通の便が良い場所にあることが人気の理由です。
ロッカー形式など、家族単位で納骨できるタイプもあります。費用は永代供養塔タイプより高額ですが、十数万円から百万円程度が相場です。屋内であるため、雨天でもゆっくりとお参りできます。近年では、ペットと一緒に埋葬可能な納骨堂も人気があります。
・納骨堂について詳しくは、【納骨堂とは】選び方・費用・注意点を解説 をご覧ください。
(4)樹木葬タイプ

樹木葬も永代供養墓の一種です。近年、自然なイメージが持てることから人気が高まっています。シンボル的な記念樹の元に埋蔵(埋葬)するタイプが現在では主流になっています。
骨壺のまま埋蔵するタイプと、骨壺から遺骨を取り出して埋蔵するタイプなど、様々な形式があります。基本的には永代供養塔の個別埋葬と同様の形式となります。費用は10万円から80万円程度が相場です。
・樹木葬の基礎知識や選び方の詳細については、【樹木葬】基礎知識・選び方 で解説しています。
4. 永代供養墓にかかる費用とその内訳
永代供養墓にかかる費用は、その形式や運営主体(寺院、民間霊園、自治体)によって大きく異なります。
(1)永代供養墓の形式ごとの費用相場
| 永代供養墓の形式 | 費用(相場) |
|---|---|
| 従来のお墓を建立するタイプ | 100万円~300万円程度 |
| 一般的な永代供養墓(個別埋葬) | 20万円~100万円程度 |
| 一般的な永代供養墓(合祀) | 5万円~50万円程度 |
| 樹木葬 | 10万円~80万円程度 |
| 納骨堂 | 20万円~200万円程度 |
(2)その他、発生する費用
| 項 目 | 費用相場 |
|---|---|
| 墓誌・プレートの彫刻費用(希望する場合) | 2万円~10万円程度 |
| 入会費・年会費・維持管理費(契約内容による) | 0円~2万円程度 |
| 事務手数料・納骨手数料(霊園により異なる) | 0円~5万円程度 |
| お布施(納骨供養を行う場合) | 3万円~5万円程度 |
永代供養墓使用料は寺院により大きく異なります。ご遺骨一体につき数万円から50万円程度まで様々です。同寺院内の墓地を墓じまいして永代供養墓へ改葬する場合は、既存のお墓の撤去費や、離檀料を請求される場合もあります。
様々な形式がありますが、永代供養塔タイプの個別葬は十数万円程度、合祀タイプでは数万円程度が相場と言えます。納骨堂タイプでは、十数万円から百万円程度になります。
費用は比較的安価で、数万円程度から利用可能です。ただし、居住要件など様々な条件が設定されていることが多いため、事前に各自治体へ確認が必要です。
5. 永代供養墓を選ぶ際のポイントと注意点
永代供養墓は一度契約すると長く付き合うことになるため、慎重な検討が必要です。後悔しないために、以下のポイントを確認しましょう。
(1)契約時期と流れ
場所、形式、費用を検討し、実際に寺院・霊園を見学します。管理規約や使用規則も確認し、問題がなければ納骨時期に合わせて契約を進めます。契約から納骨まで数ヶ月かかる場合もあるため、事前確認が重要です。
墓じまいをして永代供養墓に埋葬することを「改葬」と言います。改葬には自治体の改葬許可申請が必要です。特に寺院にお墓がある場合は、ご住職に墓じまいや改葬の理由を丁寧に説明し、理解を得ることが大切です。管理者の了解を得てから永代供養墓を契約しないと、後でトラブルになり、永代供養墓が無駄になる可能性もあります。
・改葬時の永代供養墓選びや手続きの注意点については、【改葬後】永代供養墓の選び方 で詳細を解説しています。
(2)墓地管理会社の確認
霊園を管理する会社はどこか、評判はどうかを確認しましょう。(実際の管理は石材店などが行っている場合もあります。) 事前にインターネットなどで情報を集め、現地で管理事務所の対応なども確認することをお勧めします。(会社の規模・経営状況なども併せて確認)
(3)交通の便と立地
霊園までの交通の便は非常に重要です。ご自身が高齢になった際に、車の運転をやめる可能性も考慮し、公共交通機関でのアクセスが良い場所を選ぶと良いでしょう。 「遠方だと年々お参りに行くのが大変になる」という声も多く聞かれます。
(4)霊園内の設備・バリアフリー
休憩施設、トイレ、売店などの設備の充実度や清潔さを確認しましょう。特にご自身が高齢になった際に、これらの設備が充実していると、お墓参りが快適になります。園内の階段や段差の多さも確認が必要です。
(5)契約書・使用規則の確認事項
契約時には、詳細な見積書をもらい、永代供養墓使用料以外の費用(プレート代、納骨手数料、お布施など)も含めた総額を必ず確認してください。
永代供養の期間、その後の遺骨の扱い(合祀される時期、場所など)、維持管理費の有無など、使用規則や管理規約の内容を事前にしっかり把握することが重要です。寺院によっては規則があまり具体的に記載されていない場合もあるため、不明点はご住職に質問し、明確な説明を受けましょう。
6. 納骨・供養の方法と期間
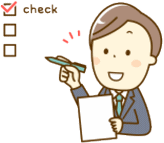
永代供養墓における納骨・供養の方法は、大きく分けて2種類あります。
永代供養墓として用意された区画に、個別のスペースを設けて骨壺のまま、または骨壺から取り出して埋葬する形式です。樹木葬や一部の納骨堂もこのタイプに含まれます。
通常、安置期間が定められており、13回忌や33回忌を区切りとすることが多いです。期間経過後、遺骨は合祀墓に移されるのが一般的です。埋葬可能な遺骨数は通常3~4体程度までですが、骨袋に移せば増える場合もあります。
シンボル的な記念碑等の地下にある大きなカロート(埋葬スペース)に、他の方の遺骨と一緒に埋葬される形式です。骨壺から取り出して埋葬する、または骨袋に移して埋葬する形式があります。一度合祀されると、後から遺骨を別の場所に移す(改葬)ことはできません。費用は合葬タイプより安価な場合が多いです。
(1)永代供養の期間とその後の遺骨の扱い
個別に埋葬するタイプや納骨堂の場合、一定期間の経過後に管理者によって他の遺骨と合祀されることになります(例外もあります)。期間については、13回忌まで、33回忌までなど、霊園などにより様々ですので、事前に契約書等にて確認しておきましょう。
永代供養墓と言いましても、契約した場所に永代に埋蔵(埋葬)されているわけではありませんので注意が必要です。中には、維持管理費を毎年支払う永代供養墓もありますが、そのような墓地は、維持管理費が支払われている限り継続してその場所に埋蔵(埋葬)されることになります。
(2)納骨の具体的な手順
- ご希望の永代供養墓のある寺院・霊園等に見学に行く事から始めます。
- 予め予約した日時に納骨を行います。
- ご住職をお呼びして納骨供養を行うか、霊園管理者または石材店の進行により納骨を行うかを決めておきます。
- 納骨の際には、埋葬許可証または改葬許可証が必ず必要になりますので、忘れずに持参しましょう。
- 納骨時の服装は、近年では夏場など無理に礼服を着る必要はなく、地味な服装であれば問題ありません。
7. よくある質問
Q1: お墓を選ぶ際に、どのような点に注意すれば良いですか?
A:費用と場所が最も重要になります。費用面については、パンフレットなどで費用を確認します。場所は、公共の交通機関で行きやすいか、将来免許を返納する可能性も考慮して確認しておく必要があります。
Q2: 良い霊園と良くない霊園の違いは?
A: 一言では言えませんが、比較的人気のある霊園は、お参りに来る方も多く、いつも花などが供えられ清潔感もあります。逆に、お参りに来る人もあまりいない非常に寂しい霊園もあります。供養されるなら、お参りに来る人が多い霊園の方が気分的にも良いでしょう。
Q3: どのような永代供養墓を選ぶのが良いですか?
A:現在、様々な形式のお墓がありますので、まずは希望の形式を選択し、次に予算に合うお墓を選びます。個別埋葬、合祀など予算に応じて埋葬形式を選択できますので、ご家族とよく相談された上で決めると良いでしょう。
Q4: 納骨の際に、ご住職をお呼びして供養した方が良いですか?
A:ご自身の気持ち次第になります。霊園などで納骨する際に、ご住職をお呼びしないで納骨される方も多くおります。
Q5: 遠方より近くのお墓を選んだ方が良いですか?
A: 金額にもよりますが、将来的なことも考えて近くの霊園等を選ばれた方が良いでしょう。遠方だと年々お参りにいくことも大変になります。もし、将来引越し等を行う可能性がある場合は、骨壺で保管してもらえる永代供養墓を選択しておけば、将来、居住地が変わった場合、お墓の引越し(改葬)も可能になります。
8. まとめ

「お墓を守る継承者がいない」、「子どもたちにお墓のことで負担をかけたくない」、「独身で亡くなった後のことが心配」――こうした現代の多様なニーズに応えるのが永代供養墓です。
永代供養墓は管理の利便性や費用の明確さから多くの人々に支持されており、寺院や霊園でも様々な形式が提供されています。従来の形にとらわれない永代供養墓は、利便性が高く、費用も比較的抑えられるため、現代の社会状況に適した新しいお墓の形といえます。今後も需要がさらに増えることが予想されます。
最後に当事務所のご紹介をさせて頂きます。当事務所はお墓の手続きを専門としている行政書士事務所になります。これまで100件以上のお墓じまい等を行わせて頂きました。
近年、お墓じまい後に遺骨を埋葬する先として永代供養墓を選ばれる方が多くなっております。お客様の中には、永代供養墓を紹介してほしいと言われる方も多く、当事務所ではNPO法人等が運営する永代供養墓をご紹介させて頂いております。
もしお墓の事でお困りのことなどありましたら、当事務所にお気軽にご相談下さい。お墓に関するアドバイスから手続代行まで幅広い範囲でサポートさせて頂きます。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)

















