


・海外にお住まいの日本人の方で、日本にご家族(故人)を埋葬したいと考えるケースは少なくありません。現地で亡くなられたご家族を日本の墓地に埋葬したい、あるいは故人の遺志で日本のお墓への埋葬を希望している、と言った ご相談をよくいただきます。
日本でご遺骨を埋葬するには、主に「埋葬に関する手続き」と「埋葬先の確保」という二つの大きな課題があります。
海外在住の方にとって、ご自身が何度も日本に来ることは難しいため、事前に計画的な準備と、状況に応じた最適な「進め方(方法)」を検討しておくことが不可欠です。
この記事では、在外日本人の方が、海外から日本で埋葬を行う際の具体的な「進め方(方法)」と「考慮すべき点」について、詳しく解説します。
日本でご遺骨を埋葬するための手続概要と進め方(海外在住者向け)

海外にある遺骨を日本のお墓に埋葬する場合、埋葬(改葬)許可証が必要になります。ここで特に注意が必要なのは、ご遺骨の「すべて」ではなく「一部(分骨)」を日本に持ってくるケースです。当事務所が自治体に直接確認した最新の運用では、たとえ分骨であっても、原則として通常の改葬と同様に自治体への申請手続きが求められます。
又、埋葬する遺骨は焼骨である事が前提となりますので現地で火葬を行った際に火葬証明書を取得しておく必要があります(申請の添付書類になります。)。もし、その様な証明書がない場合は、自治体(市区町村)との事前協議を行い確認する必要があります。
埋葬(改葬)許可申請には、申請書の他に様々な添付書類等が必要になります。埋葬手続きの具体的な流れや必要書類、また手続き中に起こりうるトラブルについては、以下の記事で詳細を解説していますので、併せてご参照ください。
・埋葬に必要な書類関係や手続きの具体的な流れは、【海外の遺骨】日本で埋葬する手続きの流れ の記事をご覧ください。
・手続き中に起こりうるトラブルとその対策は、【海外から日本へ】遺骨埋葬のトラブルと予防策 の記事をご覧ください。
海外在住の方が、これらの手続きを進めるには、主に以下の4つの方法が考えられます。それぞれの方法について、海外からの状況を踏まえたメリットとデメリットを解説します。
進め方1:ご自身が来日して手続きを行う
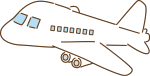
・概要:事前に自治体(市区町村)との打合せを済ませ、来日中に埋葬(改葬)許可申請および許可証の取得を目指します。
海外在住者ならではの考慮点
ご自身の目で全てを確認し、直接関係者と話ができるため、安心感が大きいです。不明な点があれば、その場で直接確認・解決できます。
複数回の来日が必要になる場合や、一度の来日で全てを完結させるには、かなりの時間的余裕と綿密な事前準備が求められます。書類に不備があると許可証が発行されず、再度の来日や郵送でのやり取りが必要になるリスクもあります。渡航費や滞在費といった費用も発生します。
進め方2:郵送で手続きを行う
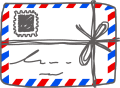
・概要: 海外から日本の自治体へ、郵送で埋葬(改葬)許可申請を行います。申請書は自治体のウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記入した上で添付書類、返信用封筒とともに郵送します。
海外在住者ならではの考慮点
来日する必要がないため、渡航費用や滞在費用を抑えられます。
書類に不備があった際のやり取りに時間がかかり、手続きが滞る可能性があります。自治体によっては、郵送申請に対応していない、あるいは一部の手続きしか郵送で受け付けない場合もあります。また、全てを郵送で行う場合は、ご遺骨の移動や納骨の際に別途手配が必要になります。
進め方3:日本に住む親族等に手続きをお願いする

概要:日本に住む親族に協力してもらい、その方に申請を代行してもらいます。親族が申請者となる場合は、親族の居住地を管轄する自治体(市区町村)が申請先となります。ご自身が申請者となり、親族に書類の提出を依頼する方法もあります。
海外在住者ならではの考慮点
ご自身の来日負担を大幅に軽減できます。親族が身近で手続きを進めるため、連絡がスムーズで安心感があります。
親族に手続きの負担がかかります。墓地管理者の連絡や書類の押印、改葬先の霊園との契約など、費用が発生するものもあるため、事前に金銭面の話し合いと明確な合意形成をしておく必要があります。
進め方4:お墓の手続き専門の行政書士に依頼する

概要: お墓の手続きを専門とする行政書士に、埋葬(改葬)許可申請を含む一連の手続きを代行依頼します。
海外在住者ならではの考慮点
最も早く確実に手続きを進めることが期待できます。ご自身の来日や親族への負担を最小限に抑えられます。海外からの複雑な書類準備や自治体・墓地管理者とのやり取り、遺骨の受取・納骨の立ち会いまで、専門知識を持つ第三者が一貫してサポートするため安心です。
費用が発生します。行政書士にも専門分野があるため、お墓の手続き、特に海外からの依頼に精通した行政書士を選ぶことが重要です。実績・経験がある行政書士に依頼しましょう。
埋葬先の確保と考慮点(海外在住者向け)
(1)新たに墓地を購入する場合の考慮点
新たに墓地を購入する場合、資料等はインターネットで調べることが可能ですが、契約はご自身が行うことになりますので、通常は一度来日する必要があるでしょう。なるべく現地見学を行った上で契約されることをお勧めします。
永代供養墓などの使用料が一括払いの場合、日本にいる親族等に契約をお願いし、納骨時にご自身が現金で支払うといった方法も考えられます。
・お墓選びに関する詳しい情報は、【在日外国人】日本のお墓選び の記事もご参照ください。
(2)既存のお墓(ご自身・親族)に埋葬する場合の考慮点
ご両親・先祖代々の墓を承継し所有している場合、そのお墓に埋葬することも考えられます。この場合、事前に墓地管理者に埋葬する旨を伝え、了承を得ておきましょう。
納骨する際には、石材店に依頼しお墓の蓋を開けてもらい、埋葬を行います。埋葬(改葬)許可証も納骨の際に墓地管理者に提出します。寺院墓地の場合はご住職に供養をして頂いた後に納骨を行います。霊園等の場合もご供養される場合は、ご住職をお呼びして供養をして頂きます。
親族等のお墓に埋葬させてもらう場合も、親族等の墓地所有者(使用者)および墓地管理者の了承が必須です。所有者の許可なく勝手に埋葬することはできませんので、所有者の許可を得た上で埋葬を行う必要があります。また、埋葬する寺院・霊園等により埋葬できる親等数が決められている場合もありますので、こちらも確認しておく必要があります。
日本のお墓に埋葬した後の長期的な注意点(海外在住者向け)
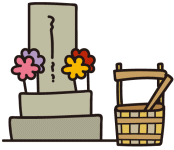
日本のお墓に埋葬した場合も、将来承継者がいない場合は、無縁墓になる可能性があります。無縁墓は墓地管理者により法律で定める手続きを行った後、撤去され遺骨は無縁墓に埋葬されます。また、所有する墓に承継者がいない場合は、墓じまいを求められる場合もあります。
このような将来的なことも踏まえ、埋葬先を決める必要があります。もし将来お墓を継ぐ人がいない場合などは、ご遺骨を永代供養墓に埋葬し、併せて所有する墓も墓じまいして永代供養墓に改葬するといった選択肢も考えられます。
折角、海外から故人の遺骨を日本のお墓に埋葬したのに、その後、誰もお参りに来ずに無縁墓になってしまったのでは、故人も可哀想です。ですので、埋葬するお墓を決める際には、将来的な管理や承継のことも十分に考えて決めてください。
散骨をお考えの場合

近年、日本では、墓じまい後の選択肢として散骨を行う方も多くなっております。散骨の場合、改葬にあたらないため、自治体から改葬許可証が発行されません。つまり改葬許可申請が不要になります。その代わり、散骨業者の所定の申込書、添付書類などが必要になります。
当事務所では、お墓じまいから散骨業者へのご遺骨の引き渡しまでの手続きも行っておりますので、散骨をご希望の場合は、その旨お伝え下さい。(散骨は、一度行うと元には戻せません。お墓参りの場所がなくなり後悔される方もおりますので、よく家族、親族等で話し合いをされてからお決め下さい。)
・散骨の詳細は、【散骨】相談・手続代行 をご覧ください。
まとめ:海外からの日本での埋葬、最適な進め方と専門家サポート

海外にお住まいの方が日本でご遺骨を埋葬する、あるいは既にあるお墓の管理を考える際、その手続きは多くの課題を伴います。
ご自身での来日や日本にいる親族への負担、郵送でのやり取りの難しさなど、海外在住者ならではの困難が伴うため、事前に最適な進め方を検討することが重要です。
大塚法務行政書士事務所は、平成21年(2009年)の開業以来、お墓に関する手続きを専門とし、特に在日外国人の方や海外在住の日本人の方からのご依頼実績が豊富です。
当事務所は、お客様が直面する具体的な状況に応じて、ご自身での対応が難しい部分を専門家としてサポートし、手続きを円滑に進めるお手伝いをいたします。
当事務所へのご依頼
当事務所へのご依頼をご検討の場合、以下のような流れでサポートさせていただきま
・まずはメールにてご連絡ください。海外からの通話料を気にせず、状況や必要なサポート範囲をご記入いただけます。
ご本人確認のため、一度は お電話、LINE、Zoomなどで ご連絡させていただきます。
![]()
・ご依頼いただいた場合、墓地返還に関する書類、石材店からの見積書、改葬許可申請書、改葬先の納骨書類等の一式を当事務所で取得させていただきます。
当事務所の委任状や契約関係に関する書類は、日本に代理人親族等がいない場合、ご本人へ メール、又は郵送させていただきます。
![]()
ご返送いただいた書類が届き次第、関係先に書類の提出を行います。永代供養墓の使用料や石材店のお墓の撤去費は、見積書取得後に入金先を確認し、お客様にご連絡いたします。
事前に霊園や石材店等へお振込みください(当事務所への着手金をいただく場合もあります)。
![]()
・改葬許可証が取得でき次第、関係先との日程調整の上、墓じまい及び改葬を行わせていただきます。当事務所での一式サポートをご依頼の場合、納骨完了まで立ち会わせていただきます。
墓じまいから改葬(納骨)まで写真撮影を行い、書類の控えと併せてお送りさせていただきます。
![]()
納骨まで完了しましたら、その旨ご連絡させていただきます。書類の控え、現地写真、ご請求書は原則メールでお送りいたしますので、当事務所報酬をお振込みください。
日本での埋葬や墓じまいに関するご不安やご不明な点は、どうぞお気軽にご相談ください。経験豊富な行政書士が、お客様の心の負担を少しでも軽くし、スムーズな手続きの完了をサポートいたします。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)











