


・海外で大切な方を亡くされた後、そのご遺骨を日本へ納骨する手続きは、通常の国内での手続きとは異なり、国際的な要素が加わるため複雑に感じられるかもしれません。
この記事では、そうした海外からのご遺骨を日本で埋葬する際の、具体的な手続きの流れと必要書類を網羅的に解説します。スムーズな手続きのためにぜひご活用ください。
1. 海外の遺骨を日本で埋葬する全体の流れ
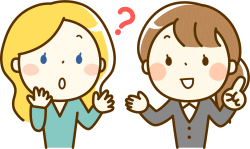
海外にある火葬されたご遺骨を日本の霊園等に埋葬(改葬)する場合、日本の法律に基づき、所定の手続きを経て「改葬許可証」を取得する必要があります。この許可証がなければ、日本での埋葬はできません。
ここでは、遺骨を日本に持ち込み、最終的に納骨するまでの一般的な流れをステップごとに解説します。
ステップ1:埋葬(改葬)許可申請先の確認

まず、改葬許可申請を行う自治体(市区町村)を特定しましょう。原則として、ご遺骨が現在ある場所(日本のご自宅、一時滞在先、親族の住所など)を管轄する市区町村役場が申請先となります。
ご自宅がない場合は日本の滞在先(ホテルや親族等の自宅)が該当しますので、申請前に必ずご確認ください。 申請先が特定できたら、その自治体のウェブサイト等から改葬許可申請書を入手します。
一部の自治体ではダウンロードできない場合もありますので、その際は他の自治体の書式を参考に編集して使用できるか、事前に確認しておくと良いでしょう。
ステップ2:改葬許可申請に必要な書類の準備
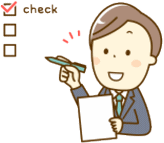
改葬許可申請には、申請書の他にいくつかの重要な書類の添付が必要です。特に海外で発行される書類は、その準備に時間がかかる場合があるため、早めに着手することが重要です。
一般的に求められる主な書類は以下の通りです。
- 死亡地の国又は地域の行政機関発行の「死亡診断書」(大使館発行の死亡証明書)
- 死亡地の国又は地域の行政機関発行の「火葬証明書」
- 本人死亡により除籍された本籍の写し。(除籍謄本)
- 死に至った経緯について申請者による報告書。※
- 死亡者と申請者の続柄がわかる戸籍(家族又は親族等)
- 申請者の身分証明書コピー
- 上記書類の日本語訳文 etc..
※④は不要の場合があります。
- 国や地域によっては、上記以外の書類が求められたり、発行される書類の形式が異なる場合があります。
- 外国語で書かれた書類については、必ず日本語訳文の添付が必要です。
- 少なくとも、死亡診断書、火葬証明書、故人と申請者との続ぎ柄がわかる公的な書類は必要になります。その他、取得が難しい書類については、自治体との打合せの際に確認しておきましょう。
- もし、ご自身で打合せをすることが難しい場合は、当事務所にご相談下さい。
【実例:アメリカ在住の申請者による渋谷区への改葬許可申請ケース】

実際に当事務所で、アメリカで亡くなられた方の遺骨を渋谷区役所へ改葬許可申請し、無事、許可証を取得した事例を挙げさせて頂きます。
申請自治体や個別の事情により必要な書類は異なりますが、死亡者:アメリカ国籍、申請者:日本国籍(アメリカ在住)のケースでは、渋谷区役所との事前打合せの結果、以下の書類一式を提出しました。業務のご依頼から改葬許可証の取得までは、約一か月の期間となりました。
【提出した書類一覧】
① 改葬許可申請書:渋谷区の場合、サイトからダウンロードができないため、郵送にて取得。
② 死亡証明書(州保険局発行):返還を求める場合は、コピーも併せて提出。(原本)
③ 火葬証明書(火葬場発行):返還を求める場合は、コピーも併せて提出。(原本)
④ 婚姻届証明書(州保険局発行):申請者と死亡者の続き柄を示す書類として提出。(写し)
⑤ 骨壺の写真:骨壺に死亡者の名前が記載されている箇所を撮影し提出。
⑥ 日本語翻訳文:②~⑥の書類
⑦ サイン証明書(日本国総領事館発行):申請者がアメリカ在住で印鑑がないため、サイン証明書を提出(原本)
⑧ 受入れ証明書:埋葬先の墓地管理者から取得。(書式については当事務所にて作成。)(原本)
⑨ 身分証明書:死亡者と申請者の身分証明書。(パスポート・免許証等)(写し)
⑩ 申述書:提出した書類が真正なものであり、虚偽・偽りがないことを誓約する書類。(書式は当事務所で作成。)(原本)
⑪ 委任状:申請者から当事務所への委任状
【業務の流れ】
本件では、最初にメールでご連絡をいただき、その後はLINEにて連絡を行いました。まずは、お客様に現地(アメリカ)の書類をご準備いただき、その書類の写真等をお送りいただきました。
その資料をもとに役所との打ち合わせを行い、不足資料などがあればその書類も併せて準備します。特に問題がなければ、当方から改葬許可申請書や委任状等の署名押印を頂く書類をメールまたは郵送(EMS等)にてお送りし、届き次第、現地で取得された書類と併せてご返送いただきます。到着後、速やかに申請を行う流れとなります。
ステップ3:埋葬先の決定と契約

改葬許可申請書には、遺骨を埋葬する新たな場所(改葬先)の住所を記載する欄があります。そのため、申請を行う前に埋葬先を決めておくことが推奨されます。
① 埋葬先の種類
日本には、寺院墓地、公営霊園、民営霊園(納骨堂、樹木葬、永代供養墓など)様々な埋葬先があります。ご自身の宗教・宗派や、将来の承継者の有無などを考慮して選びましょう。
② 霊園・寺院との契約
改葬許可申請の際に「使用許可証の原本提示」や「受入れ証明書」の添付を求められる場合があります。この場合、改葬許可証の取得前に霊園等との契約が必要となります。霊園や寺院が設ける条件が、埋葬先の選択や契約を困難にすることもありますので良く確認したうえで契約をして下さい。
※契約後、改葬許可証が発行されないと契約が無駄になります。許可証の発行に問題がないと判断出来てから契約を行いましょう。
・埋葬先の選び方や、外国籍の方が日本でお墓を選ぶ際の注意点については、【在日外国人】日本のお墓選び」もご参照ください。
ステップ4:自治体への改葬許可申請

必要書類がすべて揃ったら、ご遺骨の現在地を管轄する市区町村役場へ改葬許可申請を行います。
① 申請方法
申請書、添付書類の原本、身分証明書、翻訳文等を準備し、窓口へ直接提出する方法と、郵送で申請する方法があります。郵送の場合は時間がかかることがあるため、急ぐ場合は窓口での提出が望ましいでしょう。
②許可証の取得
申請が受理されれば、通常その場で改葬許可証が発行されます(東京都の場合など)。この許可証は納骨の際に必要となりますので、大切に保管してください。
厚生労働省の通知により、海外で火葬されたご遺骨を日本に埋葬する場合、それを「改葬」とみなし、ご遺骨が現に存する地の市区町村長、または死亡届を受理した市区町村長が特例として改葬許可を行うことが定められています。この際、市区町村長が「海外で火葬した事実を証する書面」を発行し、それが埋蔵等の事実を証する書面に代わることになります。
【 参考 】
○海外で火葬した焼骨の埋蔵又は収蔵をするための許可について(令和2年11月6日)薬生衛発1105第1号
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)
記
1 海外で火葬した焼骨の埋蔵等をする場合には、これを法第2条第3項に規定する改葬とみなし、焼骨の現に存する地の市町村長又は死亡の届出を受理した市町村長が特例として改葬許可を行うこと。
2 1の改葬許可を行うに当たり、当該市町村長は、海外で火葬したことの事実を証する書面を発行し、これを墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第2条第2項第1号に規定する墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋蔵等の事実を証する書面に代えること。
ステップ5:ご遺骨の日本への移動
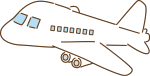
改葬許可証が発行されたら、ご遺骨を日本へ移動させる準備を進めます。
① 移動方法
骨壺のまま移動するか、骨袋に移し替えるかなどを検討します。ご遺骨は破損の可能性があるため、多くの場合、手荷物として機内に持ち込むことが推奨されますが、航空会社の手荷物制限(個数、大きさ、重量)にご注意ください。遺骨数が多い場合は、骨壺のままでは持ち込めない場合もあります。
② 携帯書類
念のため、改葬許可証の原本と英訳文も携行することをお勧めします。
ステップ6:霊園・寺院でのご納骨
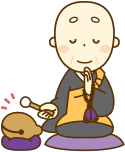
ご遺骨を日本へ移動させたら、事前に契約した霊園や寺院で納骨を行います。
① 納骨の予約
納骨には事前予約が必要な場合がほとんどです。特に土日祝日は混み合うことが多いため、希望日がある場合は早めに予約を入れましょう。
② 必要書類
納骨の際には、取得した改葬許可証を霊園等の管理者に提出します。
③ 供養
寺院墓地の場合はご住職による供養が、霊園等の場合も希望に応じて供養が行われます。
・海外から日本へ遺骨を埋葬する際によくあるトラブルと、その対策については、【海外から日本へ】遺骨埋葬のトラブルと予防策 もご参照ください。
2. 日本への遺体搬送の手続き(ご参考)
海外で亡くなられたご遺体を火葬せずに日本へ搬送する場合、手続きは異なります。
ご遺体を日本へ搬送した際には、到着時にその場所の市区町村に死亡届を提出し、埋葬許可書の申請を行います。この際、死亡届には現地医師による死亡診断書(外国語の場合は申請者が和訳したもの)を添付する必要があります。
海外からのご遺体の搬送については、遺体を日本へ搬送する取扱規定に関する件等により、ご遺体の防腐処理(エンバーミング)、棺への固定、領事館員による封印が行われ搬送されることになります。国や地域により規定が異なる場合があるため、事前に大使館等への確認が不可欠です。
3. 手続きをスムーズに進めるためのポイント

海外からのご遺骨の埋葬手続きは、時間と専門知識を要します。スムーズに進めるためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
必要書類の特定、埋葬先の選定、遺骨の搬送方法など、全てにおいて早めの情報収集と綿密な計画が重要です。
日本に協力してくれる親族や知人がいる場合、書類の郵送や現地での確認などを依頼することで、手続きが格段にスムーズになります。
書類の取得や和訳、自治体との事前協議、霊園との契約、遺骨の搬送など、専門的な知識が必要な場面や、ご自身での対応が難しいと感じる場合は、専門家へ相談することを検討しましょう。
まとめ:海外からの埋葬手続きは専門家にご相談ください

海外で大切な方を亡くされた際の日本へのご遺骨の改葬(埋葬)は、想像以上に複雑で、多大な時間と労力を要するものです。
日本の法律や慣習、国際的な書類の取り扱いなど、専門知識が不可欠であり、ご自身で対応するには様々なトラブルに繋がるリスクも少なくありません。
大塚法務行政書士事務所は、平成21年(2009年)の開業以来、お墓に関する手続きを専門とし、特に在日外国人の方や海外在住の日本人の方からのご依頼実績が豊富です。
海外からのご遺骨の埋葬手続きに関するご不安やご不明な点は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。お客様の心の負担を少しでも軽くし、スムーズな手続きの完了をサポートいたします。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)











