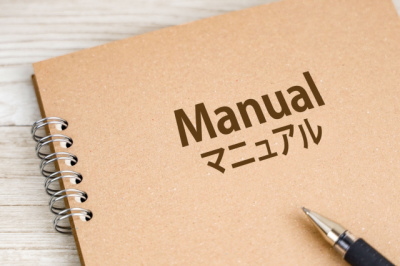・現在のお墓を墓じまいしたいが、その後の遺骨をどうしたら良いか」「遠方にあるお墓を近くに移したいけれど、新しい供養先として永代供養墓を考えている」このようなお悩みをお持ちの方へ。
このページでは、この改葬後の新たな供養先として永代供養墓を選ぶ際の具体的な手続きや、知っておくべき注意点に焦点を当てて行政書士が解説します。
特に、お墓から改葬する際に発生しやすいトラブルを避け、スムーズに永代供養墓へ納骨するためのポイントをご紹介いたします。
※墓じまいをして、新しい場所に遺骨を納骨することを「改葬(かいそう)」といいます。
1. 改葬後の永代供養墓が選ばれる理由とメリット
墓じまいや改葬の後の受け入れ先として、近年永代供養墓を選ぶ方が増えています。その主な理由とメリットは以下の通りです。
(1)承継者や管理負担の心配が不要
永代供養墓は、寺院や霊園が永代にわたって供養と管理を行うため、お墓の承継者がいない場合でも安心です。残された家族に管理や費用の負担をかける心配がありません。
(2)費用が明確で比較的安価
通常のお墓を新たに建立するよりも初期費用が抑えられる傾向にあり、年間管理費もかからない場合が多いため、経済的な負担を軽減できます。
(3)多様なニーズに対応
核家族化や少子高齢化、ライフスタイルの変化により、従来の「家のお墓」の維持が困難になるケースが増えています。永代供養墓は、このような現代社会の多様な供養ニーズに対応できる柔軟性があります。
2. 改葬後の永代供養墓選びの具体的な流れと手続き
既にお墓がある方が永代供養墓へ改葬する際には、改葬許可申請をはじめとする手続きが必要です。一般的なお墓選びとは異なる確認事項もありますので、順を追って進めましょう。
(1)まずは永代供養墓の情報収集と検討

- 希望条件の明確化: 永代供養墓の形式(合祀、個別埋葬、納骨堂、樹木葬など)、費用、場所、宗派の有無などを検討します。
- 情報収集と見学: 複数の永代供養墓の資料を取り寄せ、実際に現地を見学し、雰囲気や管理状況、交通の便などを確認します。
・永代供養墓の種類や詳細な選び方については、【永代供養墓】基礎知識・選び方 で詳しく解説しています。
(2)既存のお墓の管理者(寺院・霊園)への相談と理解
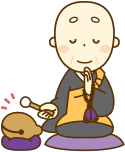
改葬手続きの中で最も重要かつ慎重に行うべきステップです。
墓じまいや改葬の意向を、現在の墓地管理者(寺院のご住職など)に直接、丁寧に説明しましょう。突然の通知ではなく、事前にアポイントを取り、理解と協力を求める姿勢が大切です。
寺院墓地の場合、離檀料を請求されるケースや、話し合いが難航する場合があります。離檀料は法的な支払い義務はないものの、これまでの寺院へのお礼として、円満解決を目指す姿勢が重要です。ご自身の状況を正直に伝え、話し合いで解決を図ることが原則です。
・離檀料の一般的な相場や詳しい進め方については、【離檀料の相場】墓じまい・改葬時の注意点 で詳しく解説しています。
・こちらの記事、【墓じまい】住職に会いたくない場合の進め方 で解説しています。
・こちらの記事、【高額離檀料請求】墓じまい対処法で解説しています。
(3)改葬許可申請の手続き
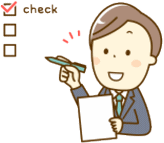
ご遺骨を別の場所に移す(改葬する)際には、現在の墓地がある市区町村役場での改葬許可申請が必要です。
現在、お墓がある場所管轄する役場で取得します。墓地管理者の記名押印が必要になります。(埋葬事実証明)
改葬許可申請時に添付が求められる場合あります。改葬先の永代供養墓の管理者から発行してもらいます。
ご遺骨者の死亡記載のある戸籍、家系図など自治体により求められる場合があります。詳細は管轄に自治体にご確認下さい。
必要書類を揃え、役場に申請し、改葬許可証を受け取ります。この許可証がないと、遺骨を移すことができません。
・詳しくは、【改葬許可申請書】取得・記入方法と必要書類 の記事をご覧ください。
(4)遺骨の取り出しと永代供養墓への納骨
改葬許可証が発行されたら、現在の墓地から遺骨を取り出します。
墓石から故人の魂を抜き、単なる「石」に戻す儀式です。寺院の僧侶にお願いするのが一般的です。
・この際の「お布施」については、【墓じまいのお布施】相場・渡し方・注意点で詳しく解説しています。
お墓の撤去は、原則として墓地が指定する石材店が行います。
事前に永代供養墓の管理者と相談して決めた日時に納骨を行います。この際、必ず改葬許可証(または埋葬許可証)が必要です。
・納骨時の具体的な手順や注意点は、【納骨の基礎知識】時期・場所・手順を解説 に関する記事も参考にしてください。
3. 改葬に伴う永代供養墓の費用と相場
改葬して永代供養墓に納骨する場合、永代供養墓自体の費用に加えて、墓じまいに関する費用が発生します。
(1)永代供養墓自体の費用
- 合祀タイプ: 5万円~50万円程度(最も安価)
- 個別埋葬タイプ(永代供養塔、樹木葬、納骨堂の一部): 10万円~200万円程度
・永代供養墓の費用相場については、【永代供養墓】基礎知識・選び方をご覧ください。
(2)墓じまい(改葬元)で発生する費用
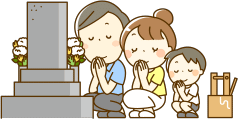
寺院墓地の場合、お寺との関係を清算する際に支払う費用。お布施という形で渡すことが多く、明確な相場はありませんが、トラブルになりやすい費用でもあります。(必ず請求される訳ではありません。寺院により異なります。)
・離檀料の考え方や対処法は、【離檀料の相場】墓じまい・改葬時の注意点で詳しく解説しています。
墓石の解体・撤去、基礎の撤去、整地などにかかる費用。墓地の広さや石材の種類によって異なりますが、数十万円から100万円以上かかることもあります。
墓石から魂を抜く儀式にかかるお布施。
・このお布施の相場や渡し方は、【墓じまいのお布施】相場・渡し方・注意点 で詳しく解説しています。
4. 改葬先の永代供養墓選びで注意すべきポイント
以下の点に特に注意して永代供養墓を選びましょう。
(1)親族への十分な説明と合意形成
墓じまいや改葬は、親族にとって感情的な問題となることが多いため、事前に十分な話し合いを行い、理解と合意を得ておくことが重要です。特に、永代供養墓への合祀は、後から遺骨を取り出せないため、トラブルを避けるためにも、承諾を得ておきましょう。
(2)新しい管理者の信頼性
改葬後の永代供養墓は、その後の管理・供養を完全に任せることになります。そのため、運営母体(寺院、民間事業者、自治体など)の経営状況、過去の実績、管理体制、担当者の対応などをしっかりと確認し、信頼できる場所を選ぶことが重要です。
(3)永代供養の期間と供養内容の確認
「永代」という言葉に惑わされず、具体的に何年間、どのように供養・管理されるのかを契約書で確認しましょう。13回忌、33回忌など何年後に期間満了ななるのか。その際に、どこに合祀されるのかなども重要です。また、個別の法要の可否や費用も事前に確認しておくと良いでしょう。
5. まとめ

墓じまいや改葬は、多くの方にとって一生に一度あるかないかの大きな決断であり、複雑な手続きや関係者との調整が伴います。永代供養墓は、現代のライフスタイルに合った有効な選択肢ですが、特に改葬を伴う場合は、通常の墓地探し以上に慎重に進める必要があります。
当事務所は、お墓の手続きを専門とする行政書士事務所です。改葬や墓じまい、そしてその後の永代供養墓選びまで、豊富な経験と実績を持つ行政書士が、書類作成から関係者との調整、現地立会まで一貫してサポートいたします。
お墓じまいや改葬のお悩み、行政手続きなど、ご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。東京都葛飾区より全国対応、無料相談を受け付けております。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)