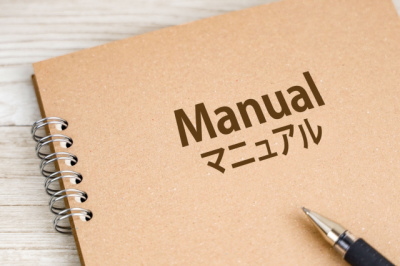・墓じまいや改葬(お墓の引っ越し)を検討する際、寺院にお墓がある方にとって「離檀(りだん)」、そしてそれに伴う「離檀料(りだんりょう)」は大きな懸念事項の一つです。
「離檀料って、いくらくらいが相場なの?」「お寺との関係を円満に終えるにはどうすればいいの?」「高額な離檀料を請求されたらどうすればいい?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
このページでは、離檀料の基本的な意味から、その相場、適切な進め方、支払い方法、そしてトラブルを避けるための具体的な注意点まで、行政書士が徹底解説いたします。円満な離檀を実現し、安心して次の供養へと進むための参考にして下さい。
1. 離檀(りだん)とは?離檀料の基本的な考え方
(1)離檀とは
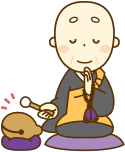
離檀とは、特定の寺院の檀家(だんか)をやめることを指します。寺院にお墓を建てる場合、その寺院の檀家となることが前提となることが多く、檀家は寺院の維持・運営を支える役割を担っています。墓じまいを行う場合、寺院との縁も無くなりますので、離檀することになります。
(2)離檀料とは
離檀料とは、檀家として長年お世話になった寺院に対し、これまでの感謝の気持ちとして、また寺院の維持・運営への協力金として支払う金銭を指します。法的に支払いが義務付けられているものではなく、あくまで慣習や感謝の気持ちとして渡されるものです。
(3)離檀料とお布施の違い
離檀料は、法要やお墓の供養に対する「お布施」とは性質が異なります。お布施は仏事に対する感謝の気持ちを表すものですが、離檀料は檀家関係を解消する際に、これまでの感謝の意を込めて渡す金銭と理解されています。ただし、離檀料という明確な項目を設けず、「お布施」という形で渡すよう指示される場合もあります。
2. 離檀料の相場と費用の考え方
(1)離檀料の一般的な相場

離檀料には明確な相場がなく、寺院の考え方や地域、檀家であった期間、寺院への貢献度などによって大きく異なります。一般的には、10万円から20万円程度が目安と言われることが多いですが、最高金額は多くても20万円くらいが妥当と言われています。中には50万円以上、あるいはそれ以上の高額な離檀料を提示されるケースもあります。
- 寺院の規模や格式
- 檀家であった期間や寺院への貢献度
- 地域による慣習の違い
- トラブルの有無や話し合いの進め方
(2)離檀料は必ず請求されるのか?
離檀料は必ず請求されるものではなく、寺院により請求される場合・されない場合があります。当事務所でこれまでに、お聞きしたケースでは、約半数程度の方が請求され、残りの半数の方が請求されていない状況です。請求される場合は、離檀の話をした際に、最初に金額を伝えられる場合が多いようです。
(3)離檀料に法的根拠はない?
離檀料は法律で定められた費用ではないため、その金額に法的な拘束力はないと思われます。しかし、長年お世話になった寺院への感謝の気持ちとして、円満な関係を保つために支払う方が多いようです。
3. 円満な離檀の進め方と離檀料の支払い方法
円満に離檀を進めるためには、寺院への配慮と丁寧な対応が不可欠です。
(1)離檀の理由を丁寧に説明する
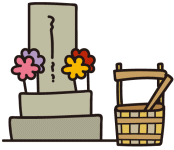
墓じまいや改葬を決めてから報告するのではなく、早い段階で「相談」としてご住職に意向を伝えましょう。
「自宅から墓地が遠くお参りに不便なため」「承継者がいないため永代供養墓に埋葬したい」など、具体的な理由を丁寧に説明することが大切です。金銭的な理由を前面に出すより、やむを得ない事情であることを理解してもらう方が、円満な話し合いにつながりやすいです。
・墓じまいする際のご住職への話し方については、墓じまいする際のご住職への話し方に関する記事 も参考にしてください。
(2)必要な費用や書類を確認する
離檀の意向を伝えた後、ご住職から離檀に関する話(離檀届等の書類、お墓の撤去に関する石材店のこと、閉眼供養の時期など)が出ることがあります。この際に、離檀料の有無や金額についても確認しましょう。
改葬許可申請書に寺院(墓地管理者)の記名押印が必要になりますので、その書類についても確認しておきましょう。
(3)閉眼供養と離檀完了
書類の準備が整い、ご住職・石材店と調整の上、閉眼供養日を決めます。供養完了後にご遺骨を取り出し、改葬先に埋葬を行います。お墓は後日、石材店により撤去されます。通常の場合、閉眼供養日を持って離檀完了となります。
(4)離檀料の支払い方法
離檀料を支払う場合は、一般的に現金で、白無地の封筒に入れるか、のし袋に入れて渡します。表書きは「御布施」「御懇志」「御礼」などとし、下段には氏名を書きます。渡すタイミングは、閉眼供養の前後や、お世話になったことへの感謝を伝える場など、寺院の指示に従うのが良いでしょう。
(5)離檀届・墓地返還届について
寺院から離檀する際には、「離檀届」や「墓地返還届」といった書類の提出を求められる場合があります。これらは寺院が檀家関係の終了や墓地の返還を正式に記録するためのものであり、寺院が独自に定めていることがほとんどです。
・これらの書類の書き方や、ひな形(テンプレート)について詳しく知りたい方は、離檀届・墓地返還届(ひな形)について解説 の記事をご覧ください。
4. 離檀料を巡るトラブルと対処法
離檀料は法的な根拠がないため、その金額や支払いについてトラブルになるケースも少なくありません。
(1)高額な離檀料を請求された場合

相場を著しく超える高額な離檀料を請求された場合は、以下のような対処法が考えられます。
まずは冷静に、請求された金額の根拠や内訳について、寺院に説明を求めましょう。
話し合いが困難な場合や、法外な金額を請求されたなど個別具体的な交渉が必要な場合は、弁護士などの専門家や国民生活センターにご相談ください。お客様のご希望により、当事務所から弁護士をご紹介することも可能です。
・高額な離檀料を請求された場合の具体的な対処法は、高額な離檀料を請求されたら どうすれば良いか?で詳しく解説しています。
(2)離檀料を支払わないとどうなる?
離檀料の支払いは法的義務ではないため、支払いを拒否しても罰則はありません。しかし、寺院との関係がこじれると、改葬に必要な書類(改葬許可申請書への記名押印、埋蔵証明書など)の発行を拒否されるなど、手続きが滞る可能性もあります。円満な解決が最も望ましいと言えます。
5. まとめ

寺院から離檀することは、あまり経験することではないため、不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。テレビ等で高額な離檀料の請求事例が紹介され、「我が家も請求されたら、どうしよう?」と更に不安が増すこともあるかもしれません。
しかし、離檀料は必ずしも請求されるわけではなく、また高額な請求をされるケースもそれほど多くないと言えます。請求されるがままに支払う義務があるわけでもありません。
ですので、まずはご住職に失礼のないよう、きちんとすべきことを行い、誠意を持って対応することが重要です。高額な費用を言われた場合も、まずは冷静に話し合いをしてみましょう。
それでも聞き入れられない場合や、最初からご自身での対応に自信がない場合は、弁護士や国民生活センター・消費生活センターなどの専門機関に相談することも一つの方法となります。
※当事務所は、お墓の手続きを専門としている行政書士事務所です。これまで100件以上のお墓じまいや改葬などをお手伝いしてまいりました。墓じまい・改葬に関する各種手続きのご相談、書類作成、行政上の手続きなど、幅広くサポートさせて頂いております。
お墓のことでお困りのことなどありましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。お客様のご希望により、当事務所から弁護士をご紹介することも可能です。
【追記】離檀料の近年状況(令和7年現在)

この記事を作成してから年月が経ちましたが、現在でも離檀料についてご心配される方が非常に多い状況です。
インターネットなどでは「離檀料を支払う義務はない」という記事もよく見かけますが、実際のところ、昔のような法外な高額離檀料を請求する寺院は、一部を除き少なくなっている傾向にあります。
最近よくお聞きするのは、10万円~30万円程度が最も多く、それ以上でも200万円~300万円程度のケースがあるかと思います。(現在でも一部の寺院では、数百万円の離檀料を請求するケースも存在します。)
これらの金額はあくまで請求された場合の例であり、請求されない寺院も多く存在します。また、宗派が同じでも、寺院によって金額が異なるのが実情です。(近年、ご住職の代替わりが進み、お布施等の金額が変わったというお話も伺うことがあります。)
なお、離檀料を請求されない場合でも、通常は閉眼供養を行っていただき、これまでの感謝としてお布施をお渡しします。この金額は3万円~5万円程度が現在でも一般的です。
離檀料が心配な方は、まずは寺院に直接、墓じまいを行った場合の金額を確認してみるのが良いでしょう。もし伝えられた金額が高額だと感じたら、値下げの交渉を試みたり、それでも応じてもらえない場合は、国民生活センターや弁護士などの専門家にご相談する流れが適切です。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)